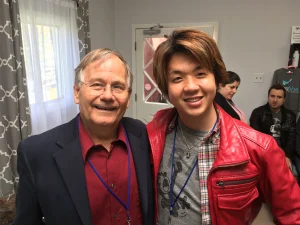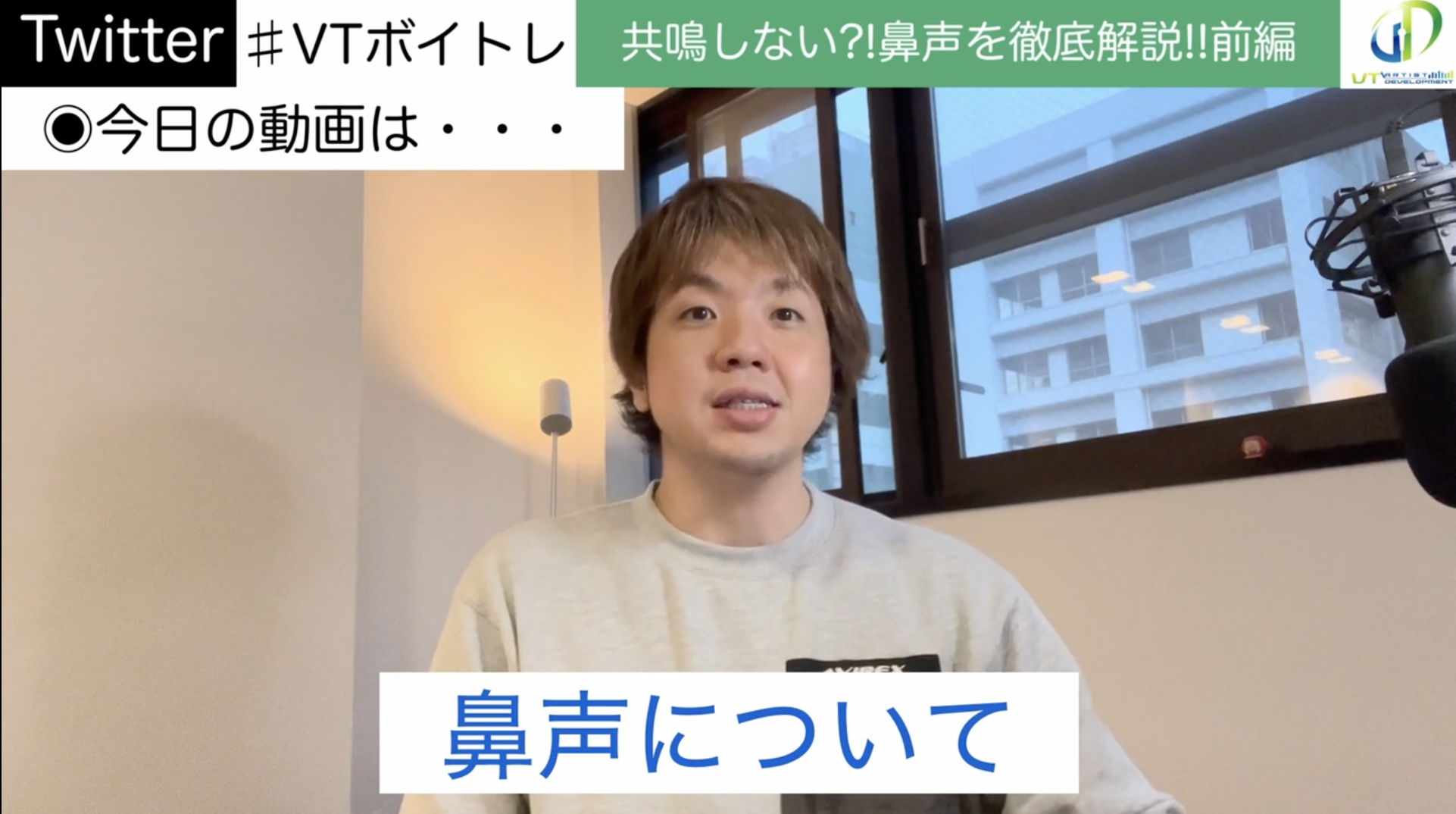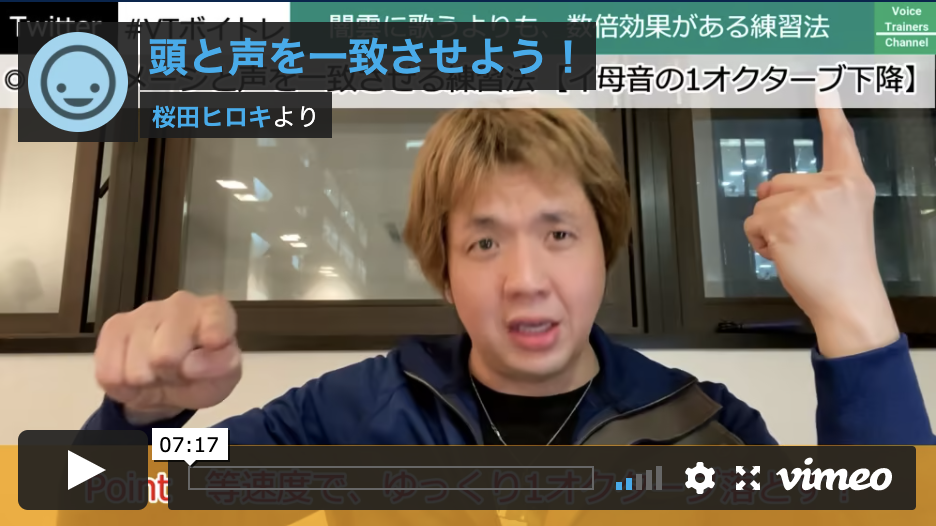加齢と声の関係:歌手にとって避けて通れない課題(第1回 イントロダクション)
はじめに―声は「年齢を映す鏡」
人の身体は年齢とともに変化していきます。顔にしわが増えたり、筋力や持久力が落ちたりするのと同じように、声もまた年齢を重ねるごとに変化します。歌手にとってそれは深刻です。なぜなら、自分の身体そのものが楽器だからです。ピアノやヴァイオリンのように外部の楽器を交換することはできません。変化を受け入れ、その中でどう表現するかを考えることこそ、歌い続けるための道なのです。
歌唱の特性―声を“作りながら”操作法を学ぶ生涯のプロセス
歌唱は、与えられた楽器をただ鳴らす行為ではありません。日々のボイストレーニングを通じて声という楽器を育てながら、その操作方法を学び続ける営みです。もし一生歌い続けるなら、自分の声の変化を観察し、そこから学び、発声の方法を常に更新し続ける必要があります。
このプロセスは一見大変に思えるかもしれません。しかし見方を変えれば、声の変化を楽しみ、学び続けられることが歌手の特権です。年齢を重ねることで深まる声の響きや質感を、新しい表現へと変えていくことは、アーティストにとって大きな喜びとなります。
加齢による声の変化―研究から見えること
声の変化は組織学、生理機能、音響的な面から観察されています。
組織学的変化:声帯粘膜に含まれる弾性線維や膠原線維が加齢とともに変化し、張りや柔軟性が低下します(Sato & Hirano, 1997)。その結果、声の明るさが失われ、高音が出にくくなります。
生理機能の低下:呼吸機能の衰えによって肺活量や呼吸筋のコントロールが難しくなり、声の強さや持続力が落ちます(Stathopoulos et al., 2010)。長いフレーズが苦しくなるのはこのためです。
音響的変化:加齢によりF0(基音)、声の揺れ(jitter/shimmer)、声の明瞭さを示すCPPSなどに変化が見られます。
これらの変化は、歌手だけでなくSLP(言語聴覚士)やボイストレーナーにとっても臨床・教育現場で重要な情報です。
男女で異なる変化―ホルモンと声の関係
加齢による声の変化は男女で異なります。
男性では、声帯筋の萎縮や甲状軟骨の骨化が進み、声帯閉鎖が不十分になりやすい。その結果、声が息っぽくなり、声量が落ちやすくなります。
女性では、更年期以降にホルモンバランスが大きく変化します。エストロゲンの低下により声帯の潤滑性が失われ、乾燥感や声の疲労感が増えます。さらに、高音域が失われ、F0も低下(声が低くなる)していきます(Marchese et al., 2022)。
Vorperianら(2018)の研究によれば、女性のF0は加齢とともに下がる一方、男性は比較的安定し、高齢になるとむしろ上がることもあるとされています。こうした差は、歌手が選ぶレパートリーや発声法に直接影響を及ぼします。
喉頭枠組みの変化―甲状軟骨と発声の可動性
歌声のピッチは声帯の張力だけでなく、喉頭枠組みの柔軟性にも依存します。
近年の研究では、甲状軟骨は思春期以降も年齢とともに形や大きさが変化することが分かっています(Riede et al., 2023)。
また、プロ女性歌手を対象とした研究では、甲状軟骨の変形は年齢が高くなるほど小さくなる、つまり柔軟性が失われることが示されました(Unteregger et al., 2019)。
このような枠組みの硬化は、特に高音を支える際に影響し、声の伸びや明るさを制限する要因となります。
歌手は変化に敏感―ボイストレーニングの意義
歌手は声を限界まで使うため、わずかな変化も敏感に察知します。
数Hzのピッチ変化や、わずかな声質の変化でも、パフォーマンスに大きく響きます。
だからこそ、日常的なボイストレーニングが重要です。
SOVT(ストロー発声やリップバブル等)やレゾナント・ボイストレーニングは、発声効率を改善する科学的根拠があり、加齢による声の変化を和らげるのに有効とされています。
発声閾値圧(PTP/発話の始まりの努力度と認識出来ます)を下げ、声門近傍圧を高めることで、声帯への負担を減らす効果があります。
これらは声を持続的に健康に使うための“経済的発声”を可能にします。
ボイストレーナーと取り組む年齢適応型の声作り
加齢による変化は避けられませんが、ボイストレーナーと共にボイストレーニングを設計し、身体の変化へ順応させることができます。
・呼吸・支持を再調整し、長いフレーズに対応できるようにする。
・声帯閉鎖の再学習を通じて、息漏れの少ない声を取り戻す。
・共鳴腔の変化を踏まえて、母音や響きの位置を微調整する。
SLPやボイストレーナーは、これらの調整を科学的根拠に基づき指導する役割を担います。専門的な視点で加齢声を分析し、歌手一人ひとりに最適なボイストレーニングを提供できることが、長い歌手人生を支える鍵です。
まとめ―変化を受け入れ、声を作り直す喜び
加齢は誰にでも訪れます。
しかし、声は学び直し、作り直すことができる楽器です。
研究は、声帯や喉頭の変化を明らかにしていますが、それと同時に、適切なトレーニングや調整で表現を広げる可能性も示しています。
次回以降は、男性・女性それぞれの加齢変化をさらに詳しく見ていき、ボイストレーニングやボイストレーナーによる具体的なアプローチを紹介していきます。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話