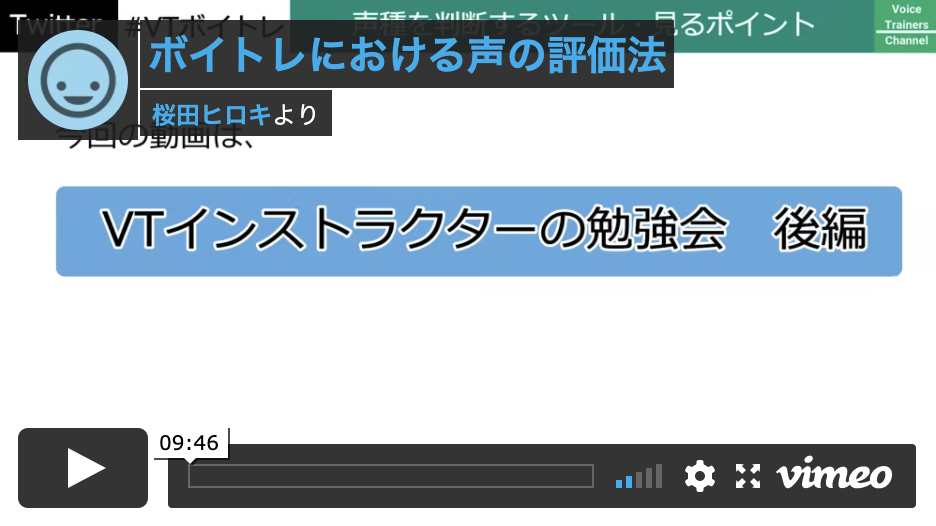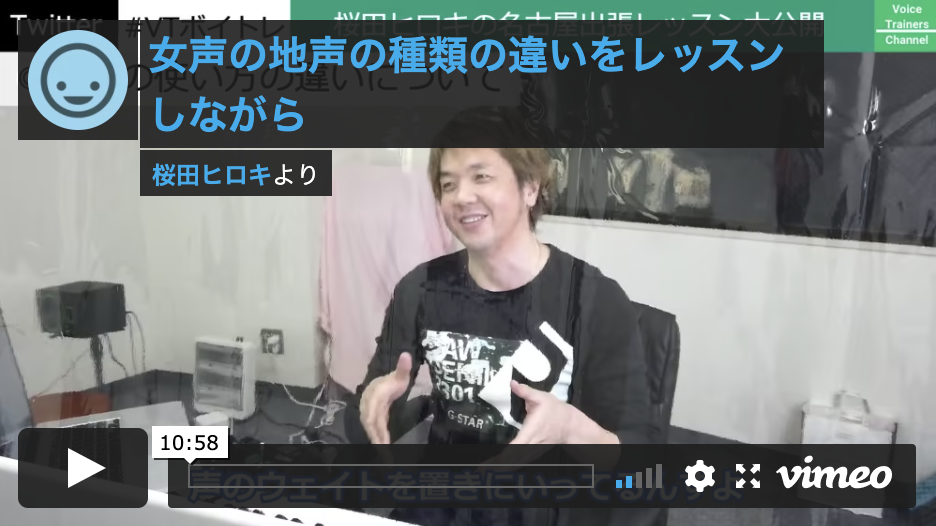- 2025.09.10
- ボイストレーナー育成 マインドセット・練習法 ミックスボイス
第4話:モチベーションと学習環境 ― 歌唱を続ける力を育てる
歌唱スキルは、正しい練習方法だけでなく「続けられる力」に大きく左右されます。
そもそもボイストレーニングにおけるタスクや、楽曲そのものの難易度を正確に理解すること自体が難しく、多くの学習者が「この曲は自分に合っているのか」「なぜ歌いにくいのか」と迷います。
こうした状況で、モチベーションが続かない、練習が習慣にならないといった問題は頻繁に起こります。ここでは、心理学と教育学の研究をもとに、歌唱の学習を支えるモチベーションと学習環境の設計について考えます。
1. 内発的動機づけと外発的動機づけ
自己決定理論(Self-Determination Theory, Deci & Ryan, 1985; 2000) によれば、モチベーションには「内発的」と「外発的」があり、長期的な学習継続には「自律性・有能感・関係性」の3つが満たされることが重要です。
歌手にとっては:
– 自律性(Autonomy):自分で練習方法や曲を選べる感覚
– 有能感(Competence):小さな成功体験を積み重ねること
– 関係性(Relatedness):信頼できるボイストレーナーや仲間の存在
これら3つはいずれも内発的動機づけの基盤とされており、満たされることで「自分の内側からやりたい!」という意欲が生まれます。逆に欠けると、外発的な要因(発表会で褒められる、オーディションに合格する、先生に叱られないようにする等)に依存しやすくなり、長期的には練習の持続が難しくなります。
2. フィードバックとモチベーション
自己効力感(self-efficacy, Bandura, 1997) は「できる感覚」を伴うと次の挑戦を生みます。
そのため、フィードバックは:
– できなかった点の指摘「だけ」ではなく
– できた点を強調しつつ、改善点を明確に示す
というバランスが求められます。
さらに OPTIMAL理論(Wulf & Lewthwaite, 2016) では、外的フォーカス、自律的選択、ポジティブなフィードバックが揃うと、学習効率が最大化されるとされています。これはボイストレーニングにおいても有効で、言葉選び一つで練習の質が変わることを示しています。
3. 学習環境と課題設定
ヴィゴツキーの最近接発達領域(ZPD, 1978) によると、学習は「少し背伸びすればできる課題」で最も効果的に進みます。簡単すぎても難しすぎてもモチベーションは下がってしまうのです。
歌唱では「楽曲選び」がZPDの設計に直結します。そこでボイストレーナーが意識すべきは、楽曲のハードルを異常に高くしないこと、そして難易度を冷静に分析することです。
楽曲難易度の分析指標
① 中〜高音域の出題頻度
– 男性:E4以上の出題が多く、さらにC4以下の着地音が少ない曲は要注意
– 女性:G4以上の出題が多く、さらにE4以下の着地音が少ない曲は要注意
② 伸ばす音(Sustain Note)の頻度と高さ
– 伸ばす音が多い楽曲は難しい。(Journey / Open Arms等良い例だと思います)
③ 上昇フレーズの頻度
– 一般的には下降フレーズの方が容易
④ ベルト・ノート(Belting Note)の出題頻度
– 強く出す音が多いほど難しい(My Days ミュージカルNotebookより/ Defying Gravity/Wickedより)
⑤ リフの速度・音数
リフが速く長いほど難しい(Don’t you worry bout a thing/ Tori Kelly)
4. 課題曲の選択とモチベーション
自己決定理論の観点からは、学習者に「選択権」を与えることがモチベーションを高めます。
ただし、楽曲の難易度を見極めるには知識と自己評価の正確さが必要です。
そのため、効果的な流れは次のようになります。
– 最初の数曲:ボイストレーナーが課題として提示
– その後:生徒とボイストレーナーが交互に課題曲を提案
この方法により:
– 学習者は「自分で選ぶ」自律性を感じられる
– ボイストレーナーは適切な範囲での導きを提供できる
結果として、学習効果とモチベーションの両立が可能となります。
5. まとめ
– モチベーションはボイストレーニングの継続と成果を左右する
– 自律性・有能感・関係性はいずれも内発的動機づけの基盤である
– フィードバックは「できた点+改善点」の両方を含める
– 楽曲選びはZPDに基づき、難易度を分析して設定する
– 課題曲はボイストレーナーと生徒が協力して選ぶことで自律性と導きを両立できる
次回(第5話)では「練習時間の設計と集中力」に注目し、歌唱スキルを効率よく積み重ねる方法を探ります。
歌手の運動学習シリーズ
第1話:歌手の学習方法を学ぼう!― 基礎理論とフィードバック
第2話:練習とフォーカスの科学 ― 効率的なスキル定着
第3話:失敗を味方につける歌の練習・ボイストレーニング
第4話:モチベーションと学習環境 ― 歌唱を続ける力を育てる
第5話:練習時間の設計と集中力 ― 効果的に声を育てる
第6話:自動化とフロー状態 ― 歌唱におけるゾーン体験
第7話:自分の歌をどう確認する?ーフィードバック環境の設計
第8話:模倣学習と観察学習 ― ボイストレーニングにおけるモデルの力
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話