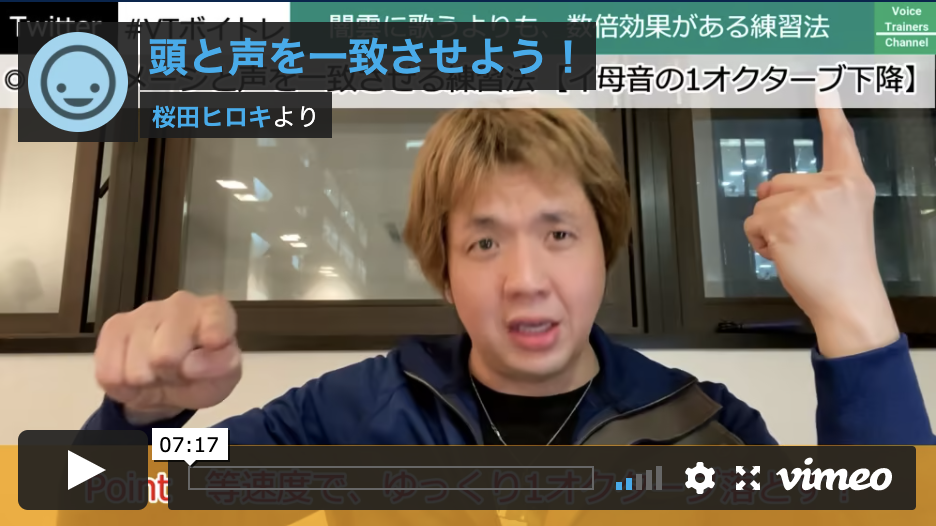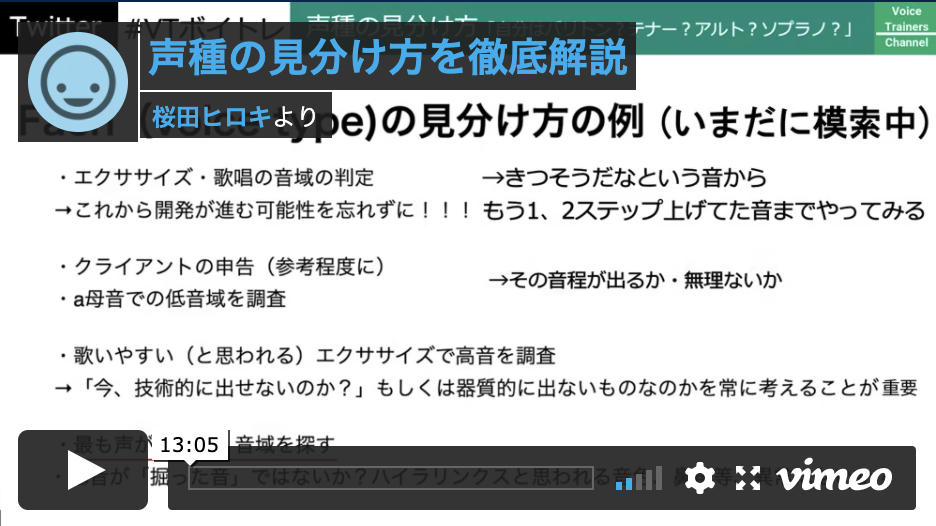-
歌手の機能性発声障害 第8話:予防とセルフケア ― 障害を起こさないためのボイストレーニング
第8話:予防法 ― 障害を起こさないためのボイストレーニング 歌手にとって、声は単なる道具ではなく「表現のすべて」を担うものです。しかし、声の障害に悩む歌手は少なくありません。結節やポリープのような器質的病変から、機能性発声障害と呼ばれるパターンまで、その多くは予防やセルフケアでリスクを減らすことができます。 実際に、臨床研究でも一般的な声の衛生(vocal hygiene)やウォーミングアップ、さらにはクールダウンが、声の健康を維持し、場合によっては手術を回避する効果を示すと報告されています。 本稿では、歌手にとって実際に役立つセルフケアを、研究知見と現場での実践を交えて整理していきます。 1. 声の衛生 ― 予防の第一歩 声の障害予防において最も基本的で効果的なのが声の衛生(vocal hygiene)です。これは、発声を妨げる生活習慣を避け、声帯にとって良い環境を維持するための総合的なケアを意味します。 水分補給 声帯粘膜は潤滑性が高いほど効率的に振動します。水分不足は発声閾値圧(PTP)を上昇させ、同じ声を出すにも余計なエネルギ… 続きはこちら≫
-
声門閉鎖と高音発声を理解する ― シリーズ総まとめ
声門閉鎖と高音発声を理解する ― シリーズ総まとめ 高音域で芯のある声を出すことは、多くの歌手にとって大きな課題です。 「高音になると急に息っぽくなる」「裏声のように弱々しい」「ベルティングのように力強く出せない」。 こうした悩みの裏側には、声門閉鎖のメカニズムと、それを支える筋肉のバランスが深く関わっています。 本シリーズでは、最新の研究と桜田の現場経験をもとに、声門閉鎖と高音発声の関係を解き明かしてきました。 ここでは全エピソードを振り返りながら、学びを整理してみましょう。 第1話:声門閉鎖率と音質 ― TAとCTの拮抗 声門閉鎖率(Contact Quotient)は、声の息っぽさや芯の強さを左右する大きな要素です。 TA(甲状披裂筋)とCT(輪状甲状筋)の拮抗バランスが変わることで、声門閉鎖の強弱が決まり、結果的に音質が変化します。 H1–H2やCPPといった音響指標の基礎を紹介し、科学的に「芯のある声」と「息っぽい声」の違いを整理しました。 第2話:LCA・IAと後部間隙のメカニズム 高音発声で息が混ざる大きな原因のひとつが「後部間隙… 続きはこちら≫
-
高音の地声って何で難しいの?第6話 声門閉鎖と声帯疲労
第6話:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても起こるリスク 歌手や俳優にとって、声帯の疲労(vocal fatigue)は日常的な問題です。 「高音を繰り返した後に声が出にくくなる」「リハーサルの翌日は声が重く感じる」といった経験は、多くの現場で共有されています。 一般的には「閉鎖が強すぎる=押し声が疲れの原因」と認識されがちですが、実はその逆、「閉鎖が弱い状態」でも疲労は起こります。 つまり、声門閉鎖が強すぎても弱すぎても声帯疲労を引き起こすリスクがあるということです。 本記事では、この二方向のリスクを研究と実践の両面から整理し、ボイストレーニングの現場でどう活かせるかを考えます。 声帯疲労とは何か 声帯疲労(vocal fatigue)は、Hunter & Titze(2009)によると「声の産出効率が低下し、努力感や違和感を伴う状態」と定義されます。 これは単なる「疲れた感じ」ではなく、実際に声帯組織や内喉頭筋が負荷を受け、回復に時間がかかる生理的現象です。 [caption id="attachment_2030" align="alignc… 続きはこちら≫
-
高音の地声って何で難しいの?第5話:ベルティングとジャンル差
第5話:ベルティングとジャンル差 ― 女性クラシック vs 女性CCM 「高音をどう出すか」は、ジャンルごとにまったく異なるゴールを持っています。 クラシックのソプラノと、ミュージカルやポップスのシンガー。 同じ「高音域の発声」でありながら、その音色・響きは大きく異なります。 ボイストレーニングの現場でも 「クラシックで学んだ発声をポップスに応用したら息っぽくなった」「ベルティングの練習したら単なる叫び声になった」という声は少なくありません。 ここには、ジャンル特有の声門閉鎖戦略と声道調整の違いが存在します。 そしてこの違いを理解することは、ボイストレーナーが生徒に適切な指導をする上で極めて重要です。 クラシック(女性ソプラノ)の戦略 [caption id="attachment_2081" align="aligncenter" width="300"][/caption] 女性クラシック発声の基本は輪状甲状筋(CT)主導です。 声帯を長く・薄くストレッチし、CTの働きによってF0(ピッチ/基本周波数)を上昇させます。 このときTAの関与は控えめ… 続きはこちら≫
-
高音の地声って何で難しいの?第4話:芯のある高音発声のメカニズム
第4話:CTとTAの相互作用 ― 芯のある高音発声のメカニズム 歌手にとって「高音域で芯のある声をどう出すか」は大きなテーマの一つです。 ボイストレーニングの現場では「高音になると急に息っぽくなる」「裏声のように弱々しくなってしまう」「ベルティングのような強い高音が出せない」といった悩みが頻繁に聞かれます。多くのボイストレーナーも、生徒から寄せられる最も大きなリクエストのひとつとして「高音でも地声的な存在感を保ちたい」というニーズに向き合っています。 このテーマの理解に欠かせないのが、CT(輪状甲状筋)とTA(甲状披裂筋)の相互作用です。 従来の説明では「高音=CT、低音=TA」という単純な二分法が語られることも多いですが、実際の発声はそれほど単純ではありません。 とくに高音での芯のある発声(地声的高音)は、CTだけではなくTAの「適度な関与」が鍵になります。 CTとTAの役割の基本 CT(輪状甲状筋)は声帯を前後に引き伸ばし、長く・薄く・張りの強い状態にします。これによって基本周波数(F0)が上昇し、ピッチを高める主役的な筋肉です。 CTは声帯をス… 続きはこちら≫
-
高音の地声って何で難しいの?第3話 -声門閉鎖の計測と聴こえ方
第3話:声門閉鎖の計測と耳のつながり 声門閉鎖を理解するうえで欠かせないのが「数値化」です。 歌手やボイストレーナーの耳は確かに鋭いものですが、感覚や比喩だけでは客観性に欠けます。 研究分野では、声門閉鎖の状態をアコースティック指標や音響分析、さらに生理学的計測によって把握することが一般的になってきました。 ここでは代表的な方法であるH1–H2、CPP、HNR、そしてEGG(電気声門図)を取り上げ、耳で聴く声の印象とどのように対応しているのかを整理していきます。 H1–H2(第1・第2倍音差) H1–H2は、声のスペクトルにおける第1倍音(基音)と第2倍音の強さの差を示す指標です。 H1が強く、H2との差が大きい → 息っぽい声、閉鎖が弱い声。裏声的な発声戦術ともいえます。ポップスやR&Bでは、この傾向をあえて利用して柔らかいニュアンスを作ることもあります。 H2が強く、差が小さい(またはマイナスになる) → 閉鎖が強く、芯のある声。 これは物理的に、声帯がしっかり閉じていると高次倍音が多く発生し、音の情報量が増すためです。 逆に閉鎖が甘いと… 続きはこちら≫
-
高音の地声って何で難しいの?第2話 ― 息漏れの正体
第2話:LCA/IAと後部間隙 ― 息漏れの正体 「高音は出るのに中音域が息っぽい」「声量はあるのに地声ぽく聞こえない」「ピッチは正確なのに芯がなく聞こえる」。 これはボイストレーニングの現場で頻繁に耳にする悩みです。特に女性に多い悩みのようです。 原因を探っていくと、単なるTAとCTのバランスだけでは説明がつかないケースが少なくありません。 そこで浮かび上がるのが、後部間隙(posterior glottal gap)です。 声帯の膜様部はきちんと接触しているのに、披裂部の後端が閉じきらない。 わずかな隙間から息が漏れ、それが音質に影響を与える。 この現象こそが「息っぽさ」の正体のひとつです。 解剖とメカニズム 声帯閉鎖を司るのはTAとCTの拮抗だけではありません。 LCA(外側披裂筋)とIA(横・斜披裂筋)という補助筋群が大きな役割を果たしています。 LCAは披裂軟骨の声帯突起を内側に引き寄せ、膜様部の接触を強めます。 IAは披裂軟骨同士を寄せ、後部を閉鎖します。 つまり、LCAが「突起を寄せる」、IAが「後ろの隙間を塞ぐ」ことでし… 続きはこちら≫
-
高音の地声って何で難しいの?第1話 ― TAとCTの拮抗
- 2025.09.24
- ボイストレーナー育成 ミックスボイス 喉頭の機能 歌手のための音声学
第1話:声門閉鎖と音質 ― TAとCTの拮抗 「声が薄い」「芯がない」「高音で息っぽくなる」。 ボイストレーニングの現場で最も多く聞かれる悩みの一つが、声門閉鎖の不安定さによる音質の問題です。 声門閉鎖が甘ければ息漏れが多く、科学的に言えば高次倍音のエネルギーが少ないため、声そのものの情報量が落ちてしまい、個体の存在感を持った声色が成立しづらくなります。 (ただし、ポップスの世界では、この状態すらも「個性」として受け入れられるケースもあります。) 一方で、強すぎる閉鎖は「叫び声」となり、硬さや苦しさを伴う声質につながります。 つまり声門閉鎖は「強ければ良い」「弱ければ悪い」という単純な話ではなく、適切なバランスが求められるのです。 ここで「声種」という考え方も関わってきます。 高音での声門閉鎖が得意な声 → 高音が出しやすい声種(男性:テナー、女性:ソプラノ) 中音域で声門閉鎖が得意な声 → 中音域が出しやすい声種(男性:バリトン、女性:アルト) つまり、声門閉鎖のしやすさや特性は、解剖学的な個人の声種や得意な音域に深く結びついているのです。 … 続きはこちら≫
-
ハリウッド式ボイストレにおける母音の使い方:科学的エビデンスを探る
- 2025.09.23
- ボイストレーナー育成 ミックスボイス 喉頭の機能 歌手のための音声学
はじめに:違和感から始まった調査 先日、アメリカ人の先輩ボイストレーナーが開催するワークショップに出席した際、あ母音は甲状披裂筋(TA)を活性化というワードを耳にしました。 近年、自分が学んでいる発声科学やボイストレーニングの知見を踏まえると、この一言には少し違和感がありました。 本当に母音だけで特定の筋肉が活性化するのか?という疑問から、いくつかの研究を調べてみたところ、興味深い事実がいくつも見えてきました。 ハリウッド式ボイストレーニングでは、強母音(あ母音など)を胸声強化、弱母音(い・う母音)を頭声強化に用いる手法が広く使われています。 本当に科学的にもそれは正しい方法なのでしょうか? これを科学がどこまで裏付けているのかを見ていきます。 [caption id="attachment_1743" align="aligncenter" width="170"] [/caption] 音圧レベル(SPL)とTA活動に関する研究 •Hirose & Gay (1972, JASA) 音圧レベル(SPL)を約70dBから90dBに上げると、TAの放電レベル… 続きはこちら≫
-
声の加齢変化― 男性と女性の比較
声の加齢変化(第4回)― 男性と女性の比較 加齢によるシリーズの目次はこちら 加齢と声の関係:歌手にとって避けて通れない課題を考える 男性歌手必見!男声の加齢による変化とは? 女性の声の加齢変化(第1話)― 低音化とその原因 女性の声の加齢変化(第2話)― 影響と研究から見える現実 女性の声の加齢変化(第3話)― 対策とハビリテーションの実践 声の加齢変化― 男性編 詳細解説 はじめに:男女で逆方向に進む声の加齢 加齢によって声が変わることは誰にでも起こる自然な現象ですが、その変化の方向性は男女で大きく異なります。男性は年齢を重ねると声が少しずつ高くなるのに対し、女性は逆に声が低くなるのです。 この現象は単なる個人差ではなく、解剖学・ホルモン・筋力・呼吸機能、そして文化的背景の複合的な影響によるものです。 ここでは、研究の知見を踏まえながら「なぜ男女で異なる変化が起こるのか」を整理し、歌手やボイストレーナーが現場で活かせる視点を探ります。 解剖学的な差異 男女の声帯はもともと構造や大きさが異なります。 男性の声帯は長く厚みがあり、甲状軟骨(のど仏… 続きはこちら≫