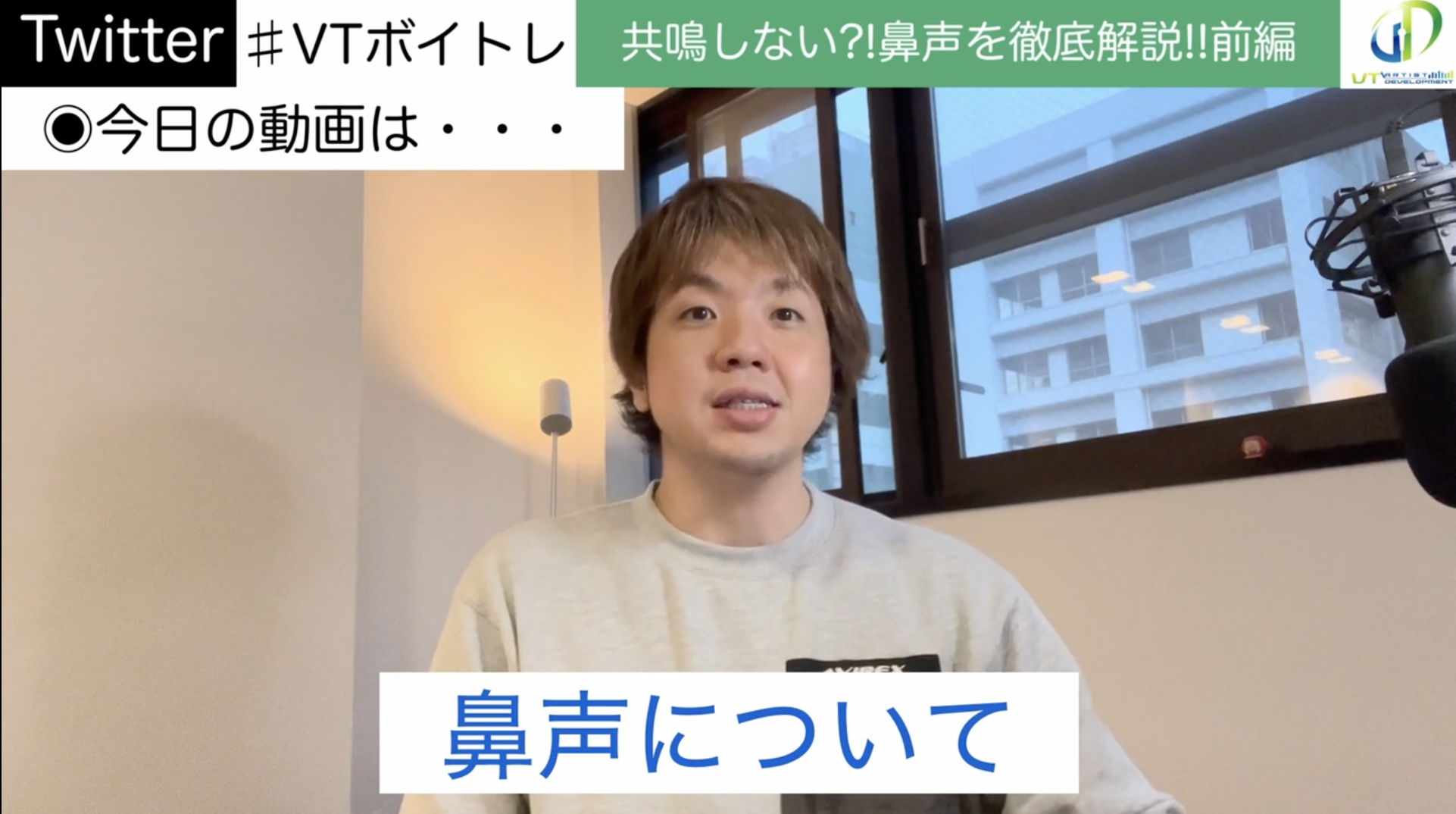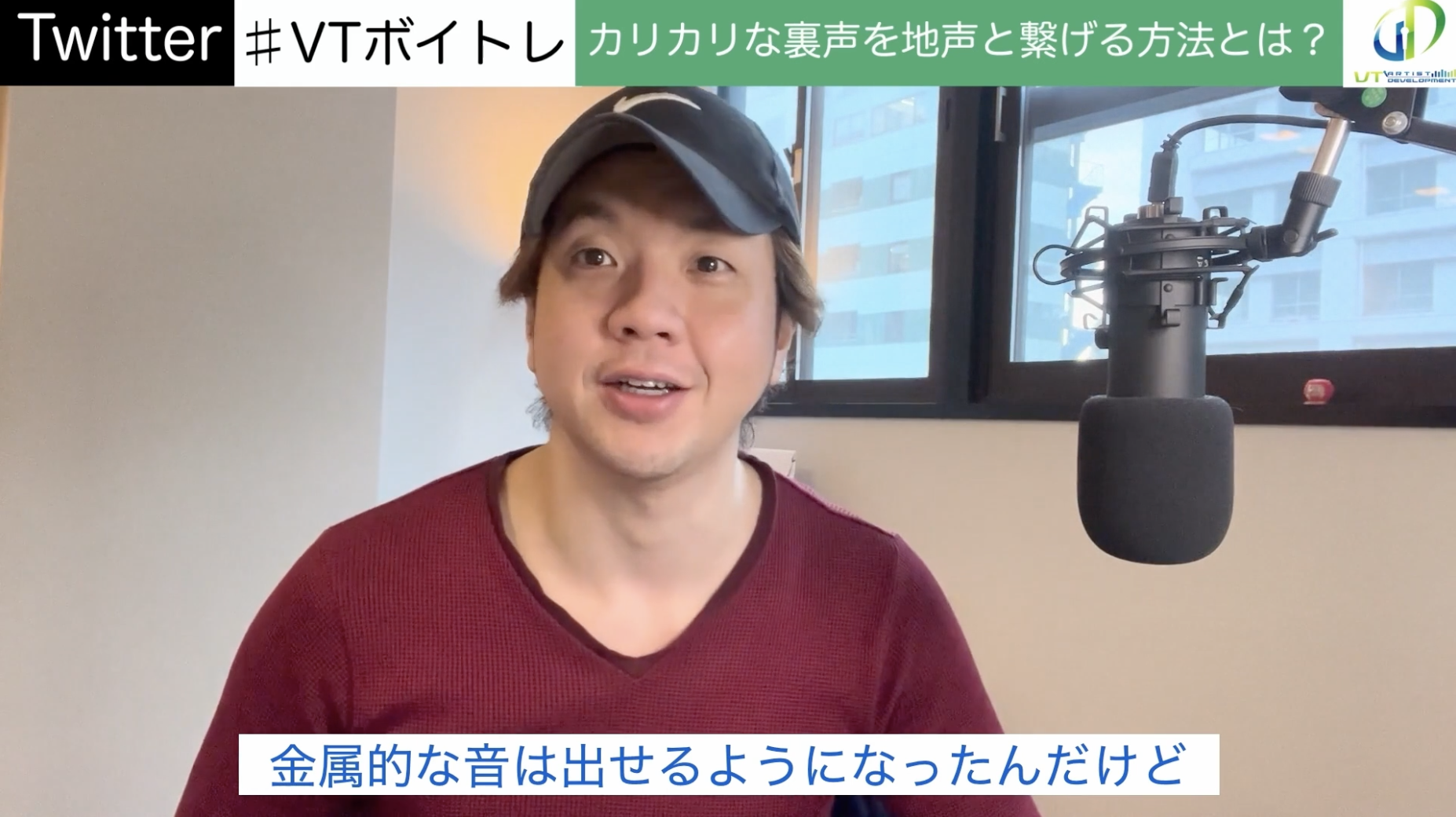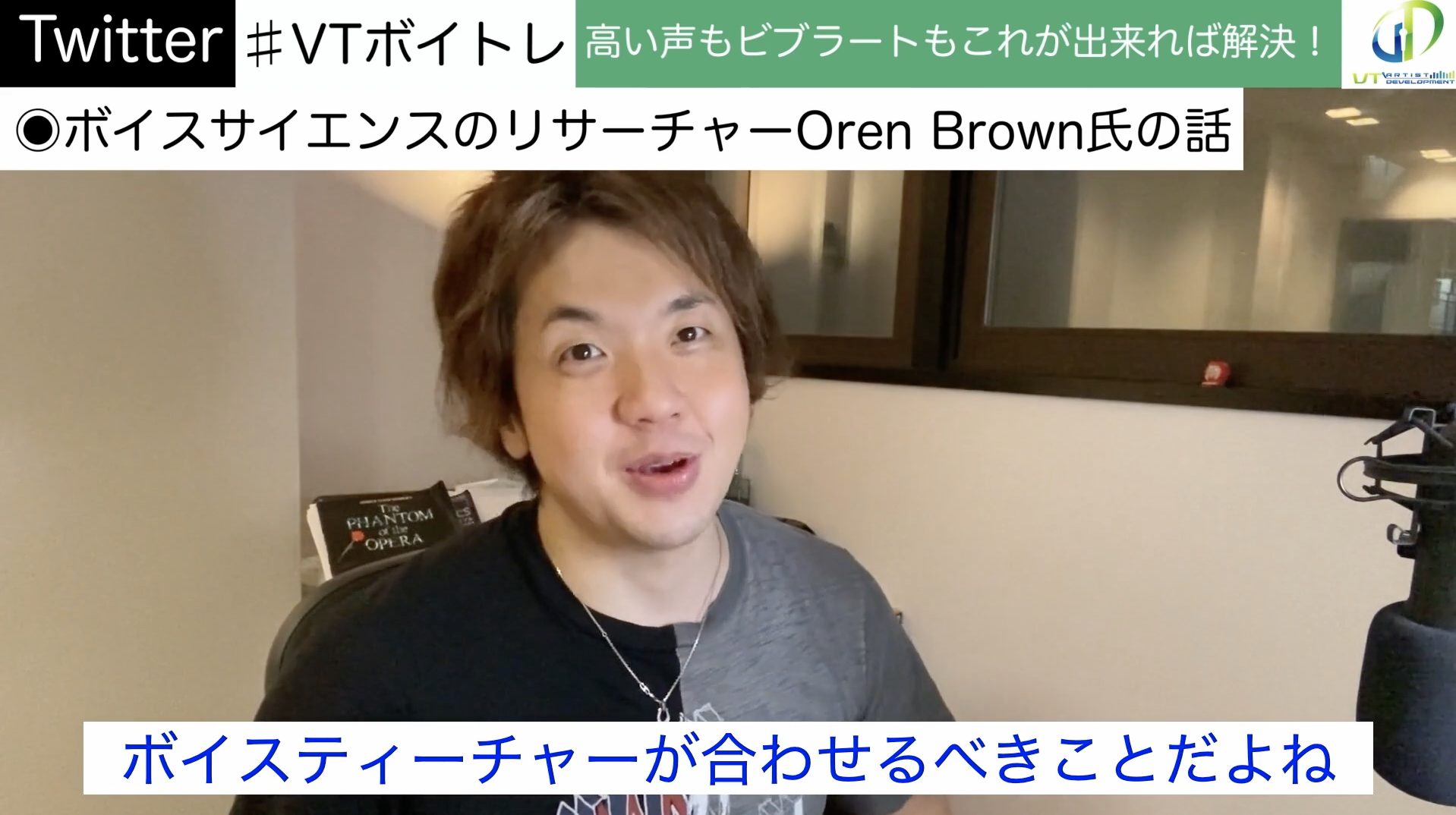-
歌手の機能性発声障害 第7話:機能性発声障害における統合的アプローチ
第7話:機能性発声障害における統合的アプローチ 歌手や声優の発声障害をサポートしていると、しばしば痛感するのは「一人の専門家だけでは十分に対応できない」という現実です。器質的な異常がないケース、検査では「異常なし」と診断されるケース、そして歌唱でのみ深刻な支障が現れるケース——これらは機能性発声障害と呼ばれ、日本でも診断名として一般的に用いられています。 しかし、この診断名だけで治療や支援の方向性が明確になるわけではありません。むしろ問題はここから始まります。歌手にとって求められる声のレベルは、日常会話を超える非常に高度なものだからです。本稿では、機能性発声障害に対して有効とされる統合的アプローチについて整理し、医師・言語聴覚士(SLP)・ボイストレーナーの役割を比較しながら考えていきます。 1. なぜ統合的アプローチが必要か 機能性発声障害の厄介さは、診断や評価の曖昧さにあります。器質的疾患(声帯結節やポリープなど)であれば診断名がつきやすく、治療方針も比較的明確です。ところが機能性発声障害は、ストロボスコピーでも決定的な異常所見が見つかりにくく、… 続きはこちら≫
-
歌手の機能性発声障害 第6話:心因性要素・歌手のイップスと発声障害
第6話:心因性要素・歌手のイップスと発声障害 「リハーサルでは普通に歌えるのに、本番で急に声が詰まってしまう」 「マイクの前に立つと、喉が固まって息もれの声しか出なくなる」 こうした声の不調を訴える歌手や声優は少なくありません。検査では異常が見つからず、日常会話では問題なく声を出せるのに、ステージや収録といった特定の環境でだけ症状が現れる。この現象は、スポーツや楽器演奏で知られる「イップス(yips)」と非常に似ています。 本稿では、イップスの定義と研究を整理し、歌手に特有の「声のイップス」について掘り下げていきます。さらに、治療法がまだ確立していない現状の中で、スポーツや音楽領域の研究から応用できるヒントを検討します。 1. イップスとは何か? イップス(yips)は、もともとゴルフのパット動作で知られる現象で、技術的には可能な動作が心理的プレッシャーや神経的要因によって阻害されるものです。手が震える、痙攣する、動作が固まるなど、特定のタスクで制御不能な運動が起こります。 Smithら(2003)の研究によれば、ゴルファー… 続きはこちら≫
-
歌手の機能性発声障害 第5話:代償発声と二次的障害
第5話:代償発声と二次的障害 代償発声(Compensatory vocalization)と言う言葉を知っていますか? 代償発声とは、発声に必要な機能が十分に働かないとき、他の筋肉や方法で無理に声を出そうとすることを指します。一見すると、声が出ていますし、コントールが上手な方であれば、かなり上手な歌唱にもなり得ます。しかし効率が悪く、声帯や周辺筋肉に過度の負担をかけ、長期的には二次的な障害につながります。 本稿では、代償発声のメカニズムと、それが引き起こす二次的障害について整理し、研究とケーススタディをもとに改善の方向性を考えていきます。 1. 代償発声とは何か? 声帯や喉頭の基本的な機能が十分に働かないとき、人は無意識に「別の方法」で声を出そうとします。これが代償発声です。 例えば、声門閉鎖が弱いとき、首や肩の筋肉に力を入れて無理に声を出そうとする。あるいは、声がかすれるのを補おうと息を強く押し出す。これらは短期的には音を出すことができますが、効率が悪く、声帯の酷使につながります。 Koufman & Isaacson(19… 続きはこちら≫
-
歌手の機能性発声障害 第4話:歌唱発声と臨床評価の乖離
第4話:歌唱発声と臨床評価の乖離 「会話は問題ないのに、歌うと声が詰まる」—— 歌手や声優にとって、こうした悩みは決して珍しくありません。 実際、病院で診察を受けた際に「異常なし」と告げられるケースも多いのですが、その一方で本人は歌唱時に深刻なパフォーマンス障害を感じています。ここに、日常会話を前提とする臨床評価と、歌唱という高度なタスクの間に存在する大きな乖離が表れています。 本稿では、このギャップがなぜ生じるのかを整理し、研究知見と臨床の限界、そしてボイストレーニングによるハビリテーションの可能性について考察します。 1. 歌唱の要求と臨床検査のギャップ 臨床現場での検査は、ストロボスコピーや内視鏡を用いて「いー」といった簡単な発声をさせ、その際の声帯の周期性や閉鎖の程度を観察するのが一般的です。これは日常会話に必要な最低限の声の機能を評価するには十分ですが、歌唱のような高度な発声タスクを反映できているとは言いがたいでしょう。 歌唱には、以下のような特徴的な要求があります。 - メロディの変化に沿った複雑な声帯運動 - … 続きはこちら≫
-
歌手の機能性発声障害 第3話:機能性発声障害(MTD)の理解と歌手への影響
第3話:機能性発声障害(MTD)の理解と歌手への影響 「声が出にくい」「高音になると急に詰まる」 歌手や声優など、声を職業にしている人の間で頻繁に耳にする悩みです。 声帯結節やポリープのように器質的な変化があれば診断は比較的容易ですが、実際には検査上は異常が見られないケースも多く存在します。 日本ではこのようなケースに「機能性発声障害」という診断名がつけられるのが一般的です。 国際的には「Muscle Tension Dysphonia(MTD, 筋緊張性発声障害)」と呼ばれます。 本稿では、機能性発声障害について定義や分類を整理しつつ、歌手や声優にとってなぜ大きな壁になるのかを考察していきます。 さらに、治療やボイストレーニングによるハビリテーションの可能性についても研究を交えて解説します。 1. 機能性発声障害(MTD)の定義と分類 機能性発声障害とは、声帯に器質的な異常がないにもかかわらず、声を出す機能に問題が生じる状態を指します。国際的にはMuscle Tension Dysphonia(MTD)がその代表であり、特に声を酷使する職業(… 続きはこちら≫
-
歌手の機能性発声障害 第2話:歌手の発声障害ってなぜ治療やリハビリが難しい?
歌手と発声障害の診断が難しい理由 「病院に行ったけれど“異常なし”と言われた」—— 歌手や声を専門的に使う人たちの間で、こうした声は少なくありません。 実際、歌手の多くは日常会話ではほとんど不自由を感じないにもかかわらず、歌唱を始めた途端に息漏れや過緊張、声の途切れといった問題が露わになります。 ところが、医師や言語聴覚士の臨床検査は「話声」を前提としていることが多いため、こうした症状は「検査上は異常なし」とされてしまうのです。 本稿では、なぜ歌手の発声障害が診断しにくいのか、その背景を整理し、研究知見と実例を交えながら解説していきます。歌手本人やボイストレーナー、そして医療関係者にとっても重要な視点となるでしょう。 [caption id="attachment_2077" align="aligncenter" width="300"] [/caption] 1. 芸術性を理解できない医療的評価の限界 発声障害の診断は、耳鼻咽喉科医や言語聴覚士がストロボスコピーや内視鏡、音響解析を用いて行います。 ところが、その評価基準はあくまで「日常… 続きはこちら≫
-
歌手の機能性発声障害 第1話:発声障害とは?歌手が知るべき基礎知識
発声障害とは?歌手が知るべき基礎知識 「声が詰まりやすい」 「高い声が出しづらい」 こうした悩みを抱えてレッスンにいらっしゃる方は少なくありません。 通常の話し声ではほとんど気にならなくても、歌い出した途端に息漏れや過緊張が現れる。 歌手にとっては声帯の内転(閉鎖)クオリティ(強すぎず弱すぎず)が非常に重要であり、極端な音域や強弱・音色操作といった高度な歌唱環境下では、わずかな乱れが即座に「発声不可能」な状態を引き起こすこともあります。 その背景に潜んでいるのが「発声障害」です。 本記事では、その基本を整理しつつ、歌手ならではの視点から理解を深めていきます。 発声障害の定義と大分類 発声障害(voice disorders)とは、声を出すための仕組みが適切に働かず、本人や周囲が「声が異常だ」と感じる状態を指します。 大きくは以下の3つに分類されます。 1. 器質性発声障害(Organic Voice Disorders) 声帯結節、ポリープ、声帯麻痺、萎縮など、解剖学的・神経学的な異常が原因。 … 続きはこちら≫
-
高音の地声って何で難しいの?第6話 声門閉鎖と声帯疲労
第6話:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても起こるリスク 歌手や俳優にとって、声帯の疲労(vocal fatigue)は日常的な問題です。 「高音を繰り返した後に声が出にくくなる」「リハーサルの翌日は声が重く感じる」といった経験は、多くの現場で共有されています。 一般的には「閉鎖が強すぎる=押し声が疲れの原因」と認識されがちですが、実はその逆、「閉鎖が弱い状態」でも疲労は起こります。 つまり、声門閉鎖が強すぎても弱すぎても声帯疲労を引き起こすリスクがあるということです。 本記事では、この二方向のリスクを研究と実践の両面から整理し、ボイストレーニングの現場でどう活かせるかを考えます。 声帯疲労とは何か 声帯疲労(vocal fatigue)は、Hunter & Titze(2009)によると「声の産出効率が低下し、努力感や違和感を伴う状態」と定義されます。 これは単なる「疲れた感じ」ではなく、実際に声帯組織や内喉頭筋が負荷を受け、回復に時間がかかる生理的現象です。 [caption id="attachment_2030" align="alignc… 続きはこちら≫
-
高音の地声って何で難しいの?第3話 -声門閉鎖の計測と聴こえ方
第3話:声門閉鎖の計測と耳のつながり 声門閉鎖を理解するうえで欠かせないのが「数値化」です。 歌手やボイストレーナーの耳は確かに鋭いものですが、感覚や比喩だけでは客観性に欠けます。 研究分野では、声門閉鎖の状態をアコースティック指標や音響分析、さらに生理学的計測によって把握することが一般的になってきました。 ここでは代表的な方法であるH1–H2、CPP、HNR、そしてEGG(電気声門図)を取り上げ、耳で聴く声の印象とどのように対応しているのかを整理していきます。 H1–H2(第1・第2倍音差) H1–H2は、声のスペクトルにおける第1倍音(基音)と第2倍音の強さの差を示す指標です。 H1が強く、H2との差が大きい → 息っぽい声、閉鎖が弱い声。裏声的な発声戦術ともいえます。ポップスやR&Bでは、この傾向をあえて利用して柔らかいニュアンスを作ることもあります。 H2が強く、差が小さい(またはマイナスになる) → 閉鎖が強く、芯のある声。 これは物理的に、声帯がしっかり閉じていると高次倍音が多く発生し、音の情報量が増すためです。 逆に閉鎖が甘いと… 続きはこちら≫
-
高音の地声って何で難しいの?第2話 ― 息漏れの正体
第2話:LCA/IAと後部間隙 ― 息漏れの正体 「高音は出るのに中音域が息っぽい」「声量はあるのに地声ぽく聞こえない」「ピッチは正確なのに芯がなく聞こえる」。 これはボイストレーニングの現場で頻繁に耳にする悩みです。特に女性に多い悩みのようです。 原因を探っていくと、単なるTAとCTのバランスだけでは説明がつかないケースが少なくありません。 そこで浮かび上がるのが、後部間隙(posterior glottal gap)です。 声帯の膜様部はきちんと接触しているのに、披裂部の後端が閉じきらない。 わずかな隙間から息が漏れ、それが音質に影響を与える。 この現象こそが「息っぽさ」の正体のひとつです。 解剖とメカニズム 声帯閉鎖を司るのはTAとCTの拮抗だけではありません。 LCA(外側披裂筋)とIA(横・斜披裂筋)という補助筋群が大きな役割を果たしています。 LCAは披裂軟骨の声帯突起を内側に引き寄せ、膜様部の接触を強めます。 IAは披裂軟骨同士を寄せ、後部を閉鎖します。 つまり、LCAが「突起を寄せる」、IAが「後ろの隙間を塞ぐ」ことでし… 続きはこちら≫