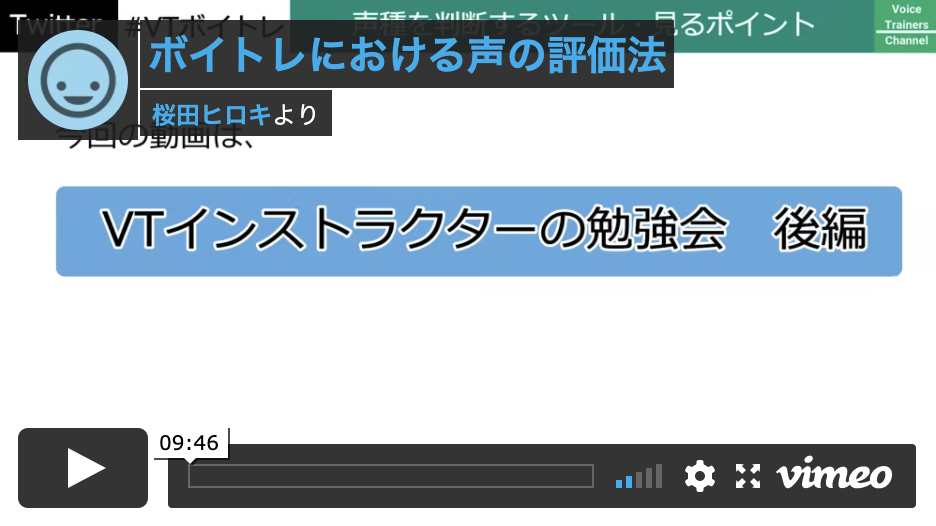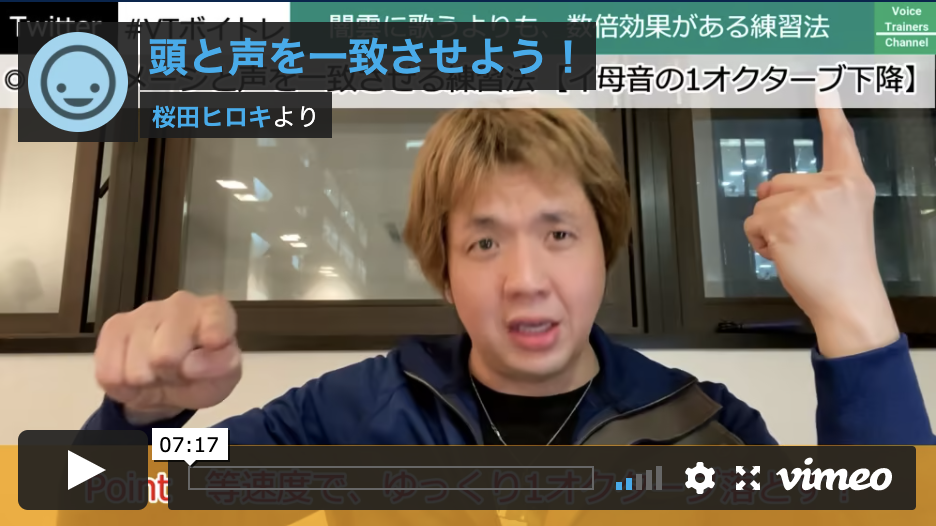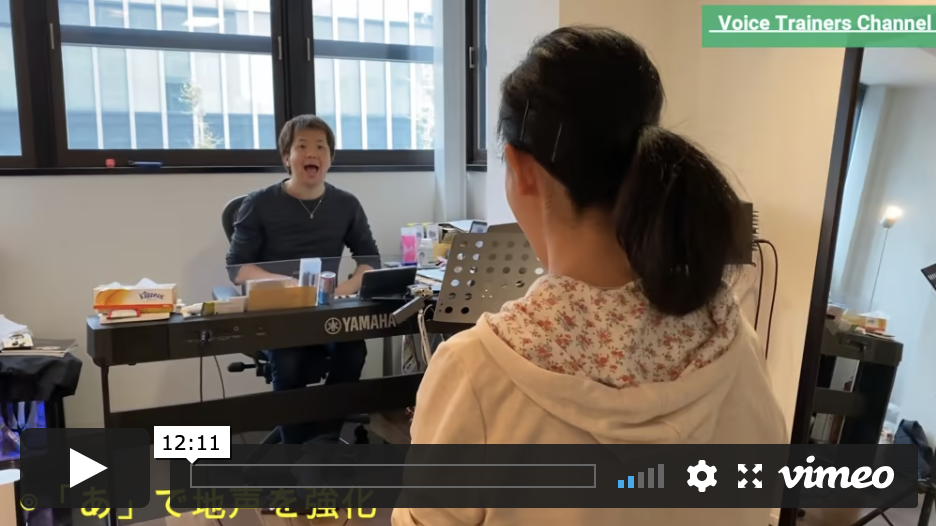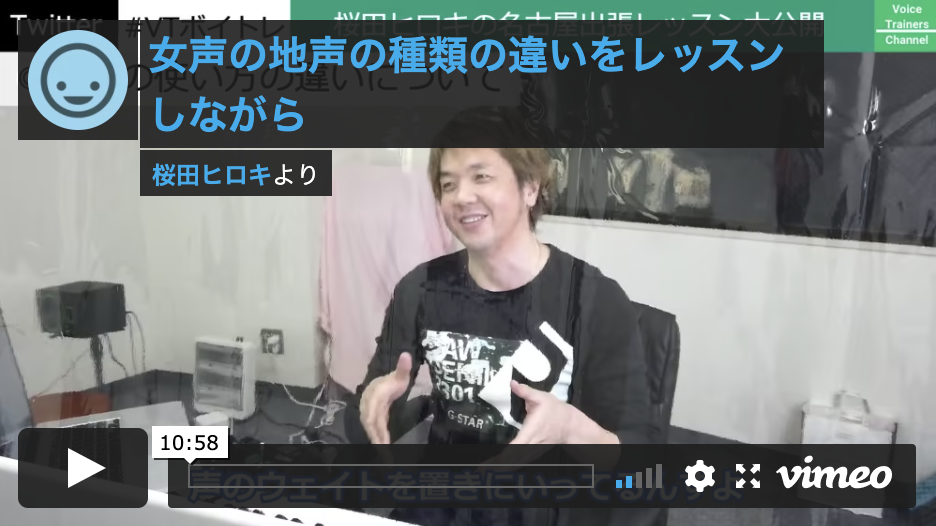ボイストレーナーの皆さんにとって、生徒の声をどう評価し、どのように改善の方向性を提示するかは非常に重要な役割です。その中で「声門閉鎖の質」をどう扱うかは、発声指導の核心のひとつでしょう。
しかし最近、女性の声における「後方ギャップ」を誤解したままトレーニングを行っている例を耳にします。特に「ライトチェスト」というラベルのもと、閉鎖が弱い=もっと閉じさせるべきだ、という短絡的な指導が増えているようです。
後方ギャップは「異常」ではない
研究では、若年女性の約85%以上において、知覚上「息っぽさ」がないにも関わらず、ストロボスコピーで後方にわずかな開き(後方ギャップ)が確認されています。つまり、女性の後方ギャップは生理的に自然な現象であり、必ずしも音質や健康に悪影響を与えるものではありません。
にもかかわらず、「息が漏れているに違いない」「もっとしっかり閉じないとダメ」という誤った前提から指導を進めると、問題は逆に深刻化します。

後方ギャップのある声門閉鎖
無理な閉鎖トレーニングの弊害
後方ギャップを「埋めよう」とするあまり、強制的に声門を強く閉じる方向へトレーニングが進められることがあります。具体的には、
- ・強すぎるグロータルアタック(強い声門閉鎖をともなうオンセット)
- ・息を押し込む「支え」の誤解
- ・長時間の声門過閉鎖を強いる発声ドリル
これらは短期的には「閉じた感」が得られても、長期的には声帯に負担をかけ、声の硬さ・疲労感・声量低下といった機能性発声障害(筋緊張性発声障害)(MTD)の典型的な症状を招く危険があります。
実際に音声外来でも、「無理な閉鎖トレーニングをしないように」と医師から注意を受けるケースが報告されています。
ケーススタディ:研究に見る「誤った閉鎖トレーニング」の影響
- 過度な声門閉鎖と機能性発声障害(筋緊張性発声障害)(MTD)
Altman et al. (2005, Journal of Voice) は、MTDの原因のひとつとして「不適切な音声トレーニング」を挙げています。特に、過度の声門閉鎖を要求する練習(強いグロータルアタックや押し付けるような支持の指導)がリスク因子となると報告されています。 - 喉頭圧迫型の発声トレーニングと障害
Koufman & Isaacson (1991) は「muscle tension dysphonia」の典型例を報告しています。そこには、無理に喉を閉じるような歌唱法や話し方の訓練が関与した症例が含まれていました。結果として、声が硬く、疲れやすく、持続がきかない「声門過閉鎖パターン」が定着していました。 - ストロボ所見に基づくケース
Verdolini & Ramig (2001, Voice Therapy) でも、トレーニング起因の障害例として「声門閉鎖を強調する誤った練習」が挙げられています。本来は軽く閉じて息の流れとバランスを取るべきところを、無理矢理に「完全閉鎖」を目標とした結果、喉頭が過緊張化。ストロボ所見では声帯が過剰に押し付けられ、振動幅が制限されていました。
意図的な「息を足す」歌唱の所見
プロフェッショナル歌手が意図的に「息っぽさ」を演出する場合、典型的な後方ギャップではなく声帯の長さに沿った帯状のギャップを形成する傾向が確認されています。
- プロの歌唱:帯状のギャップ → 声量や響きを保ちながらコントロールされたブレスィな音色
- 素人っぽい息漏れ声:後方ギャップが大きすぎる → 声門閉鎖効率が低く、声量・持続性が乏しい
この違いは、「閉じていない=悪い」ではなく、どの位置にどのようなギャップがあるかが歌声に決定的な影響を与えることを示しています。

後方ギャップを使わない「息っぽい歌声」の声門閉鎖
ギャップの種類とリスクマップ
- 後方ギャップ(posterior chink)
若年女性の約85%に見られる自然な現象。息っぽさを必ずしも伴わず、矯正不要のケースが大半。 - 前方ギャップ(anterior gap)
高齢女性に多く、声の弱さや疲労感と関連。音声不調のリスク要因になりやすい。 - 紡錘状ギャップ(spindle-shaped gap)
声帯萎縮や筋力低下に伴う。持続的なブレスィネスや加齢性嗄声と関連。 - 砂時計型ギャップ(hourglass gap)
声帯結節などの器質的病変に多い。息漏れに加え、病変部位に負荷を集中させるため障害進行と強く関連。
ボイストレーナーが気を付けるべきポイント
- 息っぽい声=必ず後方ギャップとは限らない
- 女性の後方ギャップは自然な現象である
- ギャップの「形」を無視して閉鎖量だけを増やすのは危険
- 無理に閉じさせるアプローチは逆効果になり得る
まとめ
「ライトチェスト」という判定に基づいて無理に閉鎖を強制する指導は、クライアントの声を壊すリスクを孕んでいます。女性の声に見られる後方ギャップは、研究的にもごく一般的な現象です。
重要なのは「閉じていない部分を強制的に埋める」ことではなく、声門閉鎖の形や機能を正しく理解した上で、効率的で快適な声の流れを引き出すことです。
ボーカルマッサージについてはこちら
歌手に多い「機能性発声障害(筋緊張性発声障害)(MTD)」とは?
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!
ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?