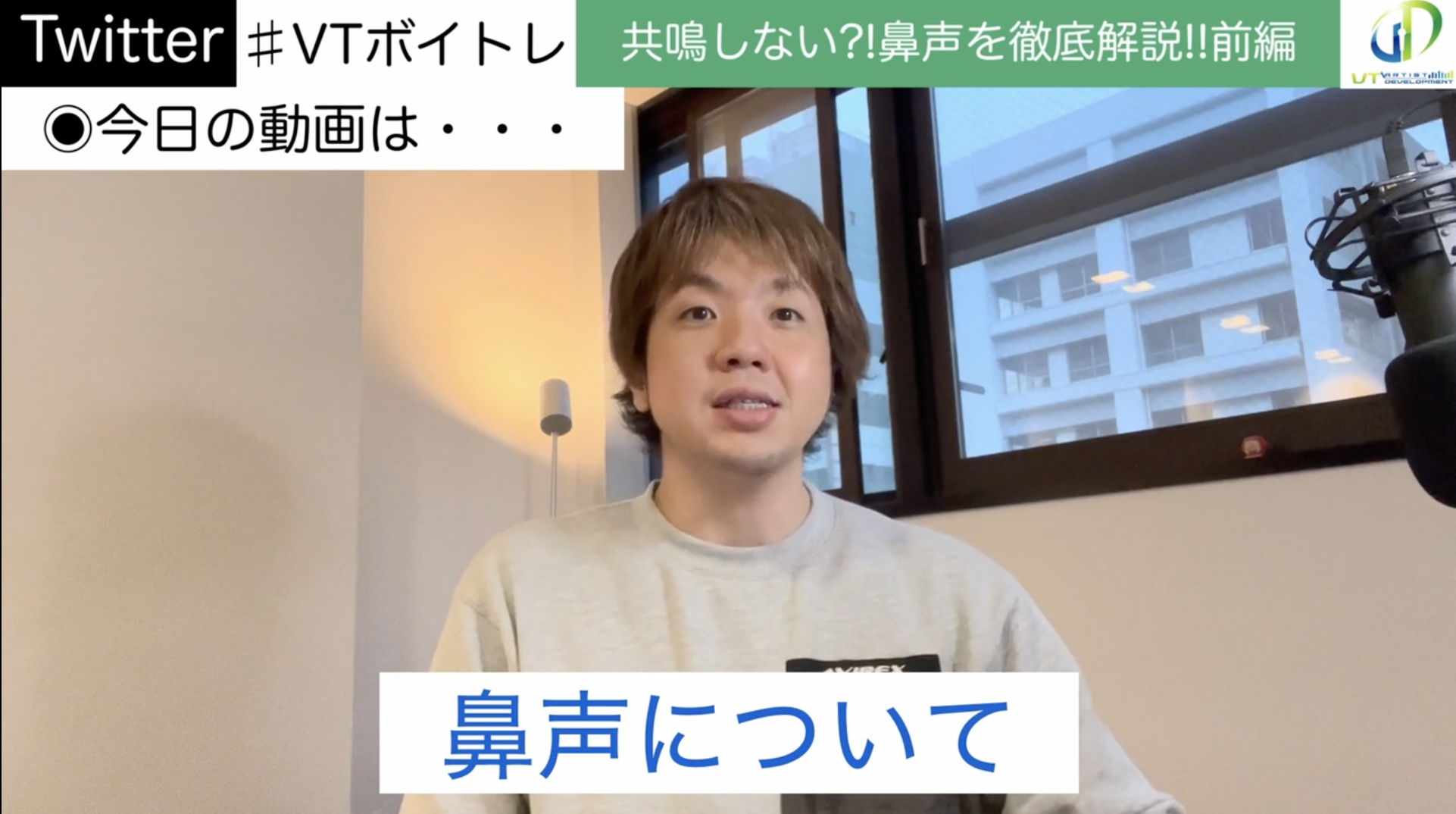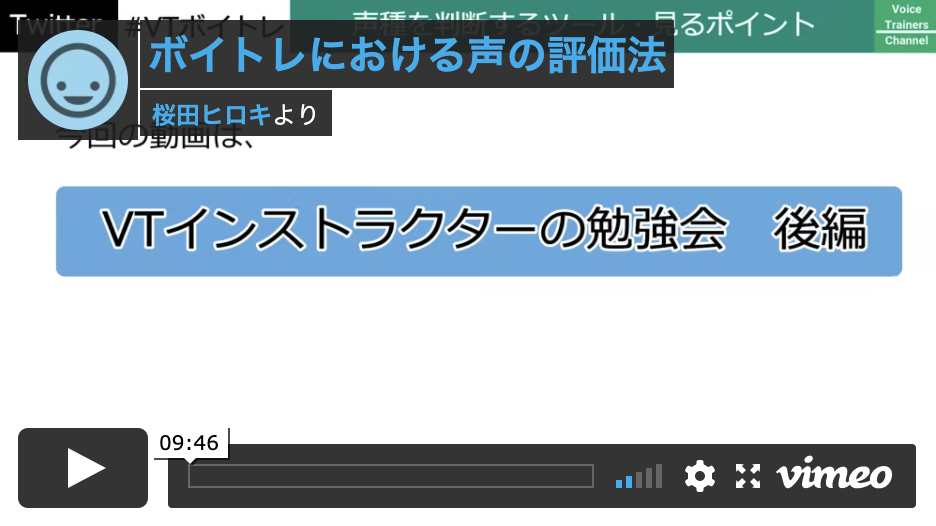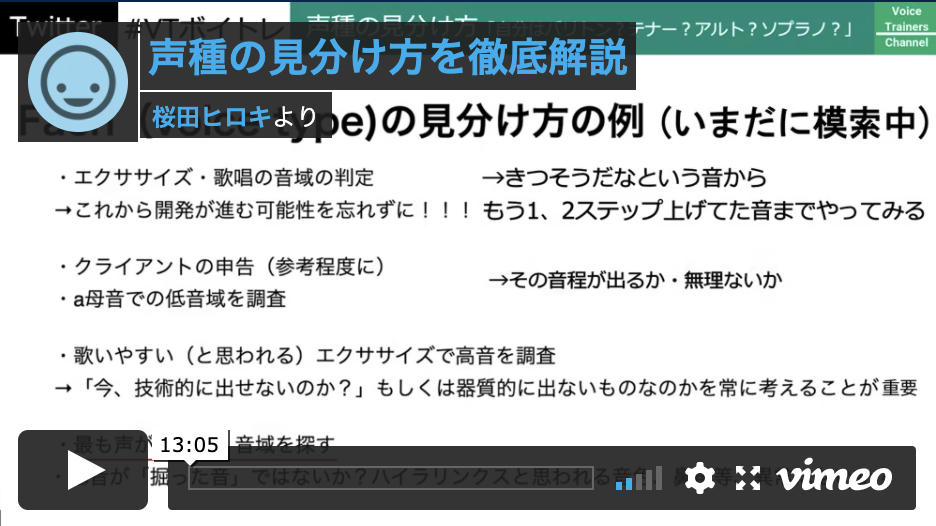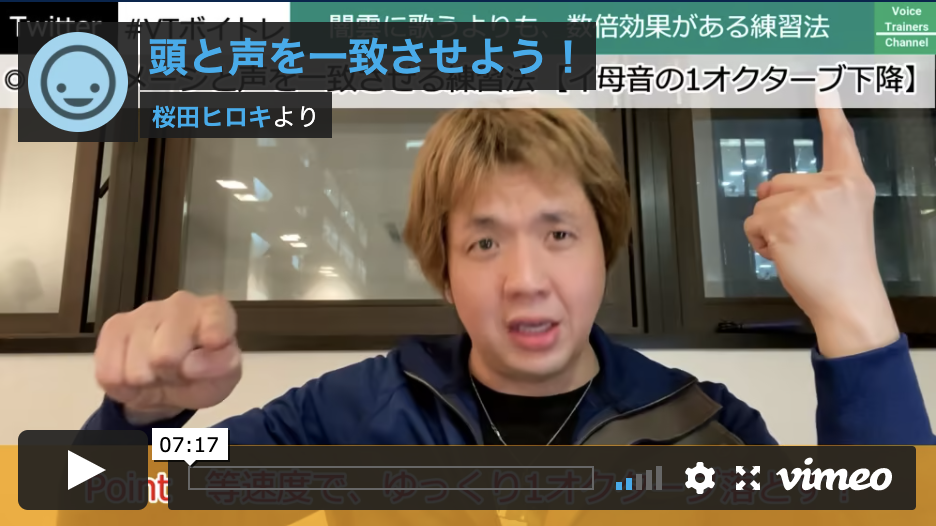第3話:機能性発声障害(MTD)の理解と歌手への影響
「声が出にくい」「高音になると急に詰まる」
歌手や声優など、声を職業にしている人の間で頻繁に耳にする悩みです。
声帯結節やポリープのように器質的な変化があれば診断は比較的容易ですが、実際には検査上は異常が見られないケースも多く存在します。
日本ではこのようなケースに「機能性発声障害」という診断名がつけられるのが一般的です。
国際的には「Muscle Tension Dysphonia(MTD, 筋緊張性発声障害)」と呼ばれます。
本稿では、機能性発声障害について定義や分類を整理しつつ、歌手や声優にとってなぜ大きな壁になるのかを考察していきます。
さらに、治療やボイストレーニングによるハビリテーションの可能性についても研究を交えて解説します。
1. 機能性発声障害(MTD)の定義と分類
機能性発声障害とは、声帯に器質的な異常がないにもかかわらず、声を出す機能に問題が生じる状態を指します。国際的にはMuscle Tension Dysphonia(MTD)がその代表であり、特に声を酷使する職業(教師・歌手・声優など)で高い発生率が報告されています。
Morrison & Rammage(1993)は、MTDを「声門周囲筋の過緊張によって発声が障害される状態」と定義しました。また、Roy et al.(2003)はMTDを「最も一般的な音声障害の一つ」とし、職業声使用者に頻発することを指摘しています。
MTDは大きく以下の2つに分けられます。
– 高緊張型:声門閉鎖が過剰で、声が硬く絞られ、すぐに発声困難を引き起こす
– 低緊張型:閉鎖が不十分で息漏れが強く、代償発声を行いやすい
この分類は治療やボイストレーニングの方向性を考えるうえで重要です。
2. 歌手・声優に特有のリスク
歌手や声優の現場では、日常会話では問題がなくても、歌唱やマイク前の発声になると症状が顕在化するケースが少なくありません。
桜田が実際に関わったケースのひとつに、声優の方がいます。日常的な会話や軽い発声では全く問題がないのに、いざマイクの前に立つと、急に声が詰まり、発声が続かなくなるのです。この場合、声帯そのものには明確な器質的異常がなく、検査上も「異常なし」とされる。しかし実際のパフォーマンス環境では致命的な問題が生じる。このような例は、機能性発声障害の診断・治療の難しさを象徴しています。
さらに、歌手の場合は次のような要素が症状を悪化させます。
– 広い音域(2〜3オクターブ以上)の使用
– 音量・音色のコントロールと瞬時の切り替え
– 長時間にわたる稽古や本番での酷使
– 心理的プレッシャーによる緊張
特に声優のケースのように「マイク前で声が詰まる」場合は、機能性発声障害に加えて心因性要素やイップス的要素も念頭に置く必要があります。この場合、単なる発声訓練だけでなく、心理的サポートを含めた包括的なアプローチが求められます。
3. 診断の難しさと臨床的限界
機能性発声障害は診断自体が難しいという特徴があります。
Roy et al.(2005)は、MTDの診断において臨床医間の一致率が低いことを報告しており、その曖昧さを問題視しています。さらに、Van Houtte et al.(2011)は「MTDの診断は除外診断であり、器質的異常がないことを確認した上で行われる」と述べています。
つまり、器質的な変化がない以上、医師の判断は「異常なし」となる可能性が高く、患者は治療やリハビリに進めないまま声の問題を抱え続けてしまうのです。
日本においても「機能性発声障害」と診断されるケースは増えていますが、その治療ゴールは「高音のつまりが軽減するように」といった曖昧なものにとどまることが多いのが現状です。
4. 治療とハビリテーションの可能性

治療の第一歩は、音声治療(Voice Therapy)やマニュアルサーキュムラリンジャルマッサージ(頸部のマッサージ)といった身体的アプローチです。Angadi et al.(2019)は、Circumlaryngeal MassageがMTDの改善に有効であると報告しています。
しかし、身体的治療だけでは不十分なことも多いです。Angadi et al.(2015)は「マッサージ単独よりもVoice Therapyと組み合わせた方が再発率が低い」と報告。さらに、Van Houtte et al.(2010)は「MTDの予後改善には、治療と発声再教育を組み合わせなければならない」と指摘しています。
個人的には現在の言語聴覚士の多くが喉頭のマッサージを行い、リラクゼーションによる一時的な緊張の緩和を重要な手段としているように感じます。
しかし、機能性発声障害の原因が何か間違ったエラーパターンを学習してしまった事により起こっているのであれば、正しい発声法を行い身体に再学習させる事が大切と考えます。
ここで重要になるのがボイストレーニングによるハビリテーションです。
歌手や声優は、症状の背景に誤った発声パターンの学習があることが多く、身体的治療後に誤用発声を修正しなければ、再発のリスクが非常に高いのです。
ボイストレーニングでは、以下のようなプロセスが必要となります。
– 発声運動の誤学習をリセットする
– 適切な呼吸・声門閉鎖のパターンを再学習する
– 音域やダイナミクスの中で安定した発声を確立する
– マイク前・舞台など実環境に即した練習を積む
つまり、機能性発声障害の改善には、医療+音声治療+ボイストレーニングという三位一体のアプローチが必要なのです。
5. 成果と限界
身体的治療によって即時的に声が出やすくなる例は多く報告されています。しかし、その後にボイストレーニングを通じて発声パターンを修正しなければ、症状は再発しやすいのが現実です。
例えば、歌手が代償発声を繰り返している場合、マッサージで一時的に緊張をほぐしても、翌日の稽古や本番でまた同じ使い方をしてしまえば再発します。これが、機能性発声障害の長期的な難しさです。
さらに、声優のケースのように心因性・イップス的要素が絡むと、従来の治療法やトレーニングだけでは十分ではないこともあります。この場合は、心理的介入やメンタルトレーニングを含めた多面的なアプローチが必要になるでしょう。
まとめ
– 日本では「機能性発声障害」、国際的には「MTD」と呼ばれる
– 歌手や声優に多く、診断が曖昧で治療ゴールも不明確になりやすい
– 高緊張型と低緊張型があり、それぞれでアプローチが異なる
– 身体的治療だけでは不十分で、ボイストレーニングによる発声再学習が不可欠
– 「マイク前で声が詰まる」声優のように、心因性・イップス的要素も考慮する必要がある
– 医師・言語聴覚士・ボイストレーナーのチームアプローチが、回復のための鍵
機能性発声障害は、単なるリハビリでは解決できない領域を含んでいます。歌手や声優にとって求められるのは、失った機能を取り戻すリハビリテーションに加えて、新しい発声技能を獲得するハビリテーションです。その両輪がそろって初めて、再発を防ぎ、持続的な声の健康を築くことができるのです。
歌手に多い「機能性発声障害(筋緊張性発声障害)」とは?
ボーカルマッサージについてはこちら
サーカム・ラリンジャル― 声を不自由解放するための科学と実践
変声期を迎えた少年歌手の発声障害の例
ツアー中に発声障害に罹患したロック歌手のケース(第1話)
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話