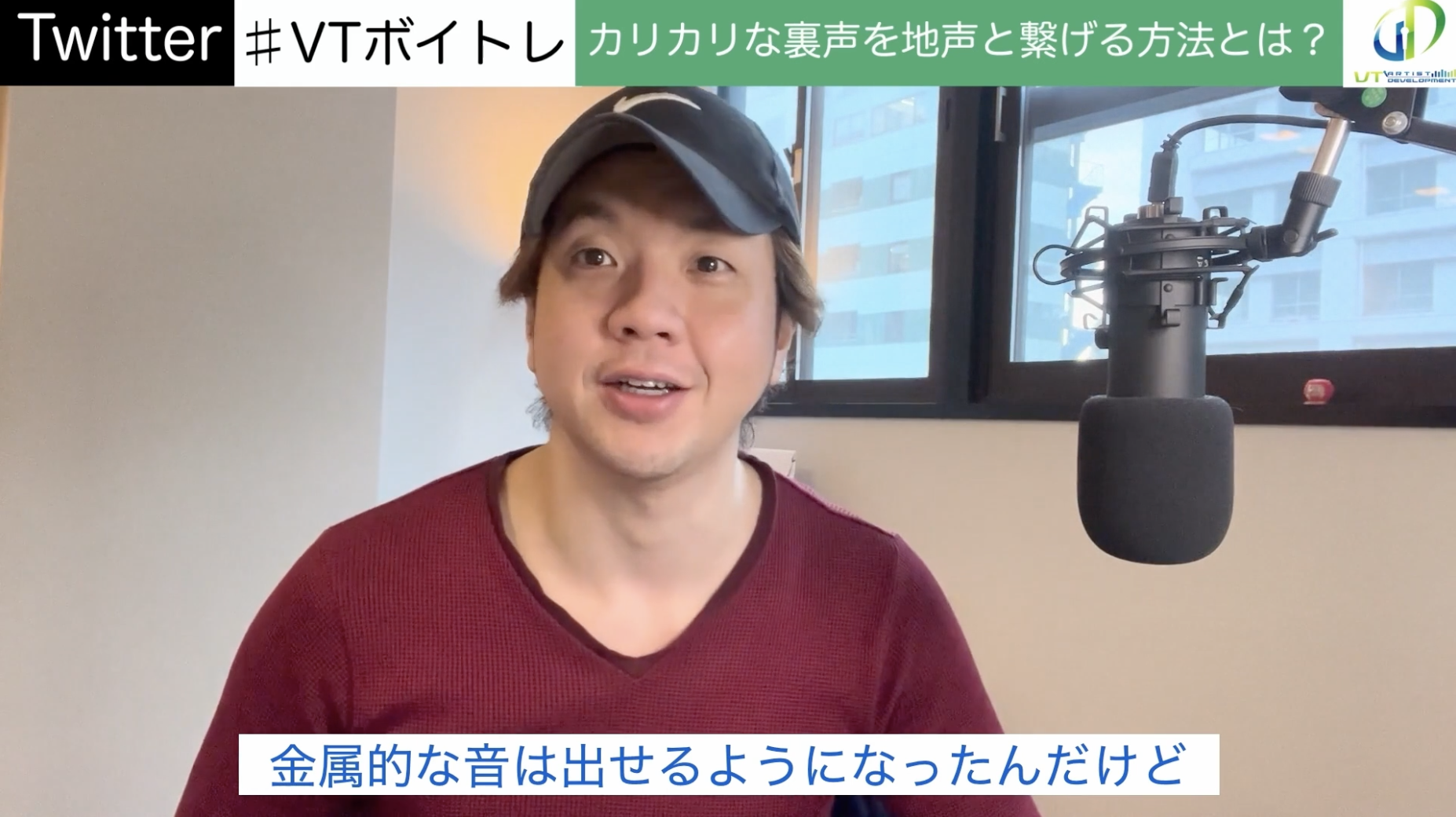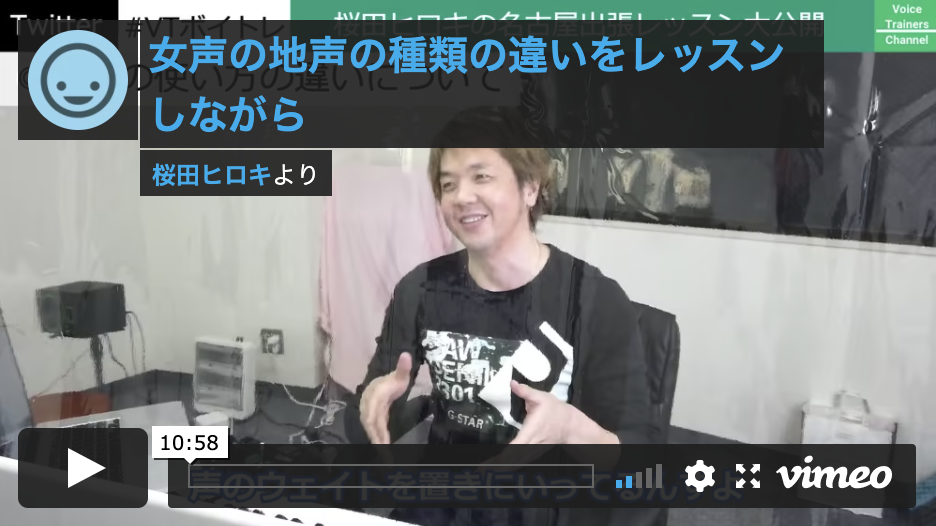声の加齢変化(第5回)― 男性編 詳細解説
はじめに:男性の声に何が起きるのか
加齢によって声が変化することは避けられません。
女性では低音化が顕著に現れますが、男性はやや異なる方向性を示します。
一般に「声が高くなる」と言われますが、それ以上に現場で強く訴えられるのは声量の低下・掠れ・持久力の低下です。
さらに多くの男性歌手からは「高音が出にくくなった」という声も聞かれます。
女性の場合はホルモン変化によって声の高さそのものが下がるのに対し、男性では声のパワーと声門閉鎖の安定性が失われることが中心的な課題になります。
本稿では、研究と臨床の両面から男性特有の加齢声の特徴を整理し、トレーニングやハビリテーションの具体策を探ります。

男性の加齢声の特徴
声量の低下
加齢により声帯の内転力が弱まり、息漏れが増えることで声が細く、届きにくい声になります。これが「昔のような力強さが出ない」という感覚につながります。
掠れや粗さ
声帯筋の萎縮によって声帯が薄くなり、振動が不規則になります。いわゆる「掠れ声」「ガラガラ声」が生じやすく、これが老化の象徴として最も分かりやすい変化です。
高音が出にくくなる
女性の高音喪失とは異なる理由で、男性も「高音が出ない」と訴えることがあります。原因のひとつは声門閉鎖の不全による代償運動です。息漏れを補うために喉頭を押し上げたり、過剰に力んだりする癖がつき、高音が出にくくなるのです。研究で直接的に裏付けられているものは少ないものの、Sundberg(2019)が指摘する声帯伸展の可動性低下や、Honjo & Isshiki(1980)の声帯筋萎縮の知見と一致します。桜田の現場でも頻繁に観察される現象です。
持久力の低下
「長いフレーズで息が続かない」という訴えは男女共通ですが、男性の場合は声門閉鎖不全による息漏れが大きく影響します。結果として発声持続時間が短くなり、歌唱の安定性が損なわれます。
解剖学的・生理的背景
声帯筋の萎縮
甲状披裂筋の萎縮は男性に顕著で、声門閉鎖が弱くなる(Honjo & Isshiki, 1980)。
粘膜・組織変化
Abitbol ら(1999)は高齢男性の声帯筋密度の低下を報告。粘膜の弾力性も低下し、規則的な振動が難しくなる。
軟骨の骨化
甲状軟骨や輪状軟骨が硬化することで声帯伸展が制限され、特に高音発声が難しくなる(Sundberg, 2019)。
呼吸機能の低下
肺活量と呼吸筋の衰えは声の持久力に直結。Hoit & Hixon(1987)は発声持続時間の短縮を、Stathopoulos ら(2010)は呼気流量の増加と安定性低下を報告。
主な訴えとその背景

Ill young man with red nose, scarf and cap sneezing into handkerchief
・「声量が落ちた」=声帯筋の萎縮と声門閉鎖不全
・「声が掠れる」=声帯粘膜の硬化と振動不規則化
・「息が長く続かない」=呼吸機能低下+息漏れ
・「昔のような力強さが出ない」=声門内転力の不足
・「高音が出にくくなった」=声門閉鎖不全による代償運動、共鳴位置の乱れ、喉頭過緊張
桜田の現場でも、男性歌手の相談はこれらが中心です。特に「高音が出ない」という悩みは、女性とは異なるメカニズムによって起きており、代償運動の改善で回復する例も少なくありません。
トレーニングと対策
声門閉鎖の補強
SOVT エクササイズ(ストロー発声、リップトリル)で効率的な閉鎖を促す。レゾナント発声で前方共鳴を利用し、声帯への過度な負担を減らす。持続母音練習で安定した声門閉鎖を体得する。
呼吸筋と全身の強化
有酸素運動で呼吸筋の持久力を維持。筋力トレーニングで胸郭と体幹の支えを改善。特に筋トレはテストステロンの低下を抑える効果が期待され、間接的に声帯筋や全身の活力を維持する重要な手段となる。Brown ら(2015)は高齢者の筋力維持が声のパフォーマンス改善につながると報告。
高音再建のための工夫
声区移行を徹底し、チェストからミックス、ミックスからヘッドへの連携を滑らかにする。特に男性はファルセット・レジスターを持っていないことが多いため、これが間接的に地声高音域の出しにくさに影響している可能性が高い。まずはファルセットの開発から入ることもある。
軟口蓋や咽頭腔の柔軟性を高め、共鳴位置を調整する。加齢に伴う筋力不足により軟口蓋が下がってくることがあり、共鳴に影響を与える。柔軟性を回復させるトレーニングは声の明瞭さを取り戻す助けとなる。
代償的な押し上げ癖をリセットするためにハミングや弱母音練習を取り入れることで、喉頭過緊張を解き、高音発声の効率を改善する。
心理的ケアと再解釈
「昔のように力強い声が出ない」と感じることは歌手にとって深刻な心理的負担となる。しかし、声の変化を衰えではなく軽さ・繊細さ・新しいニュアンスの獲得と捉えることで、キャリアの延長や新しい表現につながる。
現場での実感
桜田のレッスンでも、男性歌手は「掠れ」「声量不足」「高音困難」「持久力低下」を訴えるケースが多い。
しかし、代償運動を解消し、効率的な発声を身につけることで高音や力強さが戻る例は数多く存在する。
例えば、長年ロックを歌ってきた歌手が、加齢による高音困難を訴えていたが、SOVT と声区移行練習を徹底することで以前より軽やかに高音を出せるようになったケースがある。
これは「声を元に戻す」のではなく「新しい使い方を学ぶ」ことで可能になった成果である。
まとめ
男性の加齢声は「声量低下」「掠れ」「持久力の低下」といったパワーの減少に加え、「高音困難」という課題を抱える。
背景には声帯筋萎縮、テストステロン低下、呼吸機能低下、そして代償運動の癖がある。
しかし、研究が示す生理的変化と現場での経験を統合すれば、トレーニングやフィットネスによって改善・適応することは可能である。特に筋力トレーニングによるテストステロン維持は、男性歌手にとって声の活力を保つうえで極めて重要である。
声を「衰退」ではなく進化と捉え、効率的な発声、全身の健康管理、心理的ケアを組み合わせることが、男性歌手が生涯にわたって歌い続けるための道筋となると思います。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話