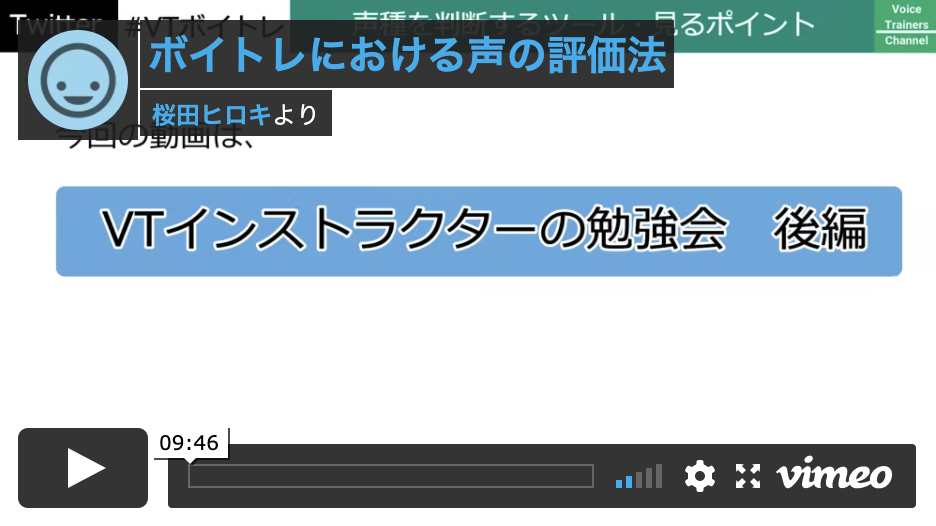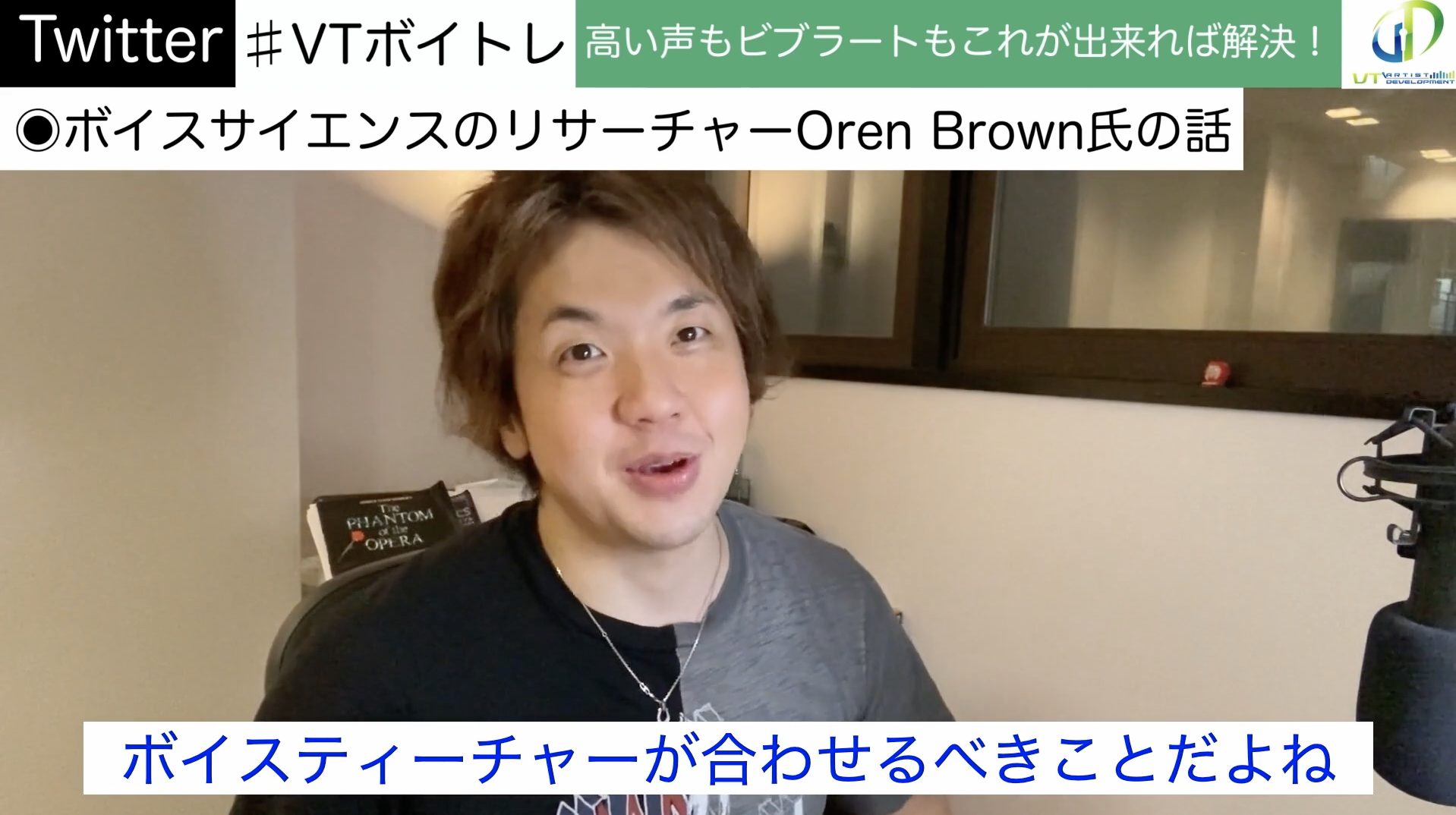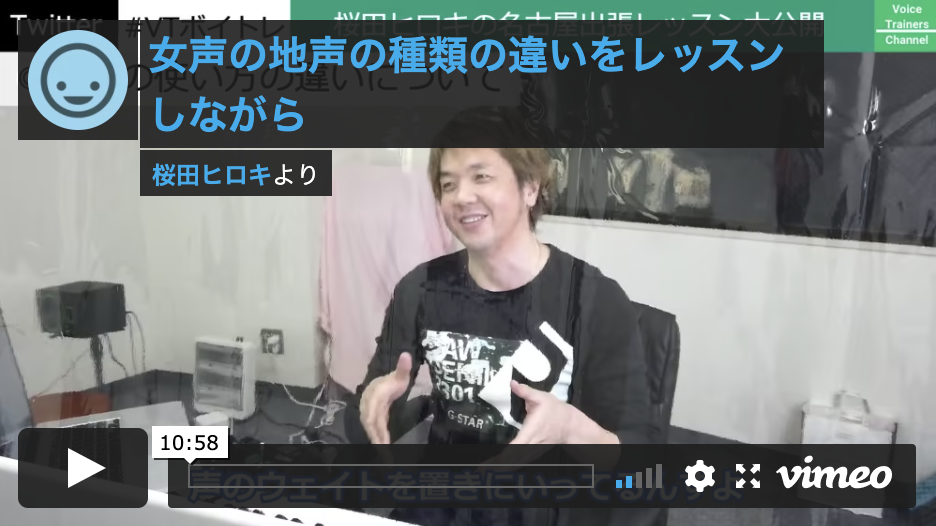歌手と発声障害の診断が難しい理由
「病院に行ったけれど“異常なし”と言われた」——
歌手や声を専門的に使う人たちの間で、こうした声は少なくありません。
実際、歌手の多くは日常会話ではほとんど不自由を感じないにもかかわらず、歌唱を始めた途端に息漏れや過緊張、声の途切れといった問題が露わになります。
ところが、医師や言語聴覚士の臨床検査は「話声」を前提としていることが多いため、こうした症状は「検査上は異常なし」とされてしまうのです。
本稿では、なぜ歌手の発声障害が診断しにくいのか、その背景を整理し、研究知見と実例を交えながら解説していきます。歌手本人やボイストレーナー、そして医療関係者にとっても重要な視点となるでしょう。

1. 芸術性を理解できない医療的評価の限界
発声障害の診断は、耳鼻咽喉科医や言語聴覚士がストロボスコピーや内視鏡、音響解析を用いて行います。
ところが、その評価基準はあくまで「日常会話に必要な発声」が前提です。
例えば、医師は診察の際に「地声でいー」「裏声でいー」と数音程度を発声させるのが一般的です。
しかし、歌唱の現場ではメロディのパターン/母音と子音の組み合わせ/SPLのダイナミクスレンジといった要素が重なります。
こうしたタスクの複雑さは、臨床検査の発声課題ではほとんど再現できません。
実際、桜田の経験でも、こうした医療と歌唱のギャップを痛感したことがあります。
ある女性クライアントが「G4とC5で地声、D4で裏声になるとザラつきが出る」と言う異常があったため、桜田はボイスクリニックの代表医師に「その音域でストロボチェックをお願いします」と依頼しました。
ところが、その医師は「そんなことを言う患者はいない」と一蹴。
結果的に診察は「地声でいー、裏声でいー」という一般的な課題にとどまり、歌唱時にのみ顕著に現れる問題は検出されませんでした。
研究でも同様の構造的問題が示唆されています。
「Frameworks, Terminology and Definitions for Voice Disorders(2022, Scoping Review, ScienceDirect)」では、発声障害の分類・定義・評価基準に大きな揺らぎがあり、歌唱を前提とした評価体系は未整備と報告。
歌唱は芸術表現×高度な身体運動であるにもかかわらず、医療側の評価は「生活に支障があるか否か」に重心が置かれ、ボイストレーニングの現場で致命的となる「高音で詰まる/微弱な声で表現できない」といった問題は疾患として認識されにくいのです。
ここにボイストレーナーの役割が生まれます。
2. 会話と歌唱の要求差 ― リハビリテーションとハビリテーション
日常会話での発声と、舞台やスタジオでの歌唱発声は、要求水準がまったく異なります。
会話においては「必要十分な音量で声が通る」「会話が成り立つ」ことが基準。しかし歌唱では、
・2オクターブ以上の音域を自由に使い分ける
・強音から弱音までの広いダイナミクスをコントロールする
・声色を自在に変え、音楽的表現に適応する
といった要求が課されます。会話では問題がなくても、歌唱では致命的な不具合が表面化するのは当然です。
「StatPearls(2022)」によれば、機能性発声障害(Functional Voice Disorders, FVD)は診断基準の統一がなく、会話では検出できないケースが多いとされます。つまり「機能性発声障害 歌手」という視点で見なければ、多くの症例が取りこぼされるのです。
ここで重要なのがリハビリテーションとハビリテーションの違い。
リハビリは「失われた機能を回復」する営み。一方、歌唱サポートは日常生活には不要な高次発声技能を新たに獲得するプロセスで、ハビリテーションに近い。
これを補えるのがボイストレーナーであり、ボイストレーニングはしばしばハビリテーション的に機能します。
ただ現状、日本国内でボイス・ハビリテーションと言う観点でボイストレーニングを行えるボイストレーナーの方がむしろ限られており、非常に難しい壁が存在します。
桜田ヒロキ主催のボイストレーナー育成講座VT-RVでは、ハビリテーションに対応出来るよう言語聴覚士や音声学者を招いての講義を行っています。
3. 診断名が必要という制度的ハードル

医師や言語聴覚士が介入するには「診断名」が必要。診断名がなければ保険制度上、治療やリハビリは提供できません。
ところが歌手に多いのは、検査上は「異常なし」、もしくは検査上、異常は見受けられないが、リハビリ計画を立てて医師や言語聴覚士がリハビリを行うために「機能性発声障害」と診断を行うケースです。
この場合、リハビリのゴール設定が曖昧になりがちです。例えば「高音のつまりがなくなるように」や「以前出していたクオリティ(患者の知覚をもとに)」といった表現にとどまる。
なぜなら、歌唱で必要とされる具体的な発声項目は、現行の臨床枠組みでは診断しづらいから。
ゴールが曖昧なら、治療やリハビリも曖昧になりがちで、桜田が継続的に観察しているクライアントという限られた範囲でも、この方法が効率的に機能しているとは感じにくいのが実情です。
一方で、「ASHA(2009, Team Management of Voice Disorders in Singers)」のケースでは、音楽専攻の大学生がMTDにより歌唱で顕著な不調を訴えていました。
診断名がつかなければ医療もリハビリも介入できませんでしたが、最終的に医師・言語聴覚士・ボーカルコーチがチームを組み、6週間で歌唱機能を回復。この例は診断名=出発点である一方、それだけでは歌唱の問題を救えないことも示しています。
4. 検査法・評価法の限界
臨床では喉頭ストロボスコピー/音響解析が広く用いられ、声帯振動の周期性や閉鎖のタイミング観察に有効です。しかし、歌唱時の複雑なパターンを完全には反映できないのが現実。
「Frameworks, Terminology and Definitions for Voice Disorders(2022, ScienceDirect)」でも、分類・評価基準の揺らぎが指摘されています。研究者ごとに方法が異なり、症例間で比較可能なデータが得にくい。
さらに、臨床では患者の主観的訴えと検査結果が食い違うことも多い。歌手が「高音で詰まる」と訴えても、ストロボ所見は「異常なし」となる場合がある。この主観—客観ギャップこそ、医師と歌手の間に言語ギャップを生む要因です。
5. 新しい研究と補助的診断の可能性
限界を補うべく、新技術・研究が動き始めています。
・「Differentiability of voice disorders through explainable AI(Nature, 2025)」
AIで異常声を分類し、どの音響特徴量が障害に関与するかを説明可能に提示。歌唱時の異常を客観可視化する補助診断ツールとなる可能性。
・「Uncovering Voice Misuse Using Symbolic Mismatch(Arxiv, 2016)」
喉頭付近の加速度センサーで長時間の発声データを収集し、無意識な声の誤用を検出。舞台稽古や本番での誤用を可視化する手段として期待。
いずれも臨床実装には距離があるものの、「機能性発声障害 歌手」の診断・予防の補助となり得ます。
6. まとめ ― 歌手が主体となる診断プロセス
総括すると、歌手の発声障害が診断しにくい理由は、
・医療側が日常会話基準で評価し、芸術性を十分に扱えない
・歌唱の要求水準が会話を大きく上回り、臨床評価の外にある
・診断名がなければ介入が始まらず、制度が壁になる
・検査法・評価法の揺らぎが大きく、主観—客観ギャップが埋まらない
・研究は話声中心で、歌唱に特化した知見が不足している
この不確実性を前提に、歌手自身が診断プロセスの主体となることが不可欠です。
録音/練習日誌で自らの声を記録し、専門家に提示。医師・言語聴覚士・ボイストレーナーを組み合わせてチームとして活用する。
その中でシンガー自身がリーダーとなり、自分の声を回復に導く。
「異常なし」と言われても、その言葉を鵜呑みにせず、違和感を具体的な言葉にして伝える。
セカンドオピニオン、サードオピニオンを色々な医師に聴きに行く。
これこそが、ボイストレーニングを継続しながらキャリアを守るための第一歩です。
歌手に多い「機能性発声障害(筋緊張性発声障害)」とは?
ボーカルマッサージについてはこちら
サーカム・ラリンジャル― 声を不自由解放するための科学と実践
変声期を迎えた少年歌手の発声障害の例
ツアー中に発声障害に罹患したロック歌手のケース(第1話)
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話