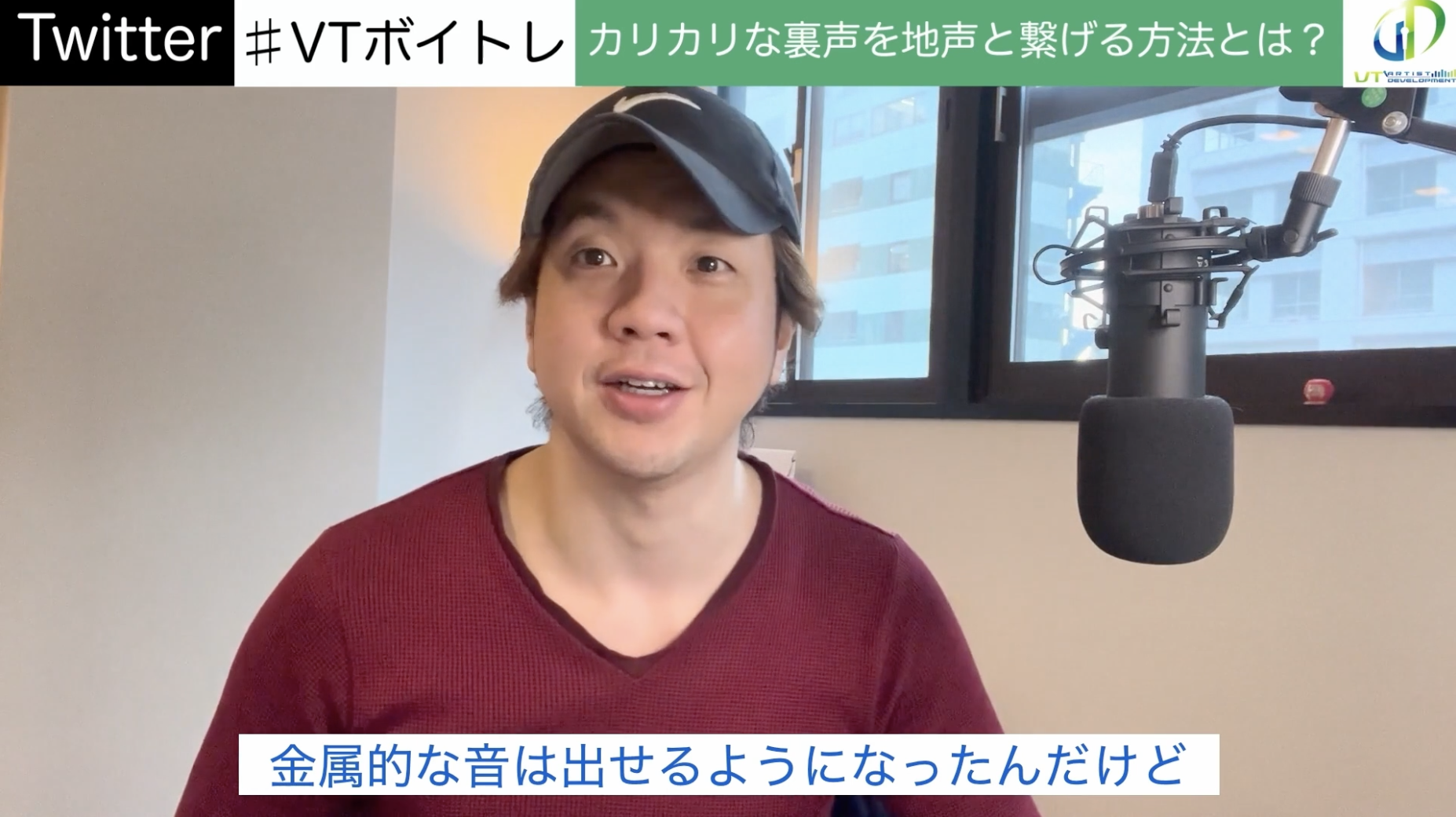第3章:ビブラートの消失と再獲得 ― 声の健康とリハビリの視点から
ビブラートは、声が健康に働いているかどうかを示す「指標」のひとつといえます。
第1章「ビブラートと言う物理現象」ではそのメカニズムを、第2章「ビブラートのトレーニング方法」では安定した揺れを育てるトレーニング法を取り上げました。
そしてこの第3章では、ビブラートが「失われる」とき、声の内部で何が起こっているのかを整理し、その再獲得の道筋を探ります。
多くの歌手が「ビブラートがかからなくなった」「以前のような自然な揺れが戻らない」と感じるとき、そこには単純な技術的要因だけでなく、喉頭の筋緊張や粘膜の変化、さらには神経系の働きが関係していることがあります。
このような変化は、短期的な声の酷使や炎症から、慢性的な過緊張、加齢にともなう筋萎縮まで、非常に幅広い要因によって起こります。
ビブラートが生まれる仕組みを「反射」や「自動調整」として捉えると、その消失は「声の自律的な揺れ」が止まった状態だと考えることができます。
言い換えると、声帯が正しいバランスで動くためのフィードバック・ループが途切れてしまっているのです。
そのため、単に「揺らそう」としても、意図的な筋活動では自然なビブラートは再現されません。

ビブラートが失われる主な原因
・声帯粘膜の物理的変化
炎症や浮腫、脱水などによって声帯の粘弾性が変化し、周期的な振動が阻害されます。
この状態では、F0(ピッチ/基本周波数)の安定した揺れが生まれにくくなり、声が“硬い”印象になります。
・筋緊張のアンバランス
長時間の発声やストレス、誤ったフォームにより喉頭筋が過剰に固定されると、反射的な揺れが起こらなくなります。
特にTA優位の緊張が続くと、声が直線的に感じられます。
・神経制御の乱れ
中枢(脳幹)と末梢(反回神経)の伝達が遅延・過敏化すると、声帯振動の周期が不規則または途絶します。
パーキンソン病や神経性トレマー(震え)では、この「周期の異常」が特徴的です。
・加齢による筋萎縮・伝達遅延
声帯筋やCT筋の線維が細くなり、振動の粘弾性が低下します。
結果として、ビブラートのRateは遅くなり、Depthも浅くなる傾向があります。
この章では、これらの変化を3つの観点から整理します。
1. 声帯粘膜の物理的変化
2. 神経・筋緊張性の要因
3. 加齢による変化
その上で、再獲得に向けてどのように声を「再教育」していくか、臨床とトレーニングの橋渡しとなる考え方を紹介します。
1. 声帯粘膜の物理的変化とビブラートの消失
声帯の振動は、上皮とその下の粘膜層が柔軟に動くことで成り立っています。
この層が炎症や脱水などで硬くなると、振動の「しなり」が減少し、ビブラートのような微細な周期変化が生まれにくくなります。
特に声帯の粘弾性が高まると、基本周期(F0)の安定性が失われます。
TitzeとJiang(1993)は、粘膜層の弾性係数が増すことで、声帯が単調な運動しかできなくなり、揺れの幅が物理的に制限されることを報告しています。
また、Verdoliniら(1998)は、脱水によって発声しきい値圧(PTP)が上昇し、結果的に声の周期性が乱れることを示しました。
これは、声を出すためにより大きな圧力が必要になるため、声帯が「滑らかに動けなくなる」ことを意味します。
臨床現場では、軽度の声帯浮腫でもビブラートが減少するケースが多く見られます。
このような物理的な硬化がある場合、どれほどテクニックを工夫しても自然な揺れは戻りにくく、まず「声帯の環境を整える」ことが第一のステップになります。
2. 神経性・筋緊張性のビブラート障害
ビブラートは声帯の自動運動によって生まれますが、この動きを支えるのは神経と筋肉の微細な制御です。
中枢の運動野や脳幹、そして末梢の反回神経が正常に機能していなければ、周期的な揺れは維持できません。
神経性の異常では、パーキンソン病や本態性トレマーが代表的です。
Ramig(1987)は、ビブラートとトレマーを音響的に比較し、パーキンソン病患者の声では周期が強制的に揺れ続ける「過振動」型、 一方でMTD(筋緊張性発声障害)では逆に「揺れが消失する」型が多いと報告しました。
Angadiら(2016)は、MTD患者の喉頭映像を解析し、過剰な内筋収縮によって声門が固定され、声帯の微細な波動(mucosal wave)がほとんど見られなくなることを明らかにしました。
このような状態では、発声自体は可能でも“波打つような柔軟性”が失われており、ビブラートの土台が存在しないのです。
つまり、ビブラートの消失は、単なるテクニック不足ではなく、神経と筋肉の自動制御が阻害されていることの現れとも考えられます。
リハビリでは「力を抜く」よりも「正しい運動パターンを再教育する」方向性が必要になります。

3. 加齢によるビブラートの変化と失調
加齢による声の変化は、多くの歌手が避けて通れないテーマです。
年齢を重ねると、声帯筋(TA)や輪状甲状筋(CT)の筋線維が萎縮し、神経伝達の速度も低下します。
その結果、声帯の収縮スピードにわずかな遅れが生じ、ビブラートのRateが遅くなったり、Depthが浅くなったりします。
Higginsら(1999)は、高齢歌手の声を分析し、若年層に比べてビブラートのRateが有意に低下する傾向を報告しました。
またLinville(2004)は、声帯の筋線維萎縮が進むことで、声帯の可動性が減少し、周期的な揺れが物理的に発生しにくくなることを示しました。
加齢による変化は避けられないものですが、音声トレーニングによってある程度の回復が見込めることも知られています。
特に、軽いポルタメントや半音スライド練習、SOVT(半閉鎖発声法)による喉頭圧の安定などは、筋協調の維持に役立つとされています。
重要なのは、若い頃のビブラートを「取り戻す」ことではなく、現在の生理状態で「最も自然な周期」を再構築することです。
これにより、年齢を重ねても聴き心地の良い、穏やかなビブラートを保つことができます。
4. ビブラートの再獲得 ― Habilitationの視点
ビブラートが失われた声を再び安定させるには、「リハビリテーション」よりも「ハビリテーション(再教育)」の考え方が適しています。
これは、失われた機能を補うのではなく、正しい使い方をもう一度学習し直すアプローチです。
Titze(2006)は、SOVT(セミオクルーデッド発声法)が声門下圧を安定させ、周期的振動を回復させる効果を示しました。
またVerdolini-Abbott(2012)は、レゾナント・ヴォイス・セラピーが声帯振動を効率化し、ビブラートを含む自然な周期運動を再教育する手法として有効であると述べています。
これらの研究は、喉頭マッサージや脱力だけでは周期が戻らないケースでも、
正しい空気圧と共鳴の調整を繰り返すことで、神経—筋—音響の協調を再構築できる可能性を示しています。
つまり、自然なビブラートを再び生じさせるには、
「揺れを作る」練習ではなく、「周期的運動を許す環境」を作る練習が重要なのです。
具体的な段階的トレーニング構築法については、以下のリンクをご覧ください。
▶ ビブラート再獲得の段階的トレーニング構築法はこちら
5. 聴覚フィードバックと中枢制御の再構築
ビブラートの安定には、聴覚によるモニタリング機能が大きく関係しています。
自分の声を聴くことで、脳は「周期のズレ」を自動的に補正しています。
そのため、聴覚損失や耳鳴りがある場合、ビブラートのRateやDepthが不安定になりやすいことが知られています。
Lester-Smithら(2016)は、聴覚遮断条件下で歌唱を行うと、ビブラートの周期が乱れ、振幅が小さくなることを報告しました。
さらにZarate & Zatorre(2008)は、fMRI研究で、ビブラート制御時には聴覚野と運動皮質が同時に活動することを示し、 「聴くこと」と「発声すること」が神経的に一体化していることを明らかにしました。
このことから、ビブラートの再教育では、聴覚フィードバックの質を高めることが極めて重要です。
録音・録画を使って自分の揺れを可視化する、リアルタイム音響ソフト(SingScope, VoceVista, Praatなど)で周期を確認する、 または他者の安定したビブラートを模倣して聴覚ループを再構築する練習などが有効です。
聴覚を活性化することで、神経系が再び「安定した揺れ」を自動的に生成しやすくなります。
つまり、聴覚は単なるモニターではなく、ビブラートそのものを生み出す中枢的要素なのです。
6. 総括:ビブラートは「健康な声の指標」である
ビブラートの安定は、声帯や筋肉の健康だけでなく、神経・呼吸・共鳴・聴覚といった複合システムが正常に機能している証拠です。
Svec(2009)は、ビブラートを「声の健康を映し出す窓」と呼び、周期の規則性が喉頭の健全性を示す臨床的指標になる可能性を指摘しました。
ビブラートが消えるということは、声のどこかに「過剰」または「不足」が生じているというサインです。
それを単なる技術不足としてではなく、「システム全体の不調和」として捉える視点が、トレーナーとSLPの共通基盤になります。
自然な揺れを取り戻すプロセスは、声の再構築そのものです。
ビブラートを回復させることは、声を治すことではなく、声が本来持つ自動的で調和的な動きを再び許すこと。
それが、健康で音楽的な声の復権につながっていきます。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト
ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!
ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密