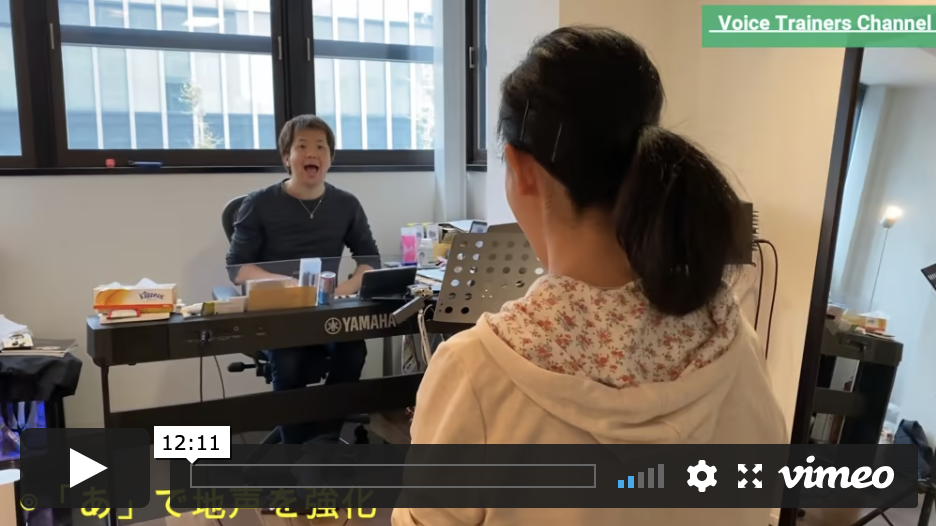第1話:ウォーミングアップで何が起こるのか?
あなたは歌う時にウォーミングアップをしますか?
桜田ヒロキ個人的には20代の頃から、ウォーミングアップが必須でした。ウォーミングアップなしでは高い声も詰まりますし、ピッチが悪くなります。なので、個人的には若い頃から今までウォーミングアップは必須です。
中には全くウォーミングアップを必要としないシンガーもいます。ただ、傾向としては多くのシンガーが年齢を重ねる毎に徐々にウォーミングアップの重要性に気づいていくようです。
ウォーミングアップを終えた時、実際に喉頭や声帯では何が起きているのでしょうか?
多くの歌手は「声が軽くなる」「高音が出やすくなる」「響きが整う」と感じますが、それがどのような生理的変化によって起こるのかを理解している人は多くありません。
本稿では、ウォーミングアップの科学的背景を整理し、研究で示されている生理変化と音響的効果を解説します。
さらに、桜田が現場で観察してきた「声の立ち上がり」「共鳴位置」「筋の再キャリブレーション(調整)」に関する臨床的視点も交えながら、歌手にとってウォームアップがどのような意味を持つのかを掘り下げます。
ウォーミングアップとは何か?
ウォーミングアップとは、発声筋群・呼吸筋群・共鳴腔の組織を発声に適した状態へ段階的に導く準備運動です。
一般的な運動と同じく、声のウォームアップにも「血流促進」「筋温上昇」「粘弾性の改善」「神経運動協調の再構築」といった生理的効果が期待されています(Sandage & Hoch, 2018)。
Elliott, Sundberg & Gramming(1995)は、声のウォームアップを行うことで声帯の振動がより滑らかになり、粘性が低下して発声しやすくなると報告しました。 この“粘性の低下”は、温度上昇と血流増加による粘膜層の軟化を意味します。 彼らは「声のウォームアップは筋の準備運動であると同時に、声帯の物理的状態を最適化する過程である」と定義しました。
つまり、単に「喉を慣らす」行為ではなく、発声機構の粘弾性・血流・神経活動を生理学的に整えるプロセスなのです。
声帯・喉頭レベルで何が起こるのか
声帯は、表層の粘膜(上皮・lamina propria)と、内部の筋層(甲状披裂筋=TA)から構成されています。
ウォームアップを行うと、まず局所血流が増え、筋と粘膜の温度が上昇します。
温度上昇に伴って粘膜の粘度が下がり、声帯がより柔軟に振動しやすくなる。 このとき、声門の開閉に必要な圧力——発声しきい値圧(Phonation Threshold Pressure, PTP)——が低下します。発声しきい値圧(Phonation Threshold Pressure, PTP)が下がると、シンガーは声帯に加える圧を減らす事が出来るので「声を出すのが楽」と感じます。
PTPの概念はTitze(2000)によって定式化され、声帯の粘弾性、声門閉鎖面積、気道密度などが複合的に影響することが示されています。粘性が低いほど声帯はより少ない気圧で振動を開始できるため、歌手は「声が軽い」「立ち上がりが良い」と感じます。
この段階では、声帯そのものだけでなく、舌骨上筋群や外喉頭筋群にも変化が起こります。血流が増えることで、これらの筋群の緊張がわずかに緩み、喉頭位置の制御がしやすくなる。 結果として、声区の切り替え(チェスト〜ミックス〜ヘッド)が滑らかになります。
神経筋制御の「再チューニング」

ウォーミングアップは筋や粘膜だけでなく、神経レベルでの協調運動にも作用します。
長時間の沈黙後、(例えば睡眠後)喉頭筋や呼吸筋はわずかに発火タイミングがズレた状態にあります。 声を出し始めて徐々に、これらの発火パターンが再調整され、必要なタイミングで適切に動くようになります。
この現象は運動学習の観点から「motor tuning」と呼ばれ、演奏家やアスリートでも確認されています。 発声では、喉頭・呼吸・共鳴腔の複数システムが同時に制御されるため、協調運動がズレると声門閉鎖が不安定になり、音質にムラが生じます。ウォームアップによって神経活動が整うと、声区移行点でのスムーズさや、音程変化の安定性が回復します。
音響的な変化
Amir, Amir & Michaeli(2005)は、12名の若年女性クラシック歌手を対象に、ウォームアップ前後の音響特性を測定しました。
結果として、jitter(基本周波数揺らぎ)とshimmer(振幅揺らぎ)の有意な低下、HNR(harmonics-to-noise ratio)の上昇、シンガーフォルマントの振幅増加が確認されました。
これらは発声が周期的・安定化し、倍音構造が整ったことを意味します。
特にメゾソプラノの被験者では改善が顕著であり、声種によって効果が異なる可能性も示唆されました。
この研究は、ウォームアップの効果が「主観的な感覚」だけでなく、音響学的にも客観的に測定できることを初めて明確に示したものとして重要です。
主観的評価と聴感の研究
Moorcroft & Kenny(2013)は、12名の女性クラシック歌手に25分間のウォームアップを行わせ、歌手自身と第三者リスナーがその変化を評価しました。
結果、歌手の多くは「声の操作性」「音色の自由度」「共鳴感」が向上したと感じましたが、聴取者がその変化を明確に認識できたのは一部の歌手に限られました。
つまり、ウォームアップの効果は主観的には強く感じられても、聴覚的に顕著に現れるとは限らない。
この研究は、ウォームアップの“体感”と“外部評価”のズレを示しており、トレーナーが生徒の声を聴く際には、主観的改善の裏にある物理的・生理的変化を見極める重要性を示唆します。
ウォームアップ時間と効果の関係
Ragsdaleら(2020)は、0分・5分・10分・15分の異なるウォームアップ時間を設定し、mVRP(Voice Range Profile)と自己評価スコア(EASE scale)を比較しました。
結果、5分または10分のウォームアップ後に高音域の最大F0(最大発声可能なピッチ)が上昇し、自己評価でも「声が出やすい」と感じた被験者が最も多かった。
一方、15分を超える長時間では必ずしも追加効果が見られず、過剰なウォームアップが疲労を招く可能性も示唆されました。
この研究は、ウォームアップが「やればやるほど良い」という単純なものではないことを示しています。
声の使用時間や前日の疲労度、喉頭筋のコンディションに応じて最適時間を調整することが望ましいと考えられます。
炎症軽減と回復への応用
Abbott, Li, Branski, Rosen & Verdolini(2012)は、急性音声負荷を与えた後に「レゾナントボイス」「声安静」「通常会話」の3条件を比較しました。
結果、レゾナントボイス群では声帯の炎症マーカーが最も低下し、組織回復が促進されたことが報告されました。この研究は、ウォームアップやクールダウン時に行われる“軽いレゾナント発声”が組織保護的であることを示しています。
桜田の現場でも、前日に声を酷使した歌手が翌日ウォームアップを丁寧に行うと、声の硬さが取れ、声の艶、音域が戻るケースが多く見られます。
これは、血流と振動による軽度マッサージ効果、さらには声帯表層の浮腫軽減が関係していると考えられます。
神経・筋・血流が連動する“準備のモデル”
以上の研究を踏まえると、ウォーミングアップ時には以下のようなプロセスが段階的に起こっていると整理できます。
1. 初期段階(1〜3分)
呼気流量の安定化と声門開閉リズムの再調整。外喉頭筋が徐々に活動を始め、喉頭位置が安定する。
2. 中期段階(4〜8分)
声帯筋群・呼吸筋の血流が増加し、粘膜温度上昇。粘性が下がり、PTPが低下する。声が軽く、柔らかく感じられる。
3. 後期段階(9〜15分)
神経運動協調が再構築され、発声パターンが最適化。音域拡張・フォルマント形成が整い、共鳴効率が上がる。
このモデルは、Sandage & Hoch(2018)が示した「発声を運動としてとらえる」観点とも一致します。
彼らは、ウォームアップが「筋の温度変化」だけでなく、「神経筋制御の再学習」によって声の機能を準備するものだと述べています。
効果の個体差と条件依存性
ウォームアップの効果はすべての歌手に均等ではありません。
研究では、以下のような個体差要因が報告されています。
– 声区・声種の違い:メゾソプラノなど中音域の歌手で効果が大きい傾向(Amir, 2005)
– 性別・ホルモンの影響:女性では月経周期による粘膜粘性の変動があり、日によって効果が異なる可能性
– 訓練歴・発声経験:訓練された歌手は協調運動の“初期チューニング”が速く、短時間で効果を感じやすい
– 疲労状態:声帯に微細浮腫がある場合、ウォームアップによる血流促進でむしろ一時的に違和感を感じるケースもある
こうした個体差を理解することで、ウォームアップを「万能の儀式」ではなく、「当日の身体状態を評価しながら最適化するプロセス」として捉えることができます。
実践への示唆
科学的知見を踏まえると、ウォームアップは次のような構成が最も合理的と考えられます。
1. 低強度のSOVT系(ストロー・リップトリル・ハミング)で3〜5分
→ 声門閉鎖と呼気流量のバランスを整える。喉頭筋群の微調整と血流促進。
2. レゾナント系発声で5分程度
→ 共鳴腔・音色の調整。軽い振動による粘膜の柔軟性改善。 (歌唱ではNay Nay等のややハイ・ラリンクスを伴うエクササイズ)
3. 音域拡張(スライド・スケール)を5分前後
→ 音高変化に伴う筋長調整を再キャリブレーション。
全体で10〜15分を目安とし、その日の喉の状態に応じて時間を変える。
この「段階的・短時間・低強度」アプローチは、Ragsdale(2020)の実験結果とも一致します。
クールダウンについて
ウォームアップが「声を使うための準備」であるのに対し、クールダウンは「声を守り、回復させる」段階です。 Ragan(2016)やAbbott(2012)の研究では、クールダウンが炎症軽減や疲労回復に寄与する可能性が示されています。
ウォームアップで血流を促し、クールダウンでそれを穏やかに戻す——この循環こそが、声の健康維持における基礎といえます。
次回の第2話では、ウォーミングアップとクールダウンの双方の効果とメカニズムをより詳細に比較していきます。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト
ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!
ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密