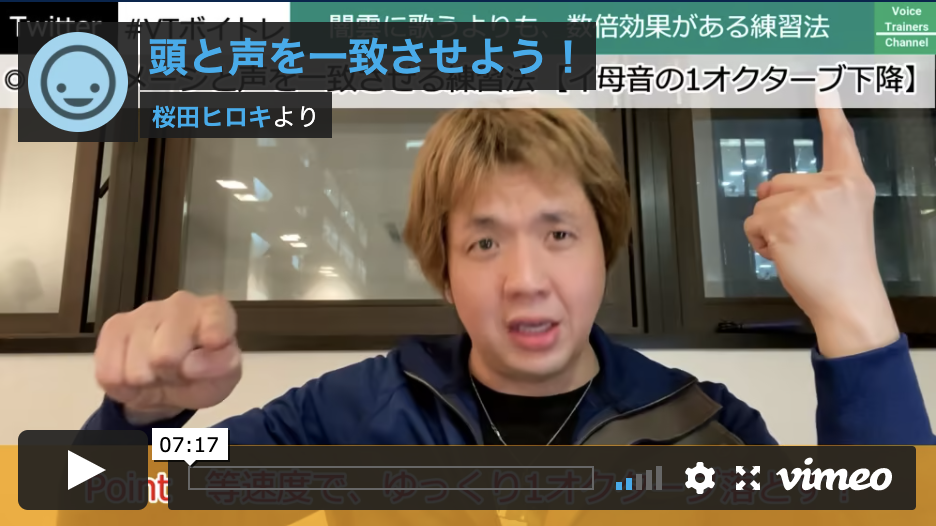発声障害とは?歌手が知るべき基礎知識
「声が詰まりやすい」
「高い声が出しづらい」
こうした悩みを抱えてレッスンにいらっしゃる方は少なくありません。
通常の話し声ではほとんど気にならなくても、歌い出した途端に息漏れや過緊張が現れる。
歌手にとっては声帯の内転(閉鎖)クオリティ(強すぎず弱すぎず)が非常に重要であり、極端な音域や強弱・音色操作といった高度な歌唱環境下では、わずかな乱れが即座に「発声不可能」な状態を引き起こすこともあります。
その背景に潜んでいるのが「発声障害」です。
本記事では、その基本を整理しつつ、歌手ならではの視点から理解を深めていきます。
発声障害の定義と大分類
発声障害(voice disorders)とは、声を出すための仕組みが適切に働かず、本人や周囲が「声が異常だ」と感じる状態を指します。
大きくは以下の3つに分類されます。
1. 器質性発声障害(Organic Voice Disorders)
声帯結節、ポリープ、声帯麻痺、萎縮など、解剖学的・神経学的な異常が原因。
痙攣性発声障害(Spasmodic Dysphonia)は神経性の器質性に含まれる。
2. 機能性発声障害(Functional Voice Disorders, FVD)
構造上は異常がなくても、発声の使い方や筋緊張のアンバランスによって声が出にくくなる。代表例が筋緊張性発声障害(MTD)。
3. 心因性(Psychogenic Voice Disorders)
心理的ストレスや心的外傷などが発声に影響するケース。器質・機能の異常が明らかでない場合に診断される。
この分類を押さえておくと、なぜ会話では問題ないのに歌唱で破綻するのかが理解しやすくなります。
歌手に多い発声障害の特徴
発症頻度の高さ
歌手を対象とした研究では、約半数が生涯で何らかの発声障害を経験するという報告もあります。
一般人口より有病率が高いのは、職業的な声の使用量と強度、そして表現上の要求水準の高さが関係していると考えられます。
声帯閉鎖の質が致命的
日常会話では声帯閉鎖が多少強すぎても、弱すぎても声として成立します。
しかし歌唱では「高音」「弱声」「声色変化」「長時間の持続」といった条件が加わるため、閉鎖のわずかな乱れが即座にパフォーマンス低下につながります。
結果として、高音・低音などの極端な音域や極端な歌唱技法(音量表現、音色表現など)の環境下では、直ちに発声不能に陥ることもあり得ます。
高負荷によるリスク
・長時間のリハーサルや連日公演
・強い発声(ベルティング、シャウト)
・特殊音色(ホイッスル、ファルセットエッジ)
こうした要素は、声帯・呼吸筋・共鳴腔に大きな負担をかけ、機能性障害を引き起こすリスクを高めます。
痙攣性発声障害(Spasmodic Dysphonia)
痙攣性発声障害は、声帯を動かす神経信号の異常により、発声中に筋肉が不随意に痙攣してしまう障害です。
「声が途切れる」「押し出されるように発声される」といった症状が特徴的で、器質性(神経性)発声障害に分類されます。
この障害は、MTD(機能性)と混同されやすく、診断は容易ではありません。
治療法としては、ボツリヌス毒素注射が有効とされますが、効果は一時的で繰り返しの施術が必要になります。
筋緊張性発声障害(MTD)
MTDは、声帯やその周囲の筋肉が過度に緊張し、スムーズな発声が妨げられる障害です。
・Primary MTD:他に器質的要因がなく、筋緊張が主因。
・Secondary MTD:声帯結節などの病変を補償するために起きる緊張。
緊張度合いによって症状も異なります。
・高緊張型:即座に声が押しつぶされる、硬い声になる → 歌唱に直結した不調。
・低緊張型:声が弱々しい、裏声に逃げる、代償発声が起こる → 長期的に疲労や不安定さにつながる。
歌手にとっては、音域拡張や表現力が制限され、キャリアに直結する重大な問題となります。
ケーススタディ①:音楽専攻の学生における筋緊張性発声障害(ASHA ケーススタディ)
アメリカの大学で音楽を専攻する20歳女性は、学期中盤から歌唱中に声の疲労感や高音の不安定さを訴えるようになりました。
日常会話では特に異常は見られなかったものの、歌唱時には声が途切れる、押し出すようになるといった症状が顕著でした。
診断は筋緊張性発声障害(MTD)。
しかし一人の専門家だけでは評価が難しいため、耳鼻咽喉科医、言語聴覚士、ボーカルコーチの三者が連携して治療に当たりました。
・医師は喉頭内視鏡で器質的異常がないことを確認。
・言語聴覚士は呼吸・共鳴のバランスを評価し、リラクゼーションと発声訓練を導入。
・ボーカル・コーチはレパートリーの調整や練習負荷のコントロールを担当。
6週間のプログラム後、学生は歌唱の持久力と音域を回復し、学業を継続できるまでに改善しました。
このケースが示すのは、歌手の発声障害は一人の専門家では対応できないということです。
むしろシンガー自身が「自分の声を回復に向かわせるチーム」のリーダーとなり、医師・言語聴覚士・トレーナーを統合的に活用する姿勢が求められます。
厳しい現実かもしれませんが、歌唱のようなQOLを高める行為には最終的な責任はあなた自身にあると言う事です。
ケーススタディ②:伝統歌手に対する喉頭マニュアルセラピー(Laryngeal Manual Therapy)
イランの伝統歌手32名を対象に行われた研究では、筋緊張性発声障害(MTD)を持つ歌手に対して「喉頭マニュアルセラピー(LMT/喉頭マッサージ)」を10回実施しました(1回30分前後、週1回)。

LMTは、頸部や喉頭周囲の筋肉に直接アプローチして緊張を和らげる手技療法です。
施術前後で音響分析と主観的評価が行われ、以下の改善が報告されました。
・発声の持続時間が延びる
・声の疲労感が減少する
・発声開始がスムーズになる
・音域の安定性が増す
興味深いのは、全員が一様に改善したわけではなく、発声の緊張パターンが変化した例もあったという点です。
この結果から言えるのは、マニュアルセラピーのみでの治癒は難しいということです。
発声障害は「誤った発声パターンを運動学習してしまった状態」である可能性が高く、筋肉を緩めるだけでは根本的な改善につながりません。実際には、発声訓練を通じて“エラーの上書き”を行い、正しい発声パターンを再学習させる必要があると予想できます。
歌唱領域での研究の不足と限界
ここで重要なのは、発声障害研究の多くは「話声」を対象にしているという点です。
歌唱に特化した研究はまだ少なく、治療法のエビデンスも限られています。
・個体差が大きい(声帯構造、発声訓練歴、歌唱ジャンル)
・医師や言語聴覚士が「正しい歌唱発声」を定義できない
・成果が一時的で、再発率が高いという報告もある(Robotti, 2023:再発率12〜88%)
つまり、歌唱の発声障害は「正解が定義できない」領域であり、臨床でも試行錯誤が続いています。
まとめ
・発声障害には 器質性/機能性/心因性 がある。
・歌手は、声帯閉鎖のわずかな乱れでも即発声不能に陥るリスクがある。
・痙攣性発声障害は器質性(神経性)に分類され、MTDとの鑑別が難しい。
・MTDは高緊張型と低緊張型に分けて理解でき、歌唱に与える影響が大きい。
・ASHAケースは、シンガーが「回復チームのリーダー」となる必要性を示す。
・イラン歌手研究は、マニュアルセラピー単独では不十分で、運動学習をやり直す発声訓練が必須であることを示す。
・研究は話声中心で、歌唱に特化した知見はまだ不足している。
次回は、「歌手と発声障害の診断が難しい理由」を取り上げ、芸術性・会話と歌唱の要求差・診断制度の壁について詳しく見ていきます。
歌手に多い「機能性発声障害(筋緊張性発声障害)」とは?
ボーカルマッサージと発声訓練 ― 職業歌手に必要な“緊張解除”と“運動学習”の二段構え
変声期を迎えた少年歌手の発声障害の例
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちら
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話