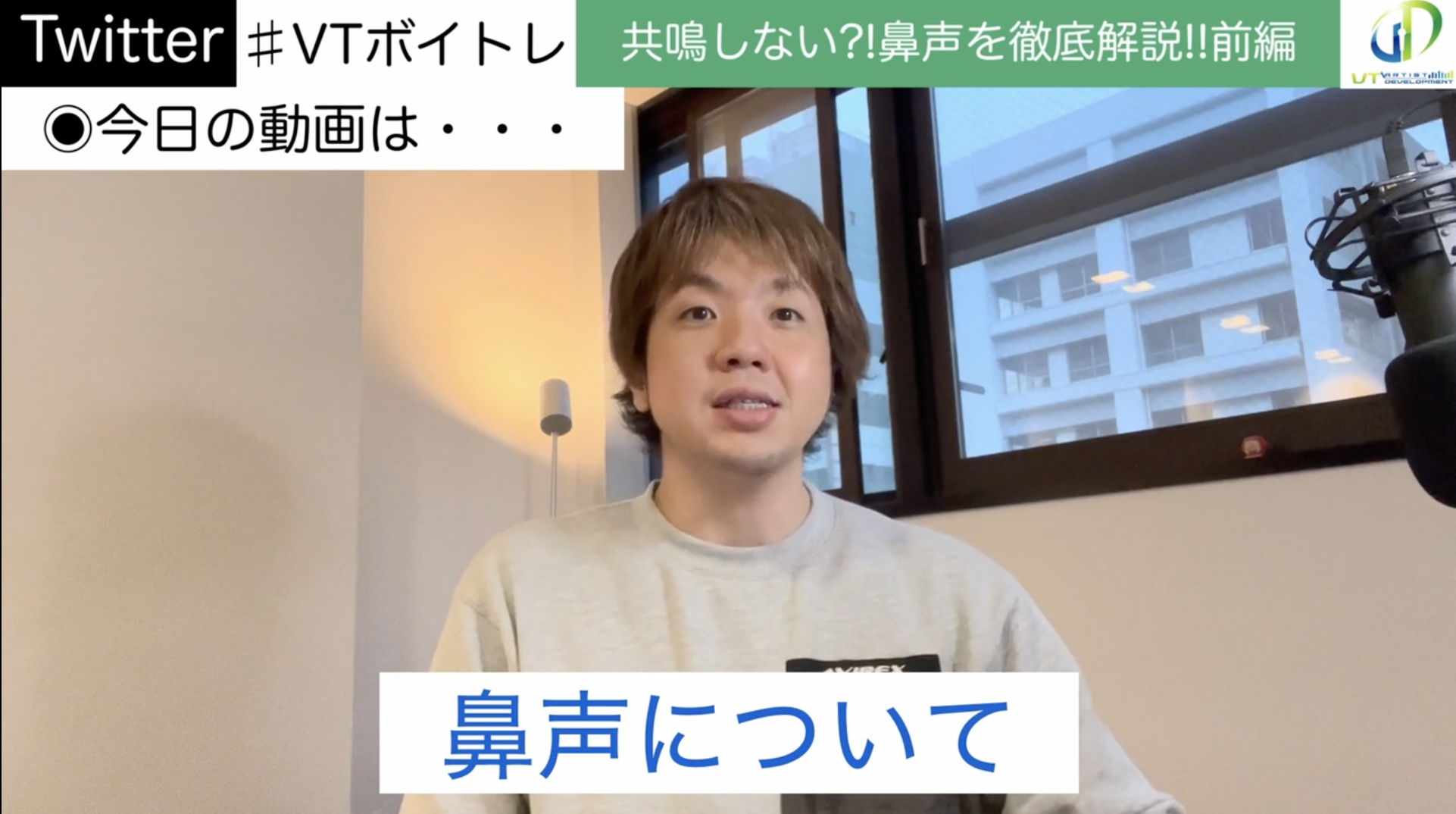第4話:歌唱発声と臨床評価の乖離
「会話は問題ないのに、歌うと声が詰まる」——
歌手や声優にとって、こうした悩みは決して珍しくありません。
実際、病院で診察を受けた際に「異常なし」と告げられるケースも多いのですが、その一方で本人は歌唱時に深刻なパフォーマンス障害を感じています。ここに、日常会話を前提とする臨床評価と、歌唱という高度なタスクの間に存在する大きな乖離が表れています。
本稿では、このギャップがなぜ生じるのかを整理し、研究知見と臨床の限界、そしてボイストレーニングによるハビリテーションの可能性について考察します。
1. 歌唱の要求と臨床検査のギャップ
臨床現場での検査は、ストロボスコピーや内視鏡を用いて「いー」といった簡単な発声をさせ、その際の声帯の周期性や閉鎖の程度を観察するのが一般的です。これは日常会話に必要な最低限の声の機能を評価するには十分ですが、歌唱のような高度な発声タスクを反映できているとは言いがたいでしょう。
歌唱には、以下のような特徴的な要求があります。
– メロディの変化に沿った複雑な声帯運動
– 母音と子音の連続的な切り替え
– 音圧レベル(SPL)の大きな変化=強弱表現
– 2〜3オクターブ以上の広い音域の使用
– 音色を自在に変化させる柔軟性

Verdolini & Ramig(2001)は「話声と歌声では声帯の生理的負荷が異なる」と報告し、Titze(2000)も「歌唱は話声に比べて声帯振動数や振幅が大きく、病理的影響が現れやすい」と述べています。つまり、臨床での発声タスクは歌唱の負荷を再現できず、そこで「異常なし」と判断されても、実際の歌唱環境では障害が露見するのです。
2. 検査で拾えない「歌唱特異的障害」
歌唱に特有の障害があることは研究でも報告されています。
Halsteadら(2015)は「Singer’s Dystonia(歌唱特異的ジストニア)」の症例を報告しています。
この患者は日常会話では全く問題がないにもかかわらず、歌唱になると発声が途切れ、音程が制御できなくなるという特徴を示しました。
ストロボスコピーでは決定的な異常が見られず、診断は困難でしたが、歌唱というタスクにおいてのみ顕著な障害が現れていたのです。
またRoyら(2003)は、歌唱に特化した音声障害は「診断基準が未整備」であることを指摘しました。臨床での「いー」での発声だけでは再現できない問題が多いため、歌手が訴える「高音が詰まる」「弱声が安定しない」といった症状は、臨床上「異常なし」とされやすいのです。
3. 臨床評価における課題
臨床現場の目的は、基本的に「患者が日常生活に支障なく声を使えるかどうか」を評価することにあります。つまり、会話ができるか否かがゴールであり、歌唱のような芸術的・高度技能の回復は必ずしも考慮されていません。
そのため、歌手が訴える「高音でのつまり」「弱声での不安定さ」「音色の再現性」といった問題は、臨床評価ではゴール設定に含まれない場合が多いのです。Frameworks, Terminology and Definitions for Voice Disorders(2022)は、発声障害の分類や定義に揺らぎが多く、歌唱を臨床評価に組み込む体系は存在していないことを明言しています。
結果として、歌手にとっては「検査では異常なし、でも歌えない」もしくは「所見上、異常はないが、本人の認識で声が出しにくいと認識しているので、機能性発声障害と診断をしてリハビリを行う」と行う事になります。
桜田が問題と感じているのは後者の方で、異常の発見が出来ていない状態でとりあえずリハビリを行ってみると言う状況です。
もちろん評価が行えていないので、目標設定も曖昧なものになってしまいます。
臨床現場でもより歌手に寄り添った評価法の開発が急務と考えられます
4. リハビリテーションとハビリテーションの目的の違い

この乖離を理解するうえで重要なのが、リハビリテーションとハビリテーションの違いです。
– リハビリテーションの目的は、基本的な声の使用に耐えられる発声を目標とすることです。つまり、会話が問題なく行えるレベルを回復することが主眼です。
– ハビリテーションの目的は、基本的な声の使用を大幅に上回る機能の習得を目指すことです。そもそも歌唱自体が基本使用を大きく超えるタスクであるため、ハビリテーション的な視点が不可欠です。
ただし、両者は明確に分かれるものではなく、オーバーラップする領域も多数存在します。だからこそ、医師・言語聴覚士(SLP)・ハビリテーションに精通したボイストレーナーの連携が不可欠であり、これが今後の課題となるのです。
5. ボイストレーニングと臨床の接点
ボイストレーナーは歌唱の要求水準を理解しており、医師やSLPと連携することで、歌唱特有のゴールを補完できます。
たとえば「高音で詰まらない」「弱声が持続できる」「特定の音色を再現できる」といったゴールは臨床検査では数値化できませんが、ボイストレーニングを通じて実現可能な領域です。
ASHA(2009)のケーススタディでも、医師・SLP・ボイストレーナーがチームを組むことで、大学生歌手の機能性発声障害を6週間で改善に導いた例が報告されています。またMathiesonら(2009)は、音声治療に歌唱発声練習を組み込むことで治療効果が高まることを示しました。
つまり、歌唱の臨床評価とボイストレーニングは二重構造として統合される必要があるのです。
6. 今後の方向性
今後は、歌唱を含めた臨床評価体系の整備が急務です。
その補助となる可能性があるのが、AI音響解析や長時間モニタリングです。Nature(2025)の「Differentiability of voice disorders through explainable AI」では、AIを用いた音響特徴解析によって異常声の分類が試みられています。さらに「Uncovering Voice Misuse Using Symbolic Mismatch(2016)」では、加速度センサーを用いて長時間の発声データを収集し、誤用パターンを検出する方法が報告されています。
こうした技術を活用すれば、従来の「いー」発声での診察にとどまらない、歌唱特有の発声を含めた評価が可能になるでしょう。
最終的には、臨床評価+ボイストレーニングによるハビリテーションという統合的なアプローチこそが、歌手の声を守る理想的なシステムになると考えられます。
まとめ
– 歌唱は会話よりも高い要求水準を持ち、臨床評価では拾いきれない障害が存在する
– Singer’s dystoniaのように、歌唱特異的障害はすでに報告されている
– 現状の臨床は「異常なし」とされても、歌手本人は深刻なパフォーマンス障害を抱える
– リハビリテーション=基本声使用の回復、ハビリテーション=高度技能の獲得という違いがある
– しかし両者は重なる部分も多く、医師・SLP・ボイストレーナーの連携が不可欠
– 将来的にはAI音響解析+長時間モニタリングの導入によって、歌唱に即した臨床評価が実現する可能性がある
歌手の声を守るには、臨床の枠を超えて、ボイストレーニングと医療が一体となる新しい発想が必要です。それこそが、歌唱という特殊な発声行為にふさわしい評価と回復のあり方なのです。
歌手に多い「機能性発声障害(筋緊張性発声障害)」とは?
ボーカルマッサージについてはこちら
サーカム・ラリンジャル― 声を不自由解放するための科学と実践
変声期を迎えた少年歌手の発声障害の例
ツアー中に発声障害に罹患したロック歌手のケース(第1話)
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話