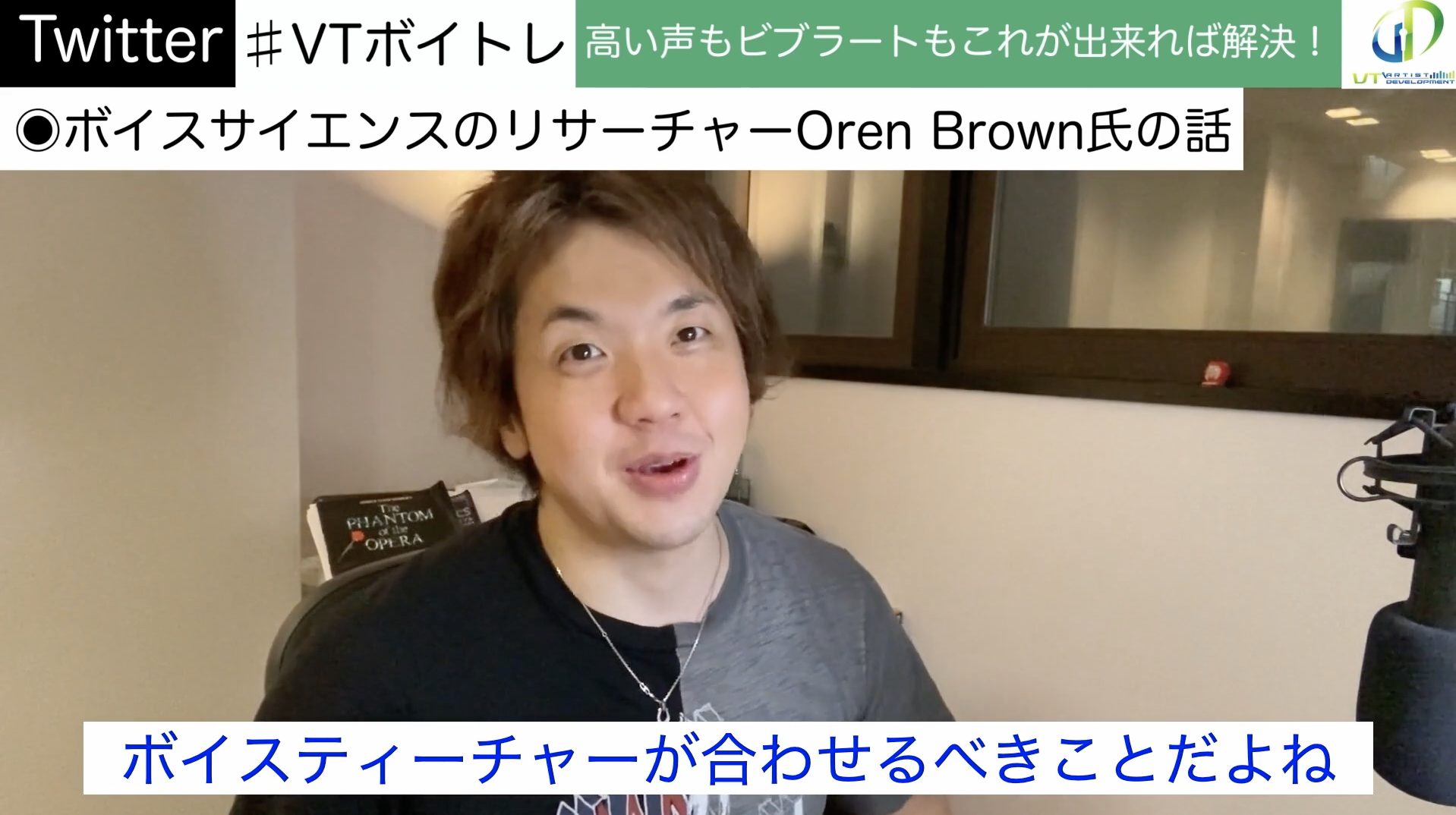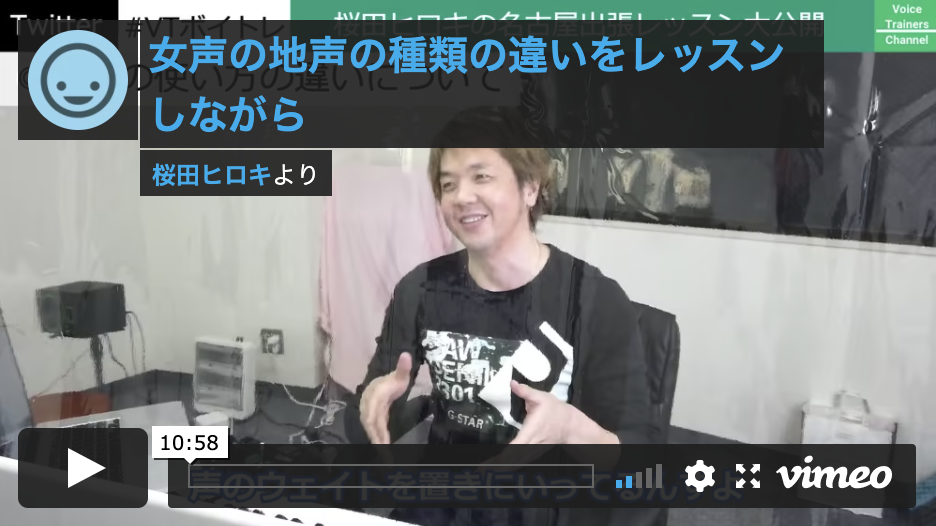機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括
歌手にとって声は単なる楽器ではなく、自身の存在そのものを伝える表現手段です。
しかし現実には、多くの歌手が声の不調に悩み、時にはキャリアを左右する重大な局面に直面します。
「高音が出にくくなった」
「声がかすれて思うように響かない」
「ステージに立つと急に声が詰まる」
こうした訴えを持ちながら病院に行くと、「検査上は異常なし」と診断されるケースが少なくありません。
器質的な病変が見つからない一方で、歌唱における深刻な困難が続く。これが機能性発声障害と呼ばれる領域であり、歌手に特有の課題です。
本シリーズでは、全8話にわたり「歌手と機能性発声障害」をテーマに取り上げました。
ここではその総括として、各話を振り返りながら全体像を整理していきます。
第1話:発声障害とは?歌手が知るべき基礎知識
第1話ではまず「発声障害」という言葉の整理から始めました。
大きく分けると、声帯に結節やポリープといった物理的な変化が生じる器質性発声障害と、構造に異常がないにもかかわらず発声が困難になる機能性発声障害があります。
歌手に多いのは後者です。検査で「異常なし」とされながらも、歌唱時にのみ深刻な問題が現れる。
声帯の内転が微妙に乱れるだけで、高音や繊細な音色表現が崩壊し、即座に「発声不可能」な状態に陥ることさえあります。
第2話:歌手の発声障害ってなぜ治療やリハビリが難しい?
第2話では、診断や治療が難しい理由を掘り下げました。
会話ではほとんど問題が出ない一方で、歌唱時には致命的な不具合が現れる。この「落差」が診断を難しくしています。
臨床現場では「いー」「あー」といった短い発声で評価することが多く、歌唱特有の高音・声区移行・母音子音の連続発声といった複雑な要素は検査に反映されにくいのです。
また、医師や言語聴覚士が芸術的要求を評価枠組みに入れにくいことも障害の理解を妨げています。
第3話:機能性発声障害(MTD)の理解と歌手への影響
第3話では筋緊張性発声障害(MTD)に焦点を当てました。
高緊張型は喉頭や声帯に過剰な力が入り、即座に声が詰まる。低緊張型は逆に声帯閉鎖が不十分で、息漏れやかすれが続く。
どちらの型でも代償的な声の出し方を学習してしまうと、発声パターンそのものが誤った運動学習として固定化されます。
そのため、単なる安静や休養では回復せず、正しいパターンの再学習が不可欠になります。
第4話:歌唱発声と臨床評価の乖離
第4話では、臨床検査と実際の歌唱の間にある大きな乖離を取り上げました。
医師の診察は「地声でいー、裏声でいー」といった単音発声が中心ですが、歌唱はダイナミクスや母音子音の連続、音域移行など、まったく異なるタスクです。
このギャップが、歌手が「異常なし」と診断されながら苦しむ現実を生み出しています。
第5話:代償発声と二次的障害
第5話では、障害を抱えた声を補うために使われる代償発声のリスクを解説しました。
無理な発声パターンを続けることで、結節やポリープといった二次的障害を招く可能性があります。
重要なのは、音響的な変化やストロボ所見だけではなく、本人が苦しいと訴えているかどうかを重視する視点です。
第6話:心因性要素・歌手のイップスと発声障害
第6話では心因性の要素を取り上げました。
スポーツで知られるイップスは、過度な緊張や失敗体験によって身体の動きが阻害される現象です。歌手でも「マイクの前に立つと声が詰まる」という症状がみられることがあります。
実際のクライアントの例では、ハンドマイクを電源オフの状態から慣れてもらい、段階的に克服できたケースも紹介しました。
第7話:機能性発声障害における統合的アプローチ
第7話では、医師・SLP・ボイストレーナーの三位一体の取り組みが必要であることを整理しました。
– 医師:器質的疾患を除外し、診断名をつける
– SLP:会話レベルの機能回復を目指すリハビリを実施
– ボイストレーナー:歌唱という高難度タスクに必要なハビリテーションを担う
そして何より、歌手本人が自分の声を守るチームのリーダーになることが強調されました。
第8話:発声障害の予防法・セルフケア
最終話では予防とセルフケアに焦点を当てました。
– 声の衛生:水分補給、発声過用の回避、逆流性胃食道炎(LPR)の管理、十分な休養
– ウォーミングアップ:SOVTやハミングで効率的に声を準備
– クールダウン:SOVT、あくび発声、頸部ストレッチで発声後の緊張を解放
さらに、強化された声の衛生教育を受けた患者が手術を回避できたという研究結果も紹介されました。
総括 ― 声を守り、育てるために
シリーズ全体を通じて明らかになったのは、以下の点です。
– 機能性発声障害は「一人の専門家」では対応できない
– 歌唱発声は臨床評価と大きく乖離しており、診断が難しい
– 無理な代償発声は二次的障害を招く
– 心因性要素やイップスが声を阻害するケースもある
– 医師・SLP・ボイストレーナーの連携が不可欠
– 声の衛生、ウォーミングアップ、クールダウンといった予防策が有効
歌手に対しての医療支援が不足している事は今回の調査で明らかになったと思います。
しかしながら、ボイストレーナー達が声の器質的、機能的な障害共に理解が低いのも間違いのない事です。
お互いに知見を深め、歌手のサポート体制を確立するするためにも双方の理解や勉強が早急に必要とされている事と考えます。
結局のところ、ボイストレーニングは歌を上手くするだけでなく、声を守り育てる科学的支援です。
そして、歌手自身が主体的に声のケアに取り組むことが、キャリアを守る最も確かな方法です。
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話