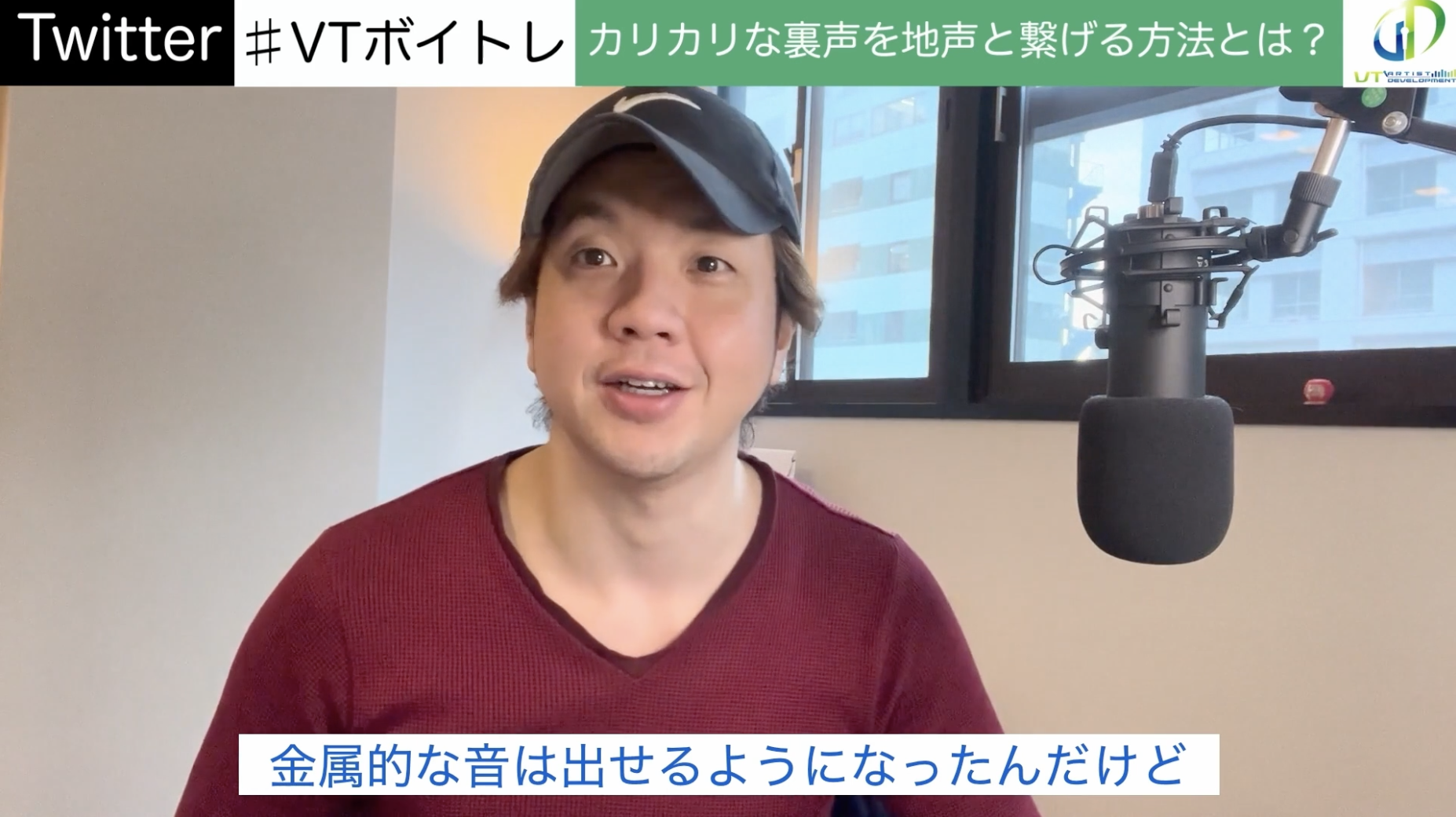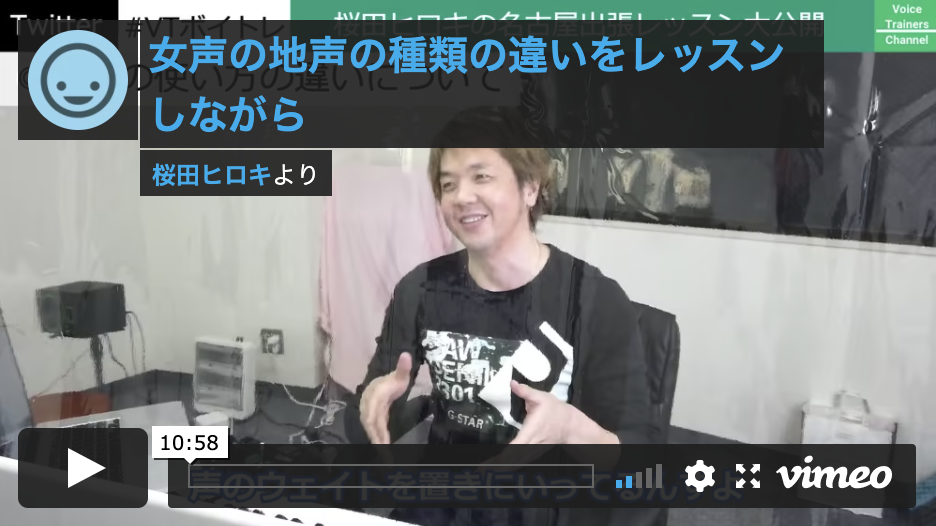- 2025.10.11
- マインドセット・練習法 ミックスボイス
第4話:トレーニング実践編 ― セルフ練習とハビリテーションの視点から
歌を学んでいる人の多くが一度は抱える悩みがあります。
「毎日練習しているのに声が変わらない」
「どんな練習をすればよいのか分からない」
「声の調子が安定しない」
こうした状況の多くは、練習方法が間違っているというよりも、自分の声の傾向を理解せずに練習している事に起因します。声は筋肉と呼吸の協調運動で成り立つ高度なシステムです。自分の声が「どのパターンに偏っているか」を知らないまま闇雲に練習を重ねても、なかなか成果は出ません。
そこで有効なのが、診断 → タイプ別練習 → 再診断というサイクルです。これはリハビリテーションではなく、健康な声をより良くするための「ハビリテーション(habilitation)」の考え方と共通しています。
診断の重要性

桜田が開発した VoiceToolsは、この問題を解決するために作られました。
動画の指示に従って声を出し、自分の声を録音するだけで、システムが「プルチェスト」「ライトチェスト」「フリップ」「ミックス」の4つのタイプに分類します。
例えば高音で苦しそうに張り上げる人はプルチェスト、息が混ざりすぎる人はライトチェスト、声がひっくり返る人はフリップ、安定している人はミックスに分類されます。
分類が明確になることで、「なぜ高音が出ないのか」「なぜ声が不安定なのか」という疑問に答えが出るのです。
そしてその解決トレーニングを行う事が出来ます。
男女別の動画のガイダンスに従ってボイストレーニングを行えば、自分の悪い癖を改良していく事が出来ます。
タイプ別の特徴と練習方向性
プルチェスト
どう聞こえるか:E4以上で苦しそうに張り上げる声。音量はあるが硬く、喉に負担がかかる。
何が起きているか:甲状披裂筋(TA)が過剰に働き、輪状甲状筋(CT)の伸展と協調できていない。声門下圧が過剰になり、声帯が過緊張している。
改善法:裏声の導入やSOVT(ストロー発声)を取り入れ、Zoo、Lip Bubble、Wee、Nayといった軽いエクササイズで声帯のバランスを整える。
プルチェストのトレーニング・ツールはこちら
ライトチェスト
どう聞こえるか:息が混ざり、声が軽い。特にF4〜G4以上で声が前に飛ばず、輪郭がぼやける。
何が起きているか:声門閉鎖が弱い。披裂筋群(LCAやIA)の内転が十分でなく、H1–H2差が大きくなり、息っぽい声質になる。
改善法:閉鎖を促すNay、子音を使った発声、閉鎖強化型のSOVT練習。
ライトチェストのトレーニング・ツールはこちら
フリップ
どう聞こえるか:声が急に裏返り、声区が分断されている。ブレイクが顕著。
何が起きているか:M1(地声)からM2(裏声)への移行がスムーズに行われていない。声道共鳴のサポート不足。
改善法:スライディング(sirening)練習や、声区移行を意図的に行うブリッジ練習。
フリップのトレーニング・ツールはこちら
ミックス
どう聞こえるか:バランスが取れていて安定しているが、ジャンルや音色によっては物足りなさを感じることもある。
何が起きているか:M1とM2の接続がスムーズに行われており、声門閉鎖や声道調整の微調整が課題。
改善法:ジャンル別に必要な音色練習、共鳴操作や声道の開閉コントロール。
ミックスのトレーニング・ツールはこちら
学習サイクルの設計
診断ツールとトレーニング動画を組み合わせることで、次のようなサイクルが可能になります。
1. 診断を受ける
2. 動画でタイプ別エクササイズを行う
3. 2〜4週間継続する
4. 再診断を受けて変化を確認する
この循環は、ただ練習を「流す」のではなく、自分の声の変化をモニタリングする習慣を育てます。これこそがセルフトレーニングを成功させる最大のポイントです。
ハビリテーション研究からの示唆
ここで、声の練習を「どう設計するか」という問いに答えてくれるのが、ハビリテーションや運動学習の研究です。
練習頻度と分散学習
Wulf & Shea (2002) は、運動学習において分散学習が集中学習よりも保持率が高いと示しました。
歌唱も同様で、「1日1時間連続」よりも「20分×2回」の方が定着しやすい。
練習時間の上限
Titze (2000) は、発声は筋疲労・組織疲労が蓄積しやすいため、1回20〜30分が望ましいと指摘しました。
桜田の動画コンテンツも1回20分設計であり、これは科学的にも理にかなっています。
声のドージング(Voice Dosing)
Verdoliniらの研究では、発声練習を「薬の処方量」として捉える考え方が示されています。
少なすぎても効果がなく、多すぎると炎症や疲労を招く。
最適なのは短時間・複数回・長期継続。
SLP領域の実証研究
Resonant Voice Therapyの臨床研究では、1日複数回の短時間練習がもっとも効果的と報告。
今日できたかどうかではなく、翌日に残っているかを評価することが大切。
4タイプ分類はゴールではない
4つのボイスタイプに分けてトレーニングを行うことは、あくまで一つの基準に過ぎません。もちろん非常に重要な基準ですが、最終目標ではありません。
この分類が意味を持つのは、声区(レジスター)の行き来が不自由な状態に対応するためです。
プルチェストやフリップといったタイプは、声区移行に問題を抱えているため、まずはそこを整理する必要があります。
しかし、実際の楽曲で求められるのは「声区をスムーズに行き来できるか?」の先にあるスキルです。
声区のコントロールができた上で、次のような演奏技術が問われるのです。
– 声色を一定に保つことができるか
– 必要に応じて声色を変化させられるか
– 予定したダイナミクス(強弱表現)を自在にコントロールできるか
– 音楽的なフレーズに合わせて柔軟に声を使えるか
– 表現の一部として自然なビブラートをかけられるか
これらを総合してプロフェッショナルな演奏として考えられる歌唱を作る必要があります。
つまり、4タイプ分類は出発点であり、「声区を制御した上でどんな音楽的表現ができるか」という次の段階に進むことが本当の目的です。
桜田の現場経験
桜田のスタジオでも、長時間連続でやみくもに練習して声を枯らしてしまう生徒が少なくありませんでした。
しかし「20分を1日2回」に切り替え、さらに「診断 → タイプ別エクササイズ → 再評価」を徹底したところ、声の安定性が格段に上がった例が多くあります。
また、練習記録をつける習慣を持った生徒ほど、自分の課題を客観的に見つけ出し、改善のスピードが速い傾向があります。練習を流すのではなく、分析する姿勢が集中の質を高めるのです。
まとめ
セルフボイストレーニングを効果的に進めるには、感覚や経験に頼るだけでなく、診断 → 練習 → 再診断という科学的なサイクルを回すことが欠かせません。
さらに、ハビリテーション研究が示すように、練習は「短時間・分散型・長期継続」が最も有効です。
桜田が制作した診断ツールと20分の動画トレーニングは、この最新知見と完全に一致しており、初心者でも安心してセルフトレーニングを始めることができます。
そして何より大切なのは、声を「健康的に育てる」という視点です。
ボイストレーナーの指導とセルフトレーニングは対立するものではなく、むしろ補完し合うものです。診断ツールはその入口であり、継続した練習と専門家の導きがあって初めて、歌声は長期的に安定し、自由になります。
機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括
👉 第1章:ミックスボイスとは何か? ― 定義と誤解
👉 第2章:ブレイクの正体 ― 地声/裏語と声道の相互作用
👉 第3章:ジャンル別のミックス ― クラシックとCCMの違い
👉 第4章:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても疲れる理由
👉 第5章:レジスター移行の科学 ― SourceとFilterの関係
👉 第6章:4つの共鳴ストラテジー
👉 第7章:ベルティングの実践と限界
👉 第8章:Airflowと声門下圧のバランス ― 効率的で安全なベルティング
👉 第9章:声の音量とエネルギー効率 ― SPLで見る発声の個性
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!
ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?