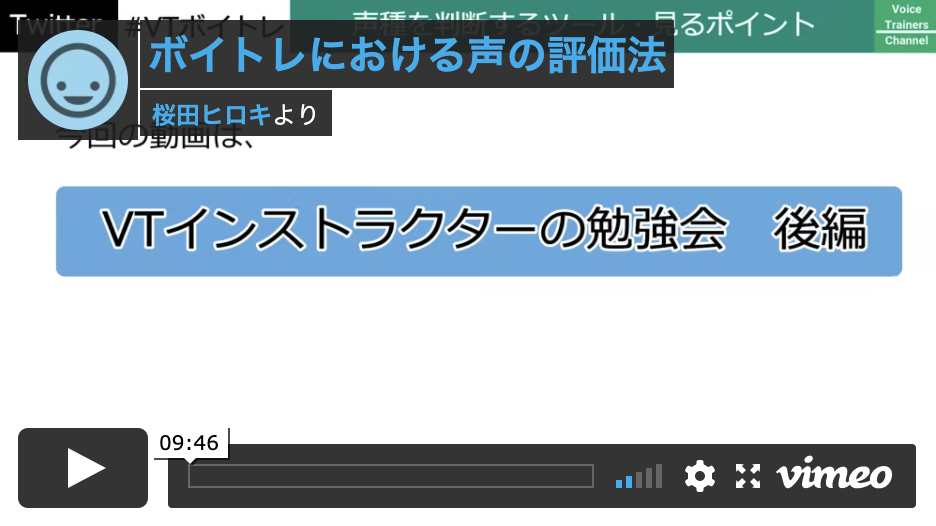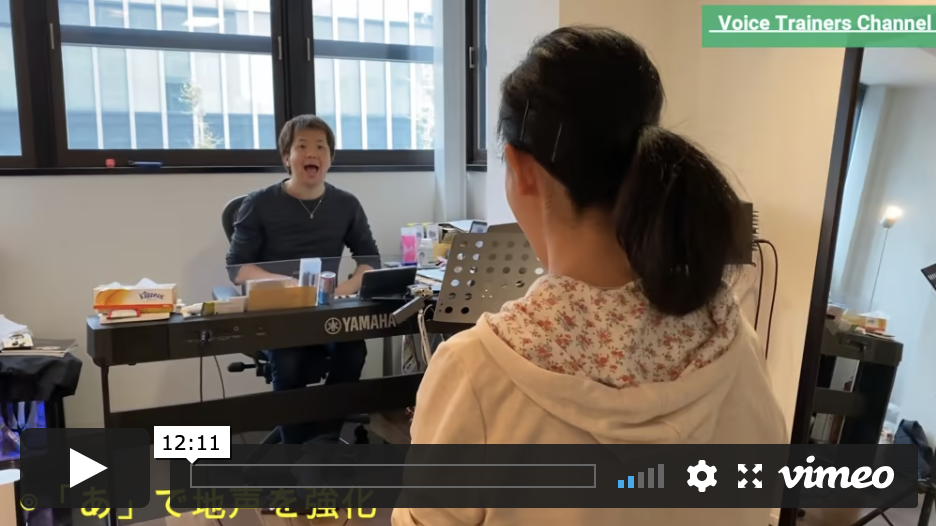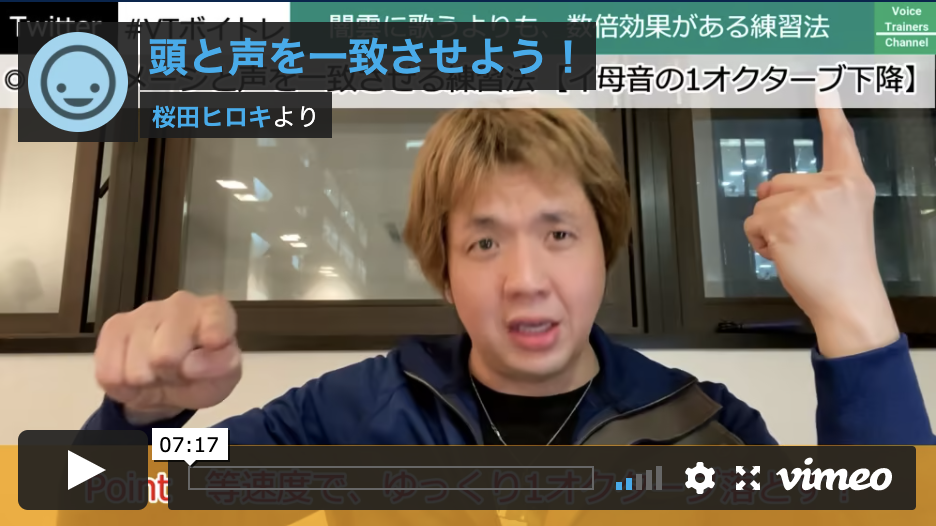声の不調の原因は? ― 医学データで見る発声トラブルの実態
「最近、声が出にくい」「喉の違和感が取れない」「高音が詰まる」
こうした訴えは、歌手だけでなく声優、講師、経営者、コールセンター業務の方など、声を職業として使う多くの人に共通しています。(American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)ではこのように声を使う多くの職種をボイスプロフェッショナルと定義しています。)
しかし、その原因を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。風邪や結節など目に見える異常がある場合もありますが、実際には検査で異常が見つからないケースも多く、そうした場合にしばしば診断されるのが機能性発声障害です。
今回は、国内外の臨床データをもとに「声の不調がどこから来るのか」を整理し、声を使う人が知っておくべき実態をまとめます。
声のトラブルは大きく3種類ある
声の不調はすべて同じではありません。大きく分けると次の3つに分類されます。
1. 器質性発声障害(声帯ポリープや結節など、構造的な変化が原因)
2. 機能性発声障害(構造的異常がないのに声が出にくい。代表は筋緊張性発声障害・MTD)
3. 心因性発声障害(心理的ストレスや運動制御の乱れによって声が詰まる)
これらは単独で起きることもあれば、重なって発症することもあります。たとえば風邪をきっかけに声を無理して使い続け、発声のクセが歪み、そこに心理的ストレスが加わる…といった流れです。
臨床データで見る「声の不調の原因」
成人(一般嗄声)
日本国内の外来統計では、嗄声の診断内訳は次の通りと報告されています。
・急性喉頭炎:42.1%
・慢性喉頭炎:9.7%
・機能性発声障害:30%
・良性腫瘍(ポリープ・結節など):10〜31%
・悪性腫瘍:2〜3%
約3人に1人は「構造異常のない声のトラブル=機能性発声障害」に分類されます。比率の高さからも、声の不調の多くが「見えない異常」であることがわかります。
成人(MTD=筋緊張性発声障害)
臨床報告(調査対象=65名)による主観的誘因の内訳
・精神的ストレス:46%
・声の誤用・乱用:17%
・身体的疲労:12%
・特に誘因なし:32%(ただし64%がストレス関連の出来事をを経験)
このデータから、機能性発声障害(MTD)の発症には「ストレス」「誤用・過用」「身体疲労」という3要素が関与していることがわかります。歌手や声優、教師など、声を酷使する職業ではこのリスクが特に高いとされています。
小児(機能性発声障害)
施設報告による内訳
・感冒などの上気道感染後:38.1%
・声の過用:21%
・原因不明:31%
子どもの場合は「風邪を引いたあとに無理に声を使った」ことが引き金になっているケースが多い。これは成人にも通じる部分であり、「感冒後の無理な発声」が慢性化の起点になる可能性を示唆しています。特に風邪を引いた状況でも声を使わなくてはいけないというプロフェッショナル・ユーザーには注意が必要と言えると思います。
データから見える「声のトラブルの構造」
これらのデータを総合すると、声の不調の構造は次のように整理できます。
・子どもの段階では「感冒+声の使いすぎ」が主因
・成長とともに「誤用・過用」+「ストレス・心理要因」へと移行
・器質的障害よりも「機能的な使い方の歪み」が中心的な原因
つまり、声の不調の多くは「使い方の問題」と「心身の負荷」の複合体です。これはスポーツでいえばフォームの崩れに近く、声を出す筋肉群のバランスが崩れた状態といえます。
「ストレス」と「誤用・過用」が生む負のループ
ストレスは声の使い方そのものに影響します。ストレス下では呼吸が浅くなり、外喉頭筋の緊張が高まります。その状態で声を出し続けると、喉頭が引き上げられ、声帯閉鎖が不均等になり、結果的にさらに「出にくい声」を作り出してしまいます。
一方で、出にくさをカバーするために力を入れると(代償発声)、喉頭の緊張はさらに強まり、症状は悪化します。これが典型的な機能性発声障害の悪循環です。
声の誤用・過用とは何か?
誤用とは、声を出す際に不必要な筋緊張や誤った共鳴を使ってしまうこと。過用とは、正しい発声でも時間や強度が過剰になること。たとえば次のような状況が典型です。
・風邪気味のまま本番やレコーディングに臨む
・騒がしい環境で長時間話す
・マイクのない場所で大声で歌い続ける
・ステージでのモニター音量が小さく、無意識に力んでしまう
これらはすべて機能性発声障害のリスク因子です。特に歌手の場合、高音や強弱表現といった要求水準が高いため、声帯への負担は日常会話の比ではありません。
声のトラブルを防ぐには
予防の基本は、声の衛生(vocal hygiene)と適切な発声習慣です。
・水分をこまめに摂る(体重1kgあたり30〜40ml)
・声を使いすぎた翌日は休声日を設ける
・騒音環境ではマイクを使用し、無理に声を張らない
・風邪や喉の炎症があるときは徹底的に休む
・長時間の練習より、短時間集中+インターバル型を意識
・クールダウンやウォーミングアップを積極的に取り入れる
・ボーカルマッサージを使い、発声関連筋のリラクゼーションを行う
ウォーミングアップ(怪我防止)を取り入れる
歌唱前にSOVT(ストロー発声・リップトリル)、軽いハミング、低〜中音域の段階的音階練習を行い、声帯・呼吸・共鳴の同調を整える。ウォームアップは発声準備性を高め、声帯への衝突圧や過緊張を抑え、怪我(声帯微小損傷)の予防につながる。
参考記事(貼り付け)
第1話:ウォーミングアップで何が起こるのか?
第2話:ウォーミングアップとクールダウンの科学的メリット
クールダウンを取り入れる
歌唱・練習後にSOVT、あくび発声(Yawn-Sigh)、頸部ストレッチ・マッサージを数分〜10分ほど。発声後の緊張を解放し、翌日の声帯疲労の残存を抑える。F0上昇や震えの改善傾向を示す研究も報告されている。
ボイストレーニングは再発予防のリハビリ
構造に異常がない機能性発声障害は、薬や手術では根本的に治りません。必要なのは「使い方の再教育=発声ハビリテーション」です。正しい呼吸・喉頭の位置・共鳴バランスを再学習し、過剰な筋緊張を解除していくプロセスは、医療でいうリハビリテーションに近い考え方です。つまり、ボイストレーニングは単なる技術向上ではなく、再発防止に直結する取り組みです。
まとめ ― 声の不調の多くは“使い方”で防げる
データを見ても、声の不調の多くは過用・誤用・ストレス・感冒後の無理な発声など、日常的な要因が重なって発生しています。だからこそ、「声の出し方」と「心身のコンディション」を整えることができれば、その多くは防げる。
声を使う仕事をする人にとって、日々のケアとボイストレーニングの両輪が、声を守り、育てる最善の戦略です。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話