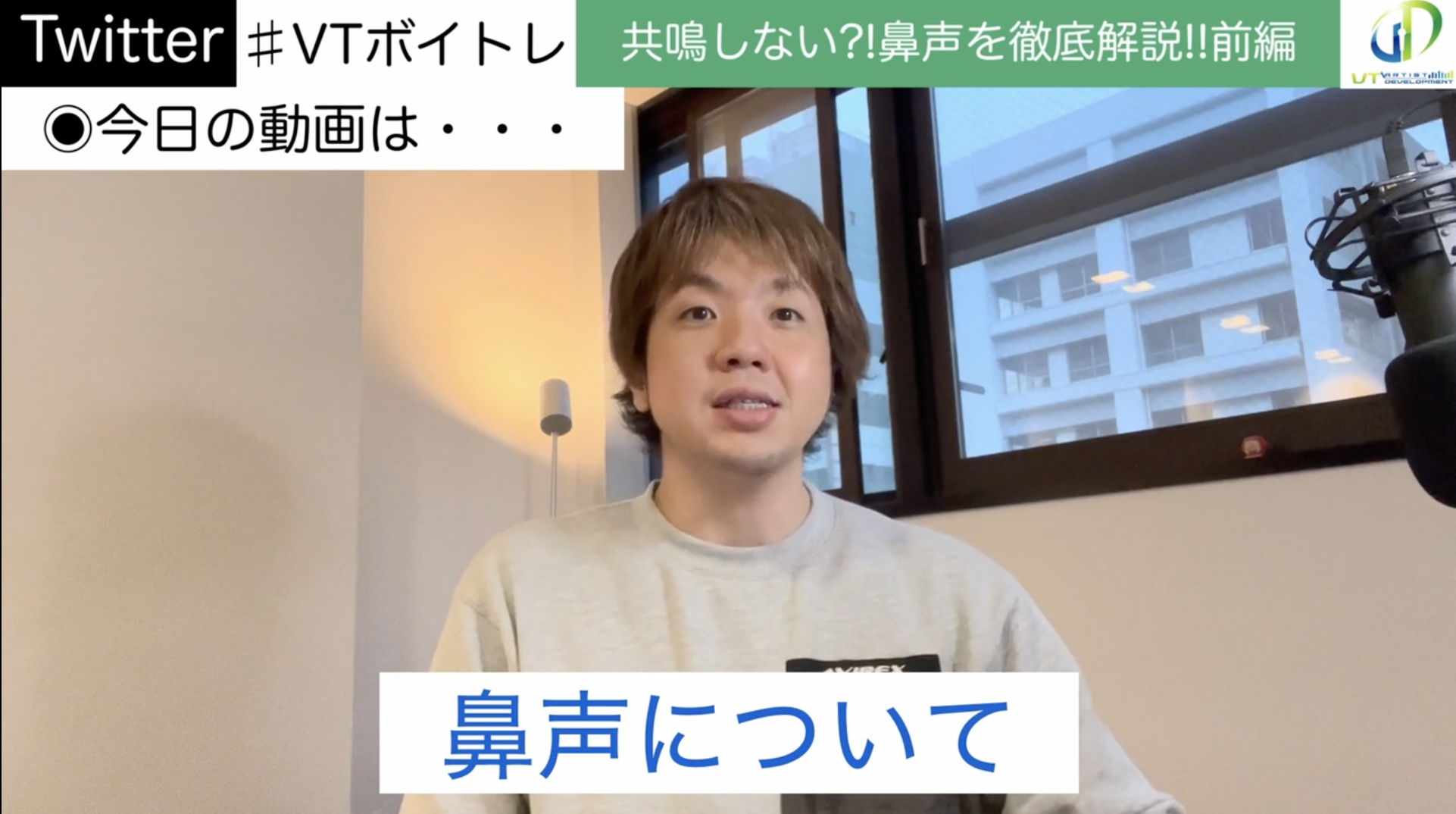- 2025.09.21
- マインドセット・練習法 ミックスボイス 加齢による声の変化 声の健康法 歌手のための音声学
女性の声の加齢変化(第3話)― 対策とハビリテーションの実践
はじめに:声を「元に戻す」から「新しい声を育てる」へ
加齢による女性の声の変化は避けられません。低音化や声質の暗化、音域の喪失は、どれだけボイストレーニングをしても完全に防ぐことは難しいと研究でも示されています。
しかし、それは「歌えなくなる」ことと同義ではありません。大切なのは、変化を受け入れながら今の声で歌い続けるための方法を見つけることです。これがボイス・ハビリテーションの核心です。
水分摂取と声帯粘膜のケア

加齢に伴い、声帯粘膜は若年期よりも乾燥しやすくなります。
潤滑性を失った声帯は振動効率が下がり、高音域の発声に大きな影響を与えます。
そのため、水分摂取は若い頃以上に重要なケアとなります。
Sivasankar & Fisher(2002)や Tanner ら(2010)の研究では、十分な水分摂取によって発声閾値圧(声が出るために必要な最低限の空気圧)が下がり、声帯振動が容易になることが確認されています。
実践的には「体重×30〜40ml」を目安に日常的な水分補給を行い、舞台やレッスン前には加湿やスチーム吸入(ネブライザーなどを使用)を組み合わせると効果的です。
フィットネストレーニングと全身の健康
声は呼吸と密接に結びついており、全身の筋力低下はそのまま発声能力の低下につながります。
加齢に伴う呼吸筋の衰えは、声の持久力や安定性を奪います。
有酸素運動や筋力トレーニングを習慣化することで呼吸筋を維持し、声の持久力を保つことができます。
Brown ら(2015)は高齢者の筋力維持が声のパフォーマンス改善に寄与することを報告しています。
さらに、筋力トレーニングはテストステロン分泌を促し、間接的に声の活力を維持する可能性もあります。
発声トレーニングの実践―レゾナント法とSOVT
加齢した声に必要なのは効率的な発声です。
無理に大きな声を出そうとするのではなく、最小限の負担で最大限の響きを得ることが重要です。
特に若年期は身体に多少負担をかけるような発声であってもフィジカルの力で乗り切れることが多いと思います。
それはそれで魅力的だと思いますが、若年期を終え、より成熟してきた歌唱はさらに技術を見直す事によって作られると考えます。
レゾナント・ボイストレーニングは、(ハリウッド式ボイストレーニングにも似たアイデアでのハビリテーション法は存在します)前方共鳴を意識した軽やかな発声を通じて、声帯への負担を減らしながら明瞭な響きを作ります。
また、SOVT(半閉鎖声道エクササイズ:ストロー発声やリップトリルなど)は声帯振動を効率化し、粘膜の健康を保ちながら安定した発声を促します。Titze(2006)や Guzmán ら(2013)は、SOVT が声帯接触パターンの改善に有効であることを示しました。
音域拡張トレーニング―声区の行き来を徹底する

加齢によって高音域が失われる一方で、発声トレーニングを通じて音域を拡張・維持することは可能です。
実際、多くの歌手が訓練によって音域を広げていきます。
音域拡張トレーニングの基本は、チェスト・ミックス・ヘッドボイスといった声区の行き来を徹底することです。
ボイストレーニングの際、ボイストレーナーと歌手のあるべきマインドセットは「音域を維持する」ではなく「以前よりも広いを音域を獲得する!」と言う強い気持ちが重要だと考えます。
これにより、音域の拡張と維持、さらにはピッチの安定が実現します。
若年期には「力で押し上げる」ように出していた高音も、加齢期には「声区をスムーズに移行させる」ことで再び実現できる場合があります。
瞬発性の低下とアジリティトレーニング
加齢による歌唱への影響として、瞬発性の低下が顕著に現れます。
速いリフやコロラトゥーラのような細かい音型が難しくなり、ビブラートも遅くなる傾向があります。
これに対しては、アジリティ系のトレーニング(半音階や分散和音の素早い反復、リズム変奏を加えたフレーズ練習など)が有効です。
瞬発性を作り直すことで、加齢による「もたつき」を軽減し、再び軽やかさのある歌唱を取り戻すことができます。
レパートリーとキー設定の再考
声の変化に最も影響を受けるのはレパートリー選択です。
若い頃に歌っていた楽曲をそのままのキーで歌い続けることは難しくなります。
しかし、これは新しい可能性を開くチャンスでもあります。キーを半音下げるだけで、現在の成熟した声と楽曲が合致し、若い頃には表現できなかった新しいニュアンスを生み出すことができます。
また、若年期に地声で歌っていた部分をミックスやファルセットに置き換えることで、音楽的な熱量を保ちながら無理のない歌唱が可能になります。
「声を元に戻す」のではなく、「今の声に合わせて楽曲を再解釈する」。この柔軟さが、加齢後のキャリアを支える大きな鍵となります。
ボイス・ハビリテーションの役割
ボイス・ハビリテーションは、医学的なリハビリテーションに近い考え方です。
リハビリテーションは声の機能回復を目的とし、ハビリテーションはそれを大きく超えた発生能力の習得を目的とします。
加齢で変化した声を「新しい楽器」として捉え、歌唱法や表現方法を再構築します。
桜田の現場でも、「高音が出にくい」と悩む女性歌手に対して、単に昔の声を取り戻すのではなく今の声でどう歌うかを提案することが増えています。具体的には、ミックスやファルセットを活用して表現を工夫し、さらにキーを半音だけ下げることで成熟した声と楽曲を結びつけ、若い頃には生まれなかった新しい表情を引き出すアプローチです。
心理的ケアと自己受容
声の変化は心理的な影響も大きく、「衰えた」と感じることがモチベーション低下につながります。
しかし、声の変化を成長の一部と捉え直すことができれば、歌手にとって大きな転機となります。
Kleemola ら(2010)の研究は、加齢声を持つ歌手が心理的サポートを受けることで活動継続率が高まることを示しました。ボイストレーナーや SLP は、単なる技術指導にとどまらず、心理的な支えとなることが求められます。
第3話のまとめ
女性の声は加齢によって変化しますが、その影響を緩和し、新しい表現を築くための方法は数多く存在します。
水分摂取で声帯粘膜を守り、フィットネスで呼吸筋を維持し、レゾナント発声や SOVT で効率的な声を作る。さらに、音域拡張やアジリティトレーニングで機能を保ち、キー設定や歌唱法を柔軟に調整する。
これらを組み合わせることで、声の変化を「衰退」ではなく進化として捉えることができます。
そして、ボイス・ハビリテーションは、その変化を新しい芸術的可能性へとつなげるための最も有効なアプローチなのです。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話