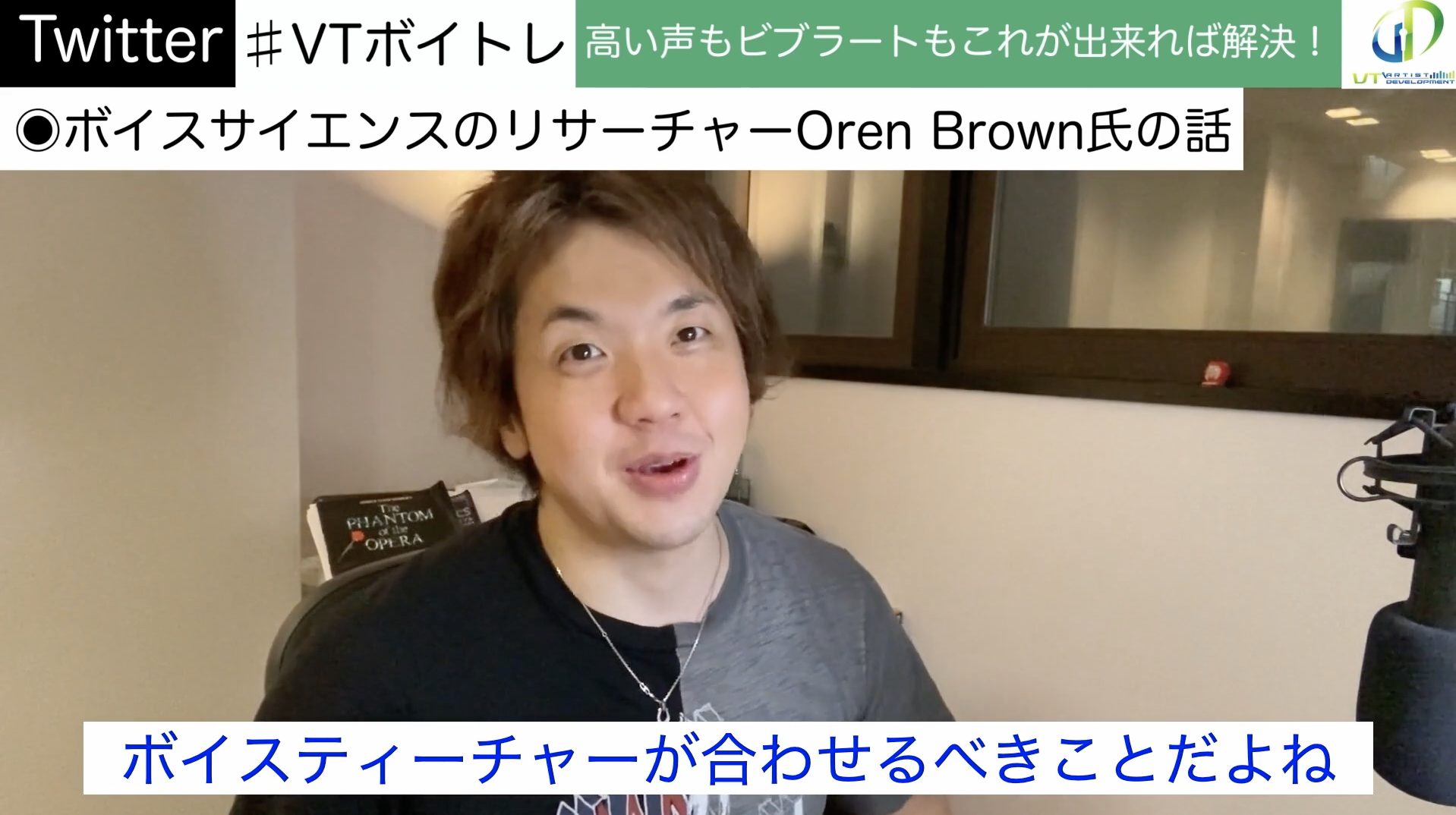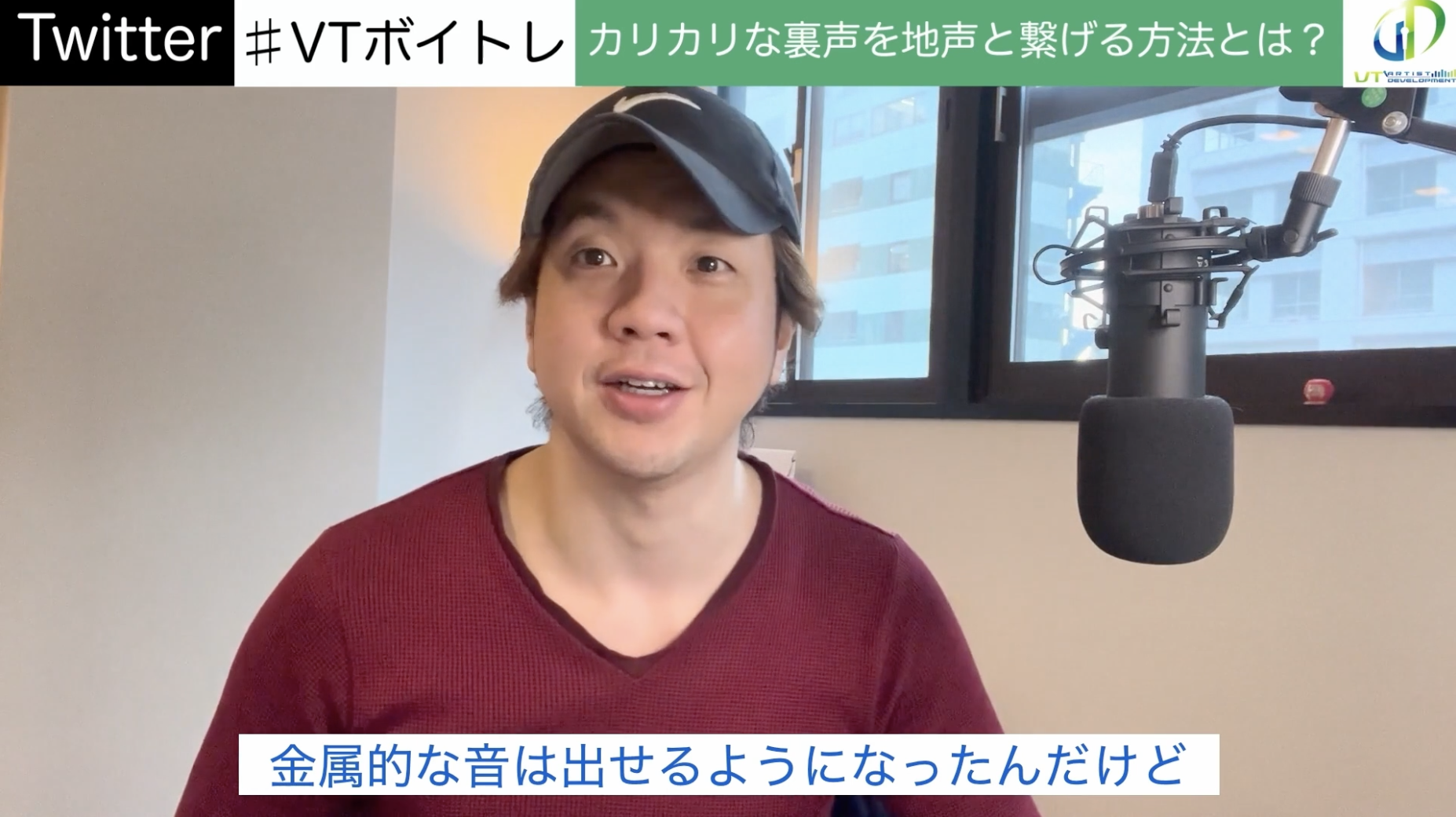- 2025.09.05
- ボイストレーナーのお仕事 ボイストレーナー育成 マインドセット・練習法
第1話:歌は運動学習である ― 基礎理論とフィードバック
歌の練習を語るとき、多くの現場では「音楽学習」という観点が中心になります。
音程・リズム・フレーズ解釈・スタイル。もちろんそれらは不可欠ですが、同時に歌は運動学習(motor learning)でもあるという視点が欠かせません。声を出すこと自体が「高度に微細な筋運動の習得」であり、音楽的な側面だけを追っても上達は頭打ちになります。
なぜなら「歌として出力したい声や想い」があっても声をコントロール出来ないと、音楽、歌というフォーマットに落とし込めないからです。以前は素晴らしい歌唱をしていたアーティストでも、発声障害と診断された後の声は、いわゆる歌が下手な人の歌唱になっている事があります。
運動学習とは何か
運動学習とは「反復経験を通じて運動スキルが獲得・保持・転移できるようになるプロセス」を指します(Schmidt & Lee, 2011)。スポーツ、楽器演奏、自転車に乗ること、すべてこの枠組みで説明できます。歌唱も例外ではなく、声帯や呼吸筋、共鳴腔をコントロールする一連の運動を習得していく行為です。
この分野で重要なモデルがSchmidtのスキーマ理論(1975, 2003)です。
ある運動を繰り返すと、脳内には「一般化された運動プログラム(GMP)」が形成されます。さらに、その動作を異なる条件で練習することで「スキーマ(運動規則)」が精緻化され、未知の状況でも適応できるようになります。
歌唱に当てはめると、同じフレーズを一定の強さで練習するだけでは応用力がつきません。楽曲を変える。異なる音楽スタイルを歌ってみる。スタジオで歌う。マイクを持って歌う。等です。
こうした多様な条件下での練習を積むことでスキーマが広がり、実際のステージや稽古で求められる多様な要求に対応できるのです。つまり、自分の歌声という普遍性を見いだし、その他の変化はノイズとして処理できるようになっていきます。
桜田はよくピアニストを例に出します。プロのピアニストはほぼ毎日、違うピアノを弾きます。
自分のピアノを現場に持ち込むことはほとんどできないからです。演奏経験の浅い頃は「自分のピアノじゃないと同じ演奏ができない!」と困ることもあります。
しかし様々なピアノで演奏する経験を積むうちに、「ピアノという楽器の普遍性」を見いだすようになります。そして、鍵盤の重さや返り、音色や響きといった微妙な差はノイズとして処理し、むしろその場その場のピアノに合わせた演奏ができるようになるのです。
歌においても同じで、環境や伴奏、体調などの変化をノイズとして扱いながら、自分の声の普遍性を保つことが可能になります。
記憶システムと歌唱
心理学的に、記憶は大きく二つに分けられます。それが宣言的記憶と手続き的記憶です。歌唱を理解するには、この二つの違いを明確に押さえておく必要があります。
・宣言的記憶(言語化できる知識)
宣言的記憶とは、言葉にして説明できる知識のことです。
たとえば「日本の首都は東京である」「Cメジャーの構成音はC・E・Gである」といった知識は宣言的記憶に含まれます。歌唱においても「喉を下げると響きが暗くなる」「息を多めに流すと声が軽くなる」などの説明は宣言的記憶として理解することが可能です。
学習者はレッスンで説明を受けると「なるほど、そういう仕組みか」と理解できます。しかし、理解できたからといって、その場ですぐに体現できるわけではありません。宣言的記憶はあくまで「頭で知っていること」にすぎず、それ自体が技能の獲得には直結しません。
・手続き的記憶(言語化できない技能)
一方で、手続き的記憶とは「身体で覚えてしまったこと」で、言葉にしにくい記憶のことです。
自転車の乗り方や水泳の動作、楽器のフィンガリングなどは一度身につけば、しばらく練習をしていなくても身体が自然に再現してくれます。これが手続き的記憶です。
歌唱もまさにこの領域に属します。発声の仕組みや理論を説明することはできても、実際に声を思い通りにコントロールできるようになるには、繰り返しの練習を通じて手続き的記憶に変換される必要があります。高度な歌唱ほど無意識的に声が出る状態、つまり手続き的記憶として技能が定着している状態が求められます。
・歌唱における両者の関係
宣言的記憶と手続き的記憶は段階的に移行する関係にあります。
学習者はまず宣言的記憶として「知識」を理解し、それを練習によって身体化することで手続き的記憶に変えていきます。レッスンで「理解はしているのに歌になるとできない」という状況が起こるのは、まさにこの移行過程にある証拠です。
桜田はこの点を踏まえ、レッスンでの説明をあえて最小限に抑え、生徒自身が試行錯誤を通じて身体で感覚をつかむ時間を大切にしています。知識を与えることは重要ですが、それを技能へと転換させるためには、繰り返しの練習と時間が不可欠なのです。
フィードバックの種類 ― KRとKP
運動学習で特に重要なのがフィードバックです。ここでいうフィードバックには2種類があります。
・KR (Knowledge of Results):結果に関する情報
例:「今の音程は20セント高かった(1/5半のズレ)」「その声は割れて声に雑音が混ざった」
・KP (Knowledge of Performance):動作に関する情報
例:「もっと声門閉鎖を作って」「下顎が動きすぎている」
現場ではKPが多用されがちですが、研究は注意を促しています。Salmoni, Schmidt & Walter (1984) のレビューやSteinhauer & Grayhack (2000) の音声課題実験では、フィードバックを毎回細かく与えるほど保持が下がることが示されています。
逆に、KRを中心にして数回分まとめて与える(サマリ・フィードバック)方が、学習者は自分で修正を試みる時間が増え、長期的に技能が残りやすいのです。
歌唱レッスンでは「今の発声はどう響いて聞こえた?」とまず本人に評価させ、その後に必要最小限のKRを提示する方が、定着率は高くなります。
桜田の現場エピソード
桜田のスタジオでも、ある生徒が「エクササイズで正しい発声は分かるけど、歌になるとできない」と悩んでいました。そこで練習の設計を見直し、フィードバックを控えめにして自分で試行錯誤する時間を増やしました。
例えば「歌詞をNAY(ネイ)に変えて歌ってごらん。その明るい響きを活かして」とだけ伝え、歌詞内での響きの調整など、細かい指示はあえて控えました。
すると数週間後には、桜田が説明しなくても自然にバランスの良い発声を選べるようになっていました。これは「理解」と「技能」が結びつき、手続き的記憶として定着した証拠といえます。
まとめ
歌の練習を運動学習の観点から捉えると、これまでの「感覚的な指導」を科学的に説明し、改善する道が開けます。スキーマ理論・記憶システム・フィードバックの使い方は、その第一歩です。
次回(第2話)では、練習構造(ブロック練習 vs ランダム練習)や外的フォーカスの理論に踏み込み、より効率的な歌唱スキルの定着方法を探っていきます。
歌手の運動学習シリーズ
第1話:歌手の学習方法を学ぼう!― 基礎理論とフィードバック
第2話:練習とフォーカスの科学 ― 効率的なスキル定着
第3話:失敗を味方につける歌の練習・ボイストレーニング
第4話:モチベーションと学習環境 ― 歌唱を続ける力を育てる
第5話:練習時間の設計と集中力 ― 効果的に声を育てる
第6話:自動化とフロー状態 ― 歌唱におけるゾーン体験
第7話:自分の歌をどう確認する?ーフィードバック環境の設計
第8話:模倣学習と観察学習 ― ボイストレーニングにおけるモデルの力
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!
ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?