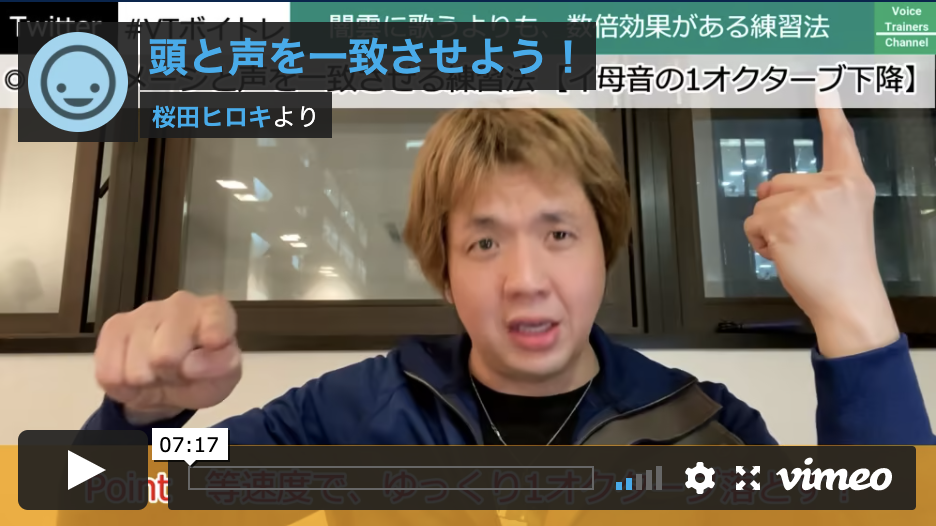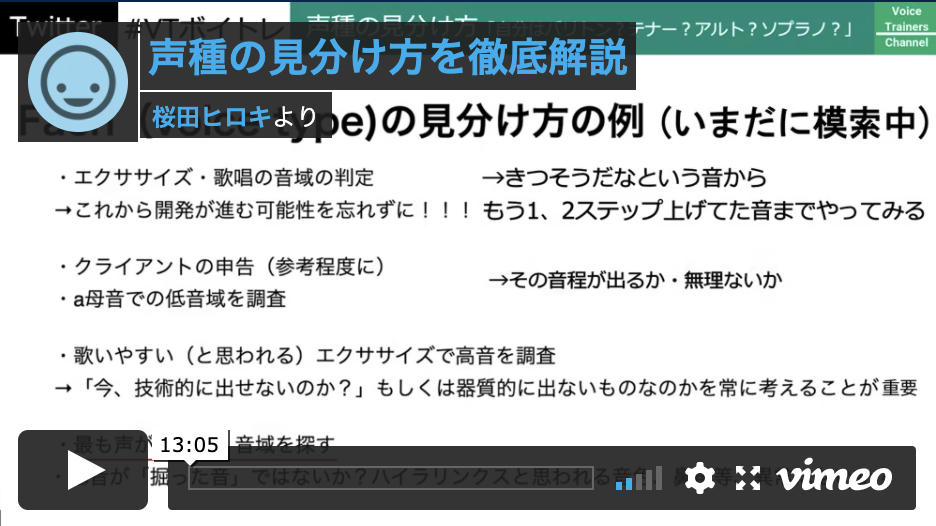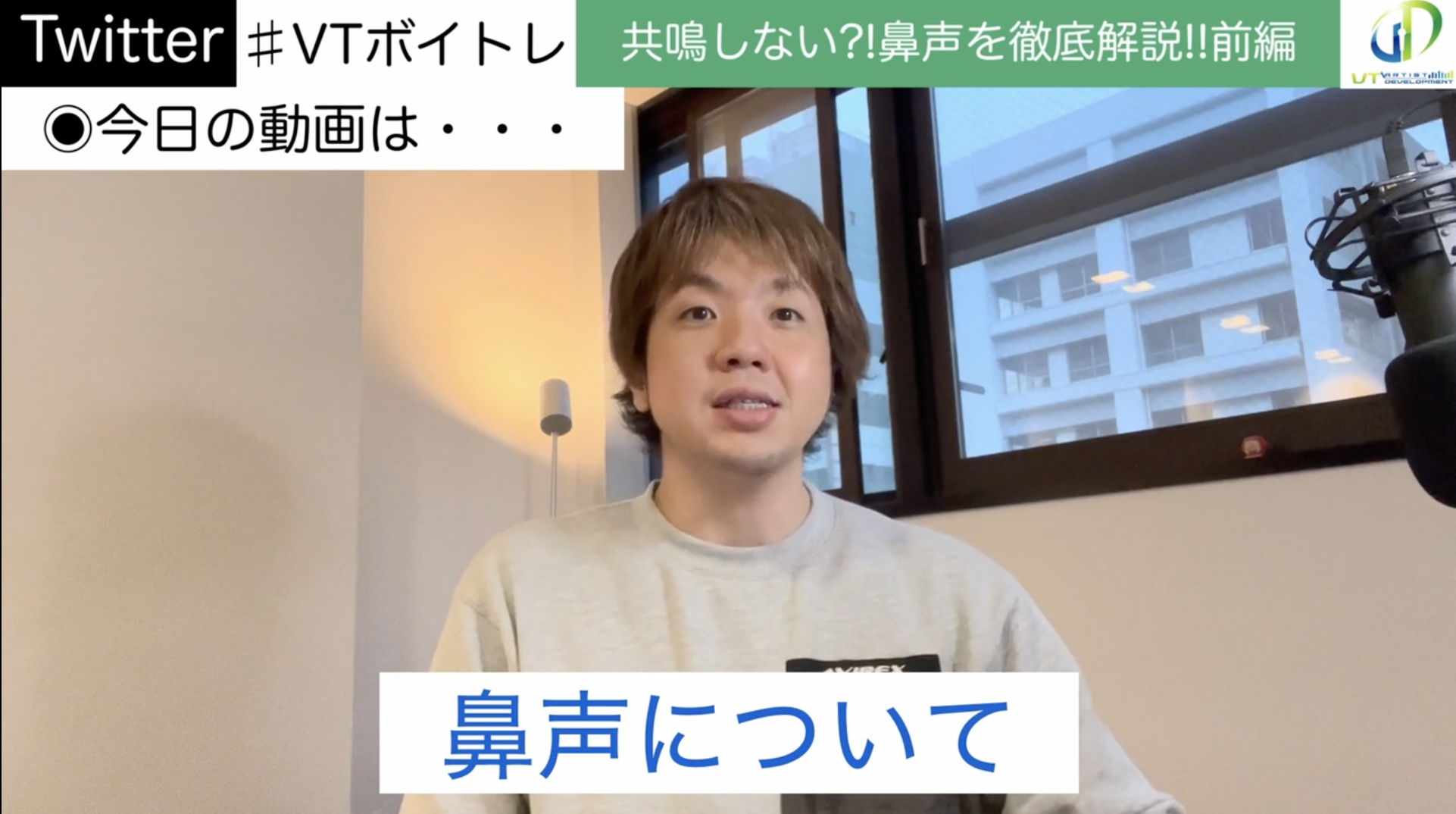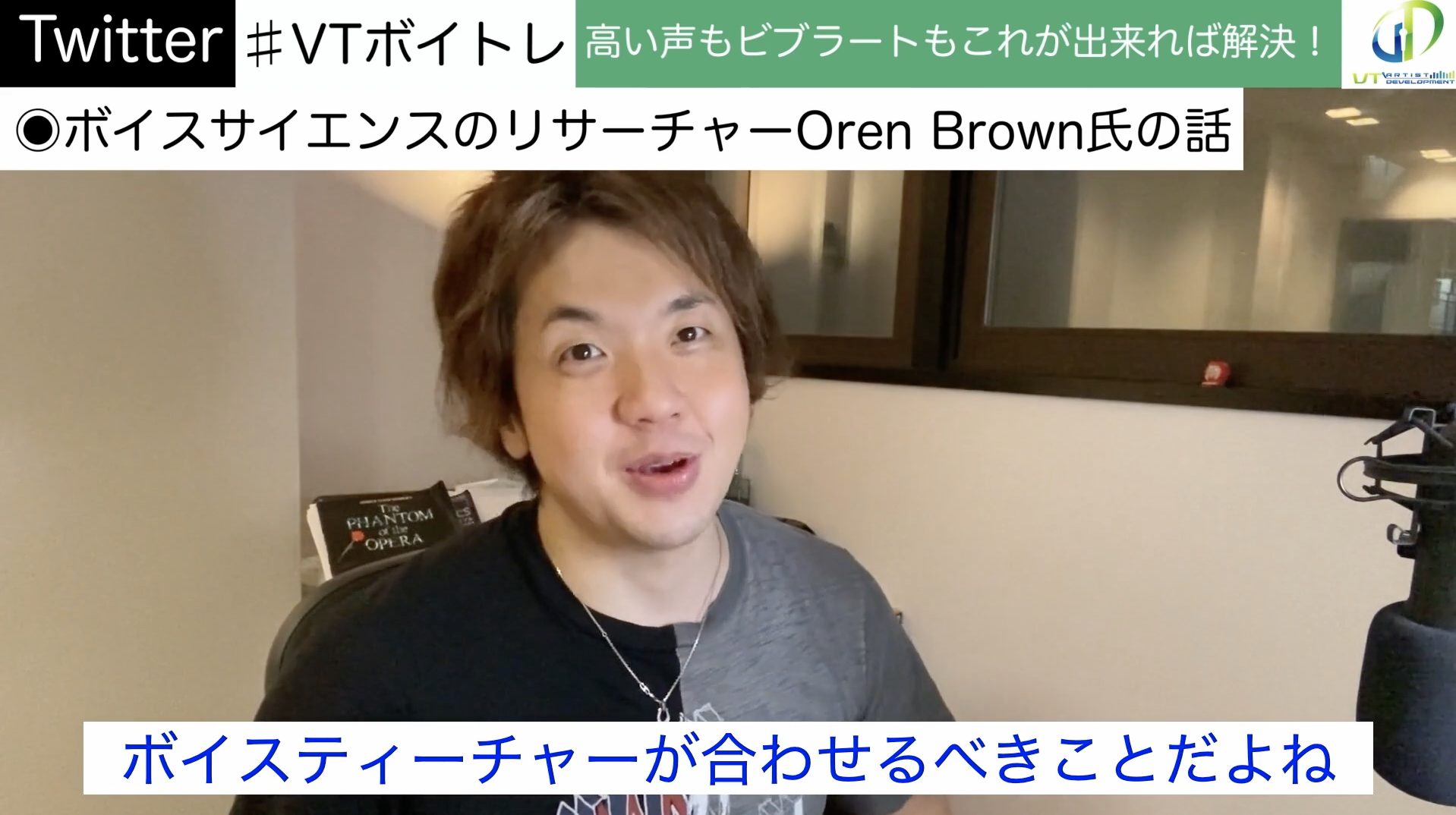アーティストは非常に過酷な環境で歌唱を要求されています。
特に売れている時期や、売り出し時期には、一般の仕事に例えるなら「ブラック企業に勤めている状況で歌うことを求められる」ようなものです。
休息が不十分なままステージが続き、さらにメディア露出や移動も重なることで、声は常に限界ギリギリに追い込まれます。
今回は3編に渡って、アメリカで実際に発声障害に陥ったアーティストの診断からリカバリーまでを追ってみようと思います。

ロックバンドのメインボーカル
・全国ツアー中、連日90〜120分のステージ
・サウンドチェック、移動、インタビューで休息不足
・インイヤーモニターの返りが不十分で、つい声を張ってしまう
このような状況は、ツアーでは珍しいことではありません。限られたリハーサル時間や会場ごとの音響の違いが積み重なり、どうしても負担が増してしまうのです。
発症経緯
・初週のステージから声枯れが出始める
・高音部を無理に押し出すような発声が増える
・苦しい発声を繰り返すうちに「代償的な発声」が固定化
・声が出にくい → さらに力む → さらに悪化、という悪循環に陥る
一度「力で何とかする」発声に頼ると、その感覚が身体に染みつき、知らないうちに毎回の歌唱で同じ使い方を繰り返してしまいます。
診察所見
・喉頭の前後方向の圧縮(AP圧縮)が顕著
・歌唱時に仮声帯が接近し、喉頭内部が内側に圧迫されていると考えられる
・話し声はある程度保たれるが、歌唱時に崩れる
・典型的な「一次性の過緊張性発声障害(MTD)」のパターン
このように、日常会話では大きな問題が見えにくくても、歌唱特有の負荷がかかると異常が明らかになるのが歌手の発声障害の特徴です。
代償的な発声とは
声帯や声の仕組みが疲労や不調に陥ったとき、喉や首の筋肉を使って無理に声を出そうとする発声です。
・一時的には声が出る
・しかし効率は低く、長期的にはさらに悪化する
・結果的に「声を守ろうとした努力」が逆に障害を固定化する
歌手の場合、ツアーの途中で発症し、それでも本番を重ねざるを得ない状況では、この代償発声が日ごとに深く根付いてしまいます。
休むことができず、同じ代償を繰り返すためです。
第1話はここまでです。
次回(第2話)では、この歌手に実際に行われた治療とトレーニング方法を詳しく紹介します。
ツアー中に発声障害に罹患したロック歌手のケース(第2話)
ツアー中に発声障害に罹患した歌手のリカバリー法は?(第3話)
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話