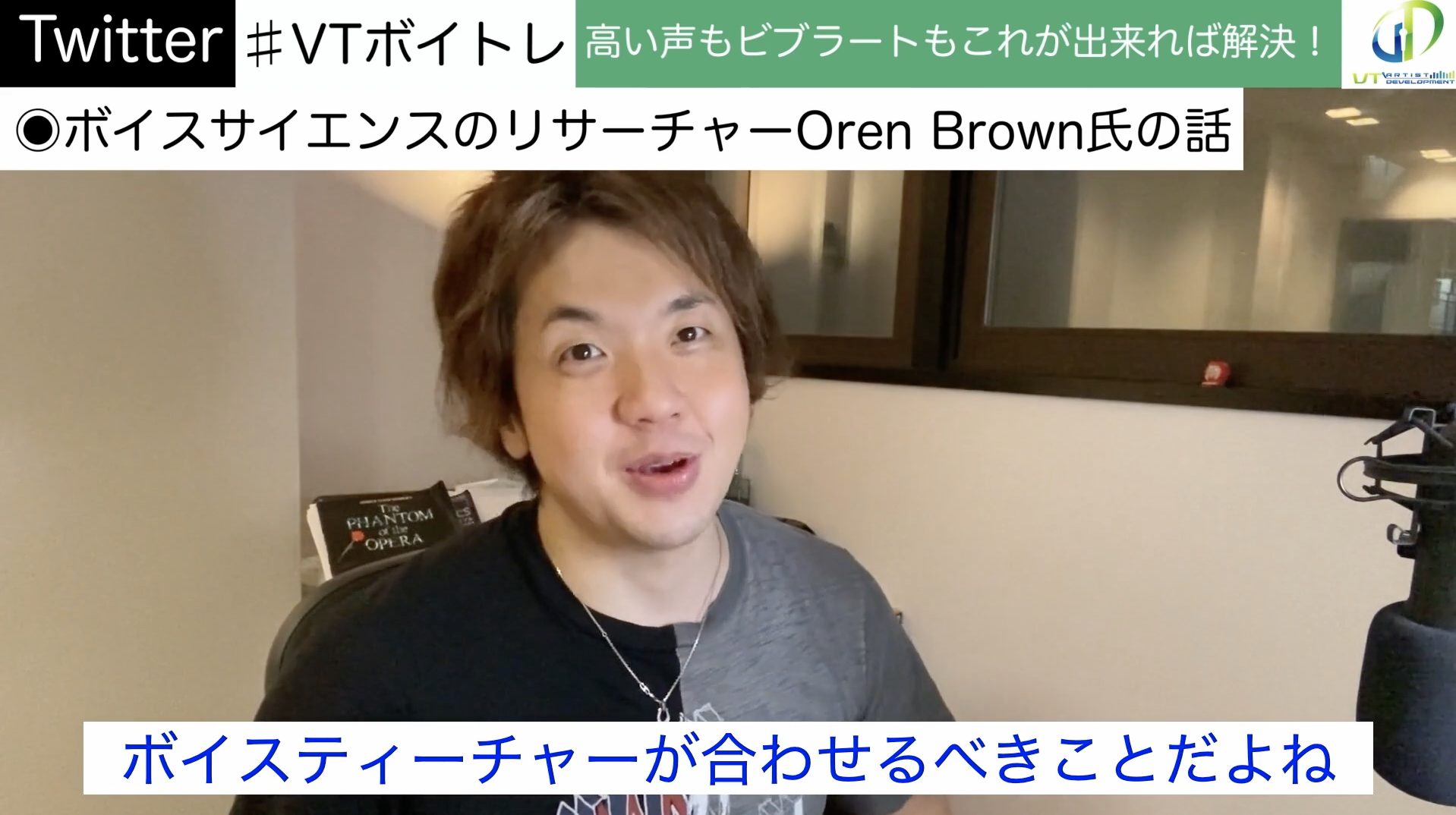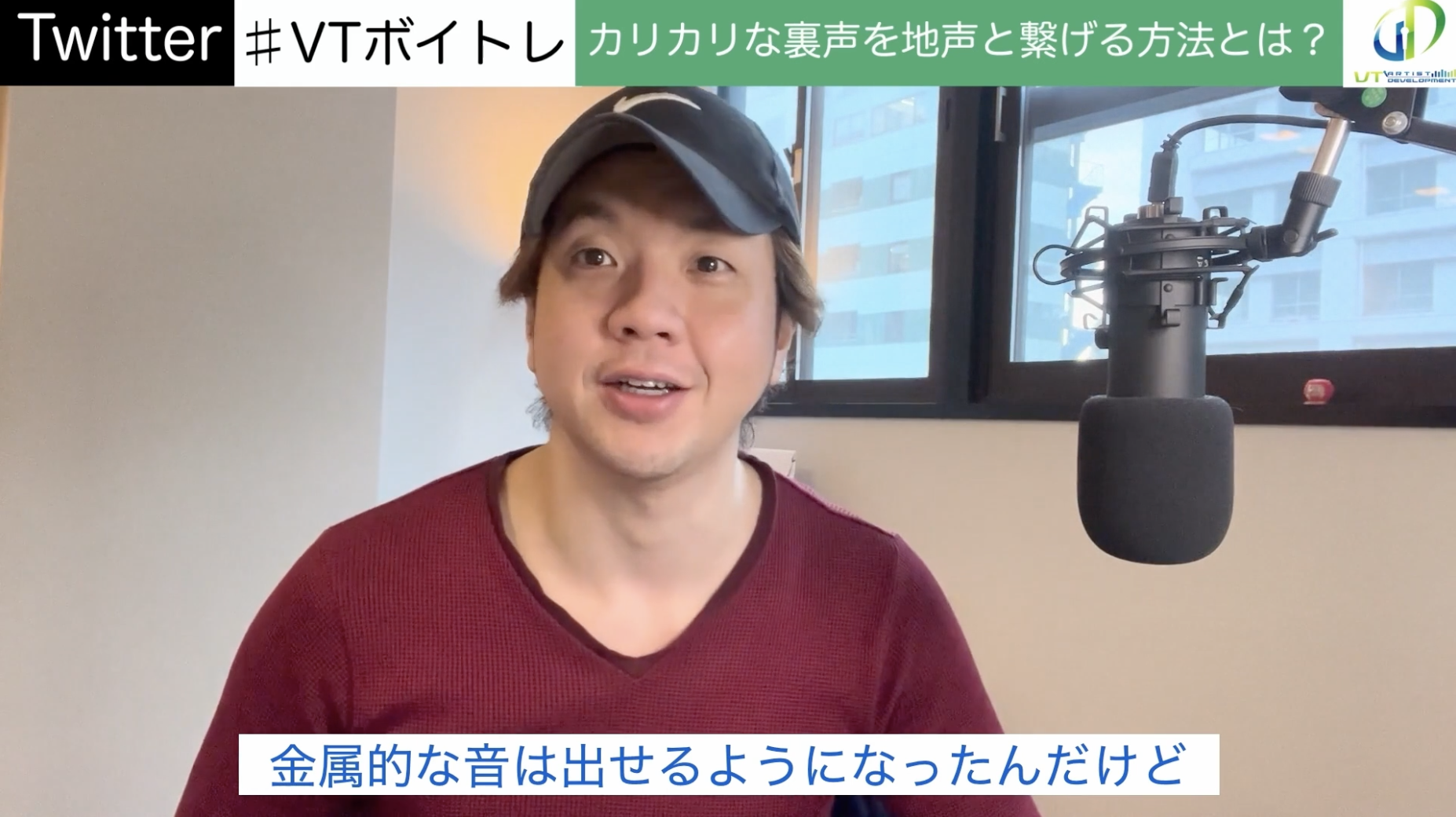第7話:機能性発声障害における統合的アプローチ
歌手や声優の発声障害をサポートしていると、しばしば痛感するのは「一人の専門家だけでは十分に対応できない」という現実です。器質的な異常がないケース、検査では「異常なし」と診断されるケース、そして歌唱でのみ深刻な支障が現れるケース——これらは機能性発声障害と呼ばれ、日本でも診断名として一般的に用いられています。
しかし、この診断名だけで治療や支援の方向性が明確になるわけではありません。むしろ問題はここから始まります。歌手にとって求められる声のレベルは、日常会話を超える非常に高度なものだからです。本稿では、機能性発声障害に対して有効とされる統合的アプローチについて整理し、医師・言語聴覚士(SLP)・ボイストレーナーの役割を比較しながら考えていきます。
1. なぜ統合的アプローチが必要か

機能性発声障害の厄介さは、診断や評価の曖昧さにあります。器質的疾患(声帯結節やポリープなど)であれば診断名がつきやすく、治療方針も比較的明確です。ところが機能性発声障害は、ストロボスコピーでも決定的な異常所見が見つかりにくく、診断は「グレーゾーン」になりやすい。
実際、Royら(2005)は成人の約30%が一生に一度は声の障害を経験すると報告しており、その多くが機能性の問題と考えられています。また、Van Houtteら(2011)は「声の障害の診断と治療は多職種チームの協力が望ましい」と強調しています。
この背景を踏まえると、医師だけでなくSLPやボイストレーナーを含めたチーム体制で取り組むことが合理的だと理解できます。
2. 医師の役割
医師の最も重要な役割は、まず器質的疾患を除外することです。声帯結節、ポリープ、痙攣性発声障害、反回神経麻痺など、臨床的に明確な病変を確認する作業は医師にしかできません。
加えて、診断名をつけることによって保険適用の治療やSLPによるリハビリを導入する根拠を与えます。例えば、Koufman & Isaacson(1991)は、声帯病変の診断と胃酸逆流症の関係を明らかにし、医師の評価が治療全体の起点になることを示しています。
しかし課題もあります。多くの臨床現場では、検査が「いー、あー」といった短い発声や、特定のタスクでの空気力学検査、特定のタスクでの音響解析に限定されます。
歌唱特有のダイナミクスや母音・子音の組み合わせは評価されにくいのです。
これが「歌唱でだけ問題が出る」歌手にとって大きな壁になります。
3. SLP(言語聴覚士)の役割
医師の診断を踏まえて、SLPは発声リハビリテーションを行います。発声効率を改善し、誤った発声パターンを修正することが目的です。
Ramig & Verdolini(1998)は、SLPによる音声リハビリの有効性をまとめており、特に会話レベルでの声の改善においては十分なエビデンスがあります。日本でも臨床の現場でSLPによる介入が進んでおり、発声障害の患者にとっては重要な支援となっています。
ただし、多くの場合リハビリのゴールは「日常会話で困らないこと」に設定されます。これは一般の患者にとっては十分ですが、歌手にとっては「ステージで観客に届く声を出す」ことが目標であり、ここにギャップが生じます。
4. ボイストレーナーの役割
ボイストレーナーは、医師やSLPではカバーしきれない「歌唱という高難度タスク」を担当します。リハビリで基礎的な声が回復しても、実際の歌唱では声区移行、音色操作、強弱表現といった高度な要素が求められます。
Sataloff(2005)は、声楽家の治療においてボイストレーナーの協力は不可欠だと指摘しています。これは、ハビリテーション(habilitation)という概念に近く、単に「元に戻す」だけでなく「芸術的要求に応えられる声をつくる」作業です。
実際の現場では、SLPのリハビリで「声が出る」状態まで回復した後に、ボイストレーナーが「歌える」状態へ導く二段階が必要になることが多いのです。
もちろん、ボイストレーナーにも課題があります。多くのボイストレーナーは自身のトレーニングの経験であったり、自身が知覚出来る事に限定して教える方がほとんどです。
恐らく日本の90%以上のボイストレーナーは臨床経験はなく、発声障害や運動学、音声科学については知識も経験もありません。
ここが桜田個人的にはボイストレーナーの大きな大きな問題と考えています。
5. リハビリテーションとハビリテーション

ここで重要なのがリハビリテーションとハビリテーションの違いです。
– リハビリテーション:基本的な声の使用(会話など)に耐えられる発声を回復させる。
– ハビリテーション:基本的な使用を超えた高難度の声の使用(歌唱・舞台)を可能にする。
歌唱はそもそも「基本的使用」を大きく超えるタスクです。したがって、歌手のサポートには両方の視点が不可欠であり、さらにオーバーラップする領域も多い。
このため、医師・SLP・ボイストレーナーが連携して声を支える体制を整えることが今後の課題となります。
6. チーム医療の実例
海外ではすでに統合的な取り組みが行われています。
– ASHA(米国言語聴覚協会)は、音声障害治療において多職種チームの重要性を強調しています。
– 英国のVoice Care Centreでは、SLP・ボイストレーナー・マッサージセラピストがチームを組み、歌手を包括的に支援しています。
– 日本でも「ボイスクリニックとボイストレーナーの連携」が少しずつ始まっていますが、まだ一般化していません。
私自身もクライアントのケースで、医師に所見を共有した上でSLPとトレーニング計画を組むことがあります。歌手本人が「自分の声を回復させるチームのリーダー」として動くことで、治療とハビリテーションがうまく結びついた例も少なくありません。
7. 今後の課題と展望
日本の現状では、「機能性発声障害」と診断されても、その先の「歌唱レベルの回復」までを視野に入れた体系はまだ整っていません。
課題は大きく3つあります。
1. 医師・SLPが歌唱の要求水準を理解しにくい。
2. ボイストレーナーが医学的知識を持たない場合、連携が難しい。
3. 教育カリキュラムの中に、統合的な枠組みが十分組み込まれていない。
しかし逆に言えば、ここは大きな成長余地でもあります。今後は、ボイストレーナー自身が声科学やリハビリの知見を学び、医師・SLPと対等に意見交換できるようになることが望まれます。そして何より、歌手本人が「自分の声を守るチームの中心人物」になり、必要な専門家を巻き込む主体性を持つことが大切です。
まとめ
– 機能性発声障害は一人の専門家では対応が難しい。
– 医師が診断、SLPがリハビリ、ボイストレーナーがハビリテーションを担う。
– 歌手自身が「声を守るチームのリーダー」になることが求められる。
– 今後は、連携モデルの整備と教育カリキュラムの発展が大きな課題である。
歌手の声を守るためには、もはや単独の専門家に頼る時代ではありません。医療・リハビリ・ハビリテーションを架橋する統合的アプローチこそが、これからの標準になっていくはずです。
歌手に多い「機能性発声障害(筋緊張性発声障害)」とは?
ボーカルマッサージについてはこちら
サーカム・ラリンジャル― 声を不自由解放するための科学と実践
変声期を迎えた少年歌手の発声障害の例
ツアー中に発声障害に罹患したロック歌手のケース(第1話)
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話