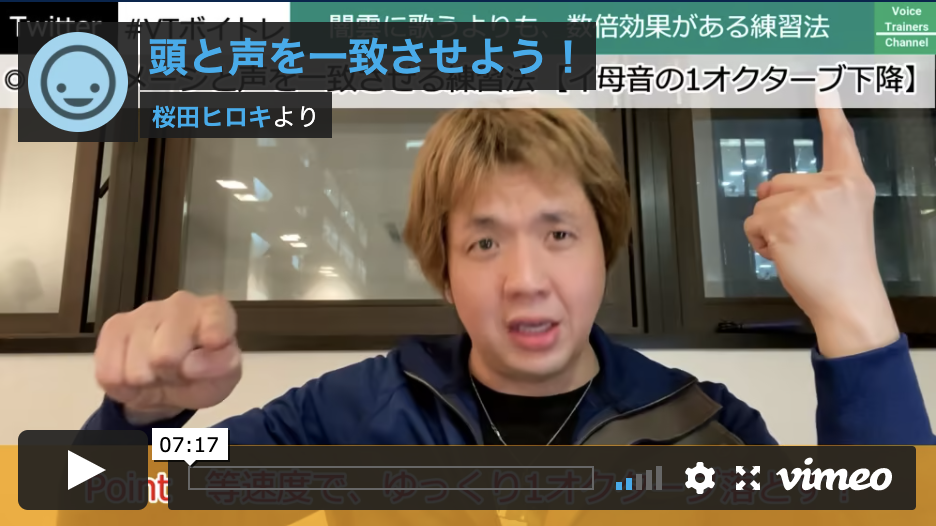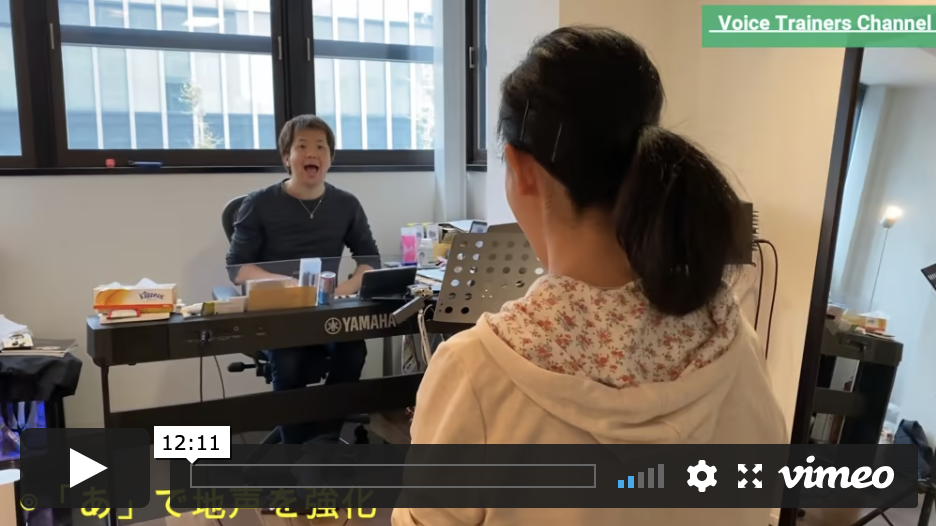- 2025.09.23
- ボイストレーナー育成 ミックスボイス 喉頭の機能 歌手のための音声学
はじめに:違和感から始まった調査
先日、アメリカ人の先輩ボイストレーナーが開催するワークショップに出席した際、あ母音は甲状披裂筋(TA)を活性化というワードを耳にしました。
近年、自分が学んでいる発声科学やボイストレーニングの知見を踏まえると、この一言には少し違和感がありました。
本当に母音だけで特定の筋肉が活性化するのか?という疑問から、いくつかの研究を調べてみたところ、興味深い事実がいくつも見えてきました。
ハリウッド式ボイストレーニングでは、強母音(あ母音など)を胸声強化、弱母音(い・う母音)を頭声強化に用いる手法が広く使われています。
本当に科学的にもそれは正しい方法なのでしょうか?
これを科学がどこまで裏付けているのかを見ていきます。

音圧レベル(SPL)とTA活動に関する研究
•Hirose & Gay (1972, JASA)
音圧レベル(SPL)を約70dBから90dBに上げると、TAの放電レベルは平均で約1.6倍に増加したと報告。著者らは音圧レベル(SPL)上昇に伴う声門閉鎖強化にはTAの寄与が不可欠と結論付け。
•Schneider & Shipp (1982)
犬と人間を用いた比較実験で、音圧レベル(SPL)を10dB上昇させるとTA活動は有意に増加し、CTは変化が小さいと報告。
•Titze (2000, Principles of Voice Production)
声帯を厚く短く保ち、声門閉鎖を強めることが、音圧レベル(SPL)を上げる主要なメカニズムであると明記。
つまりどの研究も特定の母音について論じているわけではなく「声量を大きくすると甲状披裂筋(TA)の活動が活発になる」ということです。
余談ですが、ここで課題になるのが、声帯を厚く短く保つことは、高音域で必要とされる声帯を薄く伸展させる動きと相反する点です。
高い声で強い声を出そうとすると、ピッチが下がりやすくなる歌手が非常に多いという現象は、この矛盾を反映していると言えます。
ベルティングでの最大の課題は、声帯の伸展を著しく邪魔することなく声門閉鎖を高めることです。
どこまでそれが可能なのかは、個々の歌手が持つ器質的な要素(声帯の構造や筋肉の使い方)に起因すると考えられます。
これらはいずれも母音そのものを変えた研究ではありません。
母音を固定し、発声強度だけを変えた条件でした。しかし、音圧レベル(SPL)を上げるとTA活動が増えるという事実は確かであり、ここから強母音を用いて音圧レベル(SPL)を上げ、その結果TAを高めるというハリウッド式ボイストレーニングの経験則に理論的根拠を与えます。
強母音の役割:共鳴と音圧レベル(SPL)からの解釈

強母音(/a/など)は、口腔を大きく開けることで共鳴効率が高く、同じ声の高さでも音圧レベル(SPL)を効率的に得ることができます。
母音を操作して音圧レベル(SPL)を引き上げることは、間接的にTAの活動を増やし、胸声的な響きを強化することにつながる可能性があります。
ハリウッド式ボイストレーナーが強母音で胸声強化というアプローチを重視してきた背景には、この連鎖(母音→共鳴→音圧レベル(SPL)→TA活動)があると考えられます。
弱母音とCT活動に関する研究
•Whalen et al. (2011)
英語話者4名を対象に、/i/, /e/, /a/を発話させCTのEMGを測定。
高母音 /i/ では、他の母音より平均12%高いCT放電を示した被験者が2名いた一方、残り2名では差が小さいか逆の傾向を示した。著者らは母音によるCT活動差は被験者依存性が大きいと結論。
•Hoole (1998, 2003)
ドイツ語母音の解析で高母音はCT活動の立ち上がりが速く、活動レベルもやや高いことを報告。
これらの研究は、高母音がCTを相対的に働かせやすいことを示唆しますが、著者らはCT活動は母音そのものではなく、基本周波数(F0:歌う高さ)と音圧レベル(SPL)に強く影響されると注意を付けています。
つまり、弱母音が必ずしも頭声を強化するという直接的なエビデンスはまだ弱いといえます。
母音と筋活動に関するエビデンスの限界
Whalenらのデータでも、同じ被験者が別のセッションでは異なる傾向を示すなど、CT活動のパターンにはばらつきがありました。
犬モデルやTitzeらの計算モデルでは、母音を変えることで声道共鳴が変わり、同じF0・音圧レベル(SPL)を維持するために必要なTA/CT比が変動することが示唆されています。
これらは母音が筋活動を直接決定する証拠ではなく、間接的な影響にとどまります。
母音を用いた強声・弱声のボイストレーニングは合理的な仮説ではありますが、科学的事実として断定するにはデータが不足しています。
実践的意義と今後の課題
ハリウッド式ボイストレーニングが長年培ってきた「強母音で胸声」「弱母音で頭声」という手法は、経験的には多くのシンガーに有効です。
音圧レベル(SPL)とTA活動の相関、CTと高母音の関係といった既存の知見と現場の効果が一致しているため、合理的な仮説として大きな価値があります。
ただし、この手法を絶対的な法則として扱うべきではないと考えます。
今後は、F0と音圧レベル(SPL)を厳密に統制し、母音間でのTA/CT活動を直接比較するEMG研究が必要です。
ボイストレーナーやSLPは、母音、声の高さ、音圧、共鳴、歌唱スタイルなど複数の要素を総合的に評価し、柔軟にアプローチすることが求められます。
まとめ
ハリウッド式ボイストレーニングの母音の使い分けは、現場での実践知と生理学的理論の両面から支持されている魅力的なアプローチです。
音圧レベル(SPL)が高くなるとTAが活性化するという具体的なデータ(Hirose & Gay 1972、Schneider & Shipp 1982)を踏まえると、強母音を用いて胸声を鍛える方法は理にかなっています。
一方で、弱母音が必ずしもCTを活発化させて頭声を強化するという主張には、現時点で十分な裏付けがありません。
このように、なんの疑いもなく自分のボイストレーニングや教え方で行っている事でも、疑問を持ちながら研究をしていく事が歌手としてもボイストレーナーとしても成長を続けさせてくれると考えます。
今後の研究が、ボイストレーニングの実践をさらに確かなものにし、ハリウッド式の方法論を強化していくでしょう。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト
ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!
ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!