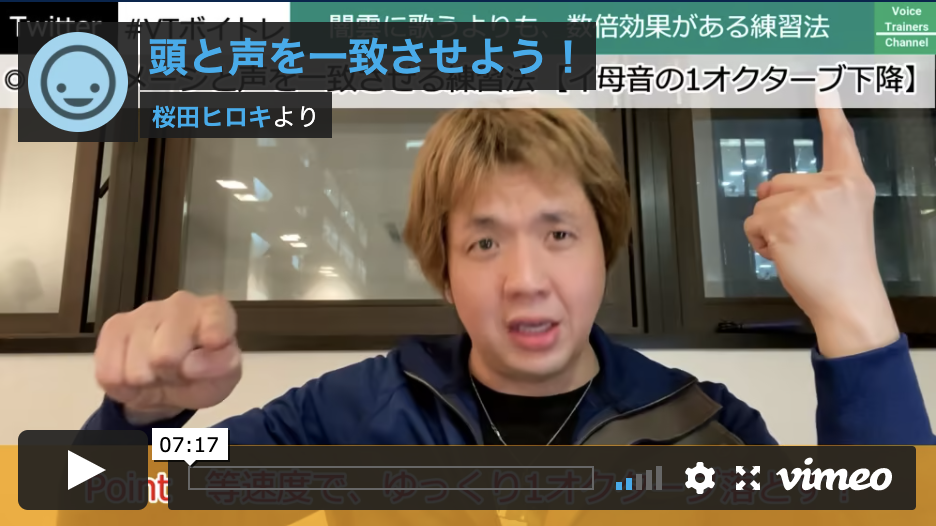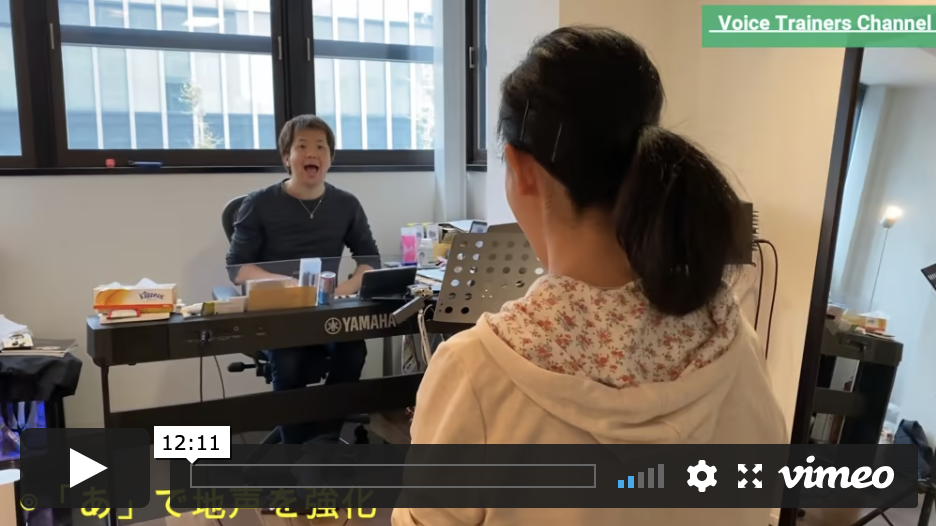女性の声の加齢変化(第1話)― 低音化とその原因
はじめに:男性と女性の対照的な変化
声は年齢を最も顕著に映しだします。
男性は高齢になると声がやや高くなるのに対し、女性は反対に声が低くなる傾向を示します。
特に女性の声の変化は、歌手にとって致命的な問題となることがあります。
なぜなら、女性歌手の多くは広い音域を求められ、その中でも高音域はキャリアを左右するほど重要だからです。加齢による低音化と高音域喪失は、ただの「声の老化」ではなく、芸術表現や職業生命に直結する深刻なテーマなのです。
こうした問題に直面したときに、多くのアーティストが頼るのが専門的なボイストレーニングです。ボイストレーニングは単なる技術習得にとどまらず、加齢による変化を理解し、声を使い続けるための「再設計」のプロセスでもあるのです。

女性の声はなぜ低音化するのか
加齢に伴う声の変化の中で、女性に最も顕著に見られるのが声の低音化です。
複数の研究で、女性は加齢とともにF0(基音周波数/ピッチ)が下がることが確認されています。Vorperianら(2018)は、広範な年齢層を対象とした研究で、女性のF0が加齢に伴って有意に低下することを報告しました。
この低音化は、男性と女性で影響の大きさが異なります。男性はそもそも加齢による低音化のリスクが低く、声種を大きく変える必要はほとんどありません。
一方で女性は、加齢とともに低音化が顕著に起こりやすく、その結果として高音域を保てず、キー変更を余儀なくされることが多いのです。
そのため、ボイストレーニングやボイス・ハビリテーションを通じて、なるべく声種を変えずに歌唱を続けられるようにすることが重要な目標となります。
更年期とホルモン変化の影響
女性の声の低音化を語るうえで欠かせないのが更年期に伴うホルモン変化です。
エストロゲンの低下は、声帯粘膜の潤滑性を失わせ、乾燥や浮腫、硬化を引き起こします。その結果、声帯の柔軟性が損なわれ、振動効率が低下します。これが高音域の喪失や声質の変化に直結するのです。
Abitbolら(1999)は、更年期後の女性歌手において声帯の形態学的変化(浮腫や厚みの増加)を観察し、高音域の喪失と関連していることを報告しました。またBoulet & Oddens(1996)は、ホルモン補充療法を受けた女性で高音域が部分的に回復するケースがあることを示しました。
ボイストレーナーが行うボイストレーニングでは、こうした生理学的な変化を理解し、無理のない発声習慣を作り直すことが求められます。
声質の変化 ― darkening
女性の声は加齢に伴い「暗く」「太く」なる傾向を示します。これは低音化に伴う現象ですが、単純にF0が下がるだけではありません。
声帯粘膜の厚みや浮腫、さらに咽頭腔の拡大などが関与し、共鳴のシフトが起こることで、音色全体がダークに変化します。このdarkeningは、クラシック音楽で求められる「明るく若々しい声質」とは対照的であり、舞台上の印象に大きな影響を与えます。
この変化に対応するためには、母音調整や共鳴の再設計を含むボイストレーニングが有効です。単なる声量の強化ではなく、音色をコントロールする訓練こそが、年齢を重ねた歌手にとって重要な課題となります。
致命的となる音域喪失
音域の喪失は、歌手にとって単なる技術的な問題ではありません。
ソプラノ歌手に限らず、ポップスやミュージカル俳優を含む多くの女性歌手は、加齢によって高音域を失うと、これまで歌ってきた楽曲をそのまま歌えなくなるという現実に直面します。代表曲やオーディエンスに期待されるナンバーをキーを下げて歌う、あるいは別の楽曲に置き換えるなど、レパートリーの調整を余儀なくされることも少なくありません。
もちろんメゾソプラノやアルトの音域に移行することも考えられますが、声質やキャラクターの違いによって「自分らしい歌い方」や「舞台上での存在感」が大きく変わってしまう可能性があります。これはクラシック歌手に限らず、ポップスやミュージカルの世界でも同様であり、長年築いてきた表現スタイルが揺らぐという点で非常に深刻な問題です。
桜田の現場でも、「若い頃のように高音が出ない」「声が暗くなった」 と相談してくるアーティストの多くは女性です。こうした場面で提供するボイストレーニングは、単に声を戻すためではなく、新しい声の可能性を開拓するためのプロセスとなります。
研究で見える共通点
ここまでに挙げた研究から共通して言えるのは、女性の声の加齢変化は以下の要素が組み合わさって起こるということです。

1. F0(ピッチ)の低下:加齢による基音の低下(Vorperian 2018)。
2. ホルモン変化:更年期後のエストロゲン低下による声帯粘膜の変化(Abitbol 1999, Boulet 1996)。
3. 声質のdarkening:粘膜・共鳴腔の変化による音色の変化。
4. 音域喪失の深刻さ:特に高音域が失われることの致命性。
これらの要素は完全に避けることはできませんが、科学的知見に基づいたボイストレーニングを組み合わせることで、その影響を緩和し、表現力を維持する道は確かに存在します。
まとめ
女性の声は加齢によって低音化し、特に更年期以降にホルモン変化が加わることで、高音域の喪失と声質の暗化が進みます。これはクラシックやミュージカルの歌手にとって致命的な問題であり、ポップスのシーンでも同様にキャリア全体に大きな影響を与えます。
しかし、この変化は「避けられないもの」として受け入れるだけではありません。ボイストレーニングを通じて、変化した声を新しい表現手段として磨き直すことは十分可能です。
次回は、研究の知見をもとに「低音化は防げるのか?」「防げないとしても何を維持できるのか?」という問いに迫り、具体的な対策やハビリテーションの方向性について考察します。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話