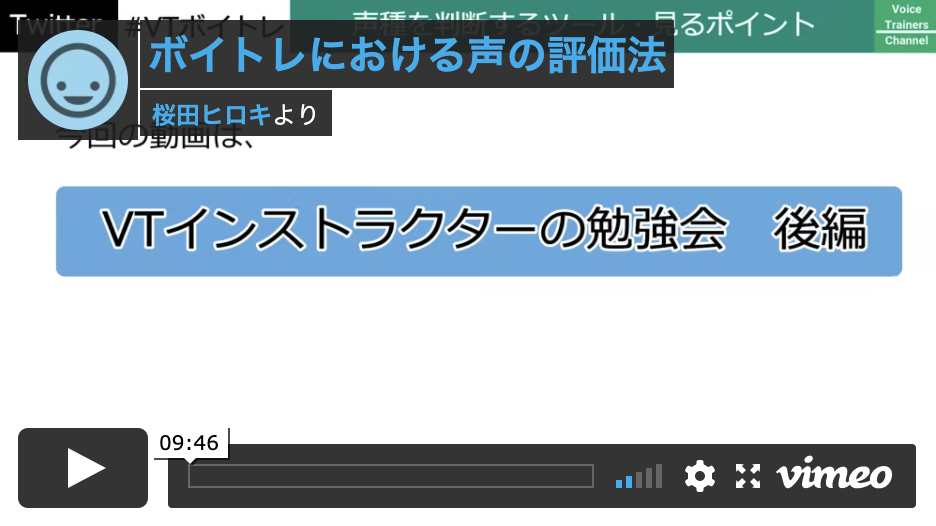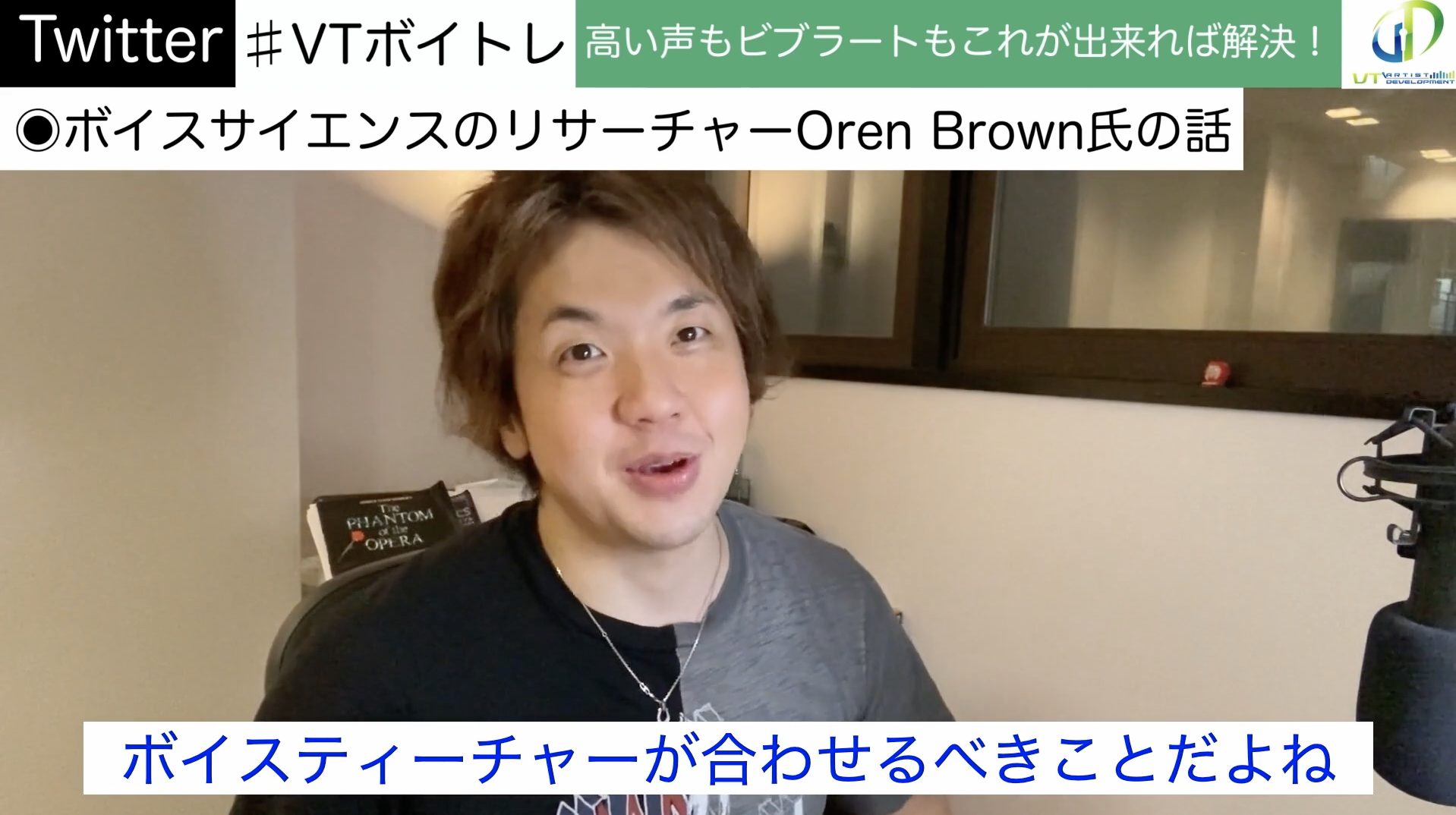第8話:予防法 ― 障害を起こさないためのボイストレーニング
歌手にとって、声は単なる道具ではなく「表現のすべて」を担うものです。しかし、声の障害に悩む歌手は少なくありません。結節やポリープのような器質的病変から、機能性発声障害と呼ばれるパターンまで、その多くは予防やセルフケアでリスクを減らすことができます。
実際に、臨床研究でも一般的な声の衛生(vocal hygiene)やウォーミングアップ、さらにはクールダウンが、声の健康を維持し、場合によっては手術を回避する効果を示すと報告されています。
本稿では、歌手にとって実際に役立つセルフケアを、研究知見と現場での実践を交えて整理していきます。
1. 声の衛生 ― 予防の第一歩
声の障害予防において最も基本的で効果的なのが声の衛生(vocal hygiene)です。これは、発声を妨げる生活習慣を避け、声帯にとって良い環境を維持するための総合的なケアを意味します。

水分補給
声帯粘膜は潤滑性が高いほど効率的に振動します。水分不足は発声閾値圧(PTP)を上昇させ、同じ声を出すにも余計なエネルギーが必要となり、疲労や障害につながります。
– 目安:体重1kgあたり30〜40mlを摂取。(桜田の経験では、多くのシンガーが全く足りていない状況)
– 方法:常温水をこまめに、喉が渇く前に飲む。
– 補足:加湿器やスチーム吸入で局所の加湿も推奨。
Demystifying Vocal Hygiene (2023)(声の衛生指導) では、全身的水分摂取と表面的加湿を組み合わせることで声の効率を維持できると提案しています。
発声過用・乱用の回避
– 騒音環境での大声会話を避ける。
– 長時間の叫び声、過度な練習を制限する。
– マイクを使える環境では無理に声量でカバーしない。
声を酷使しすぎること自体が最大のリスク因子です。歌手にとって「練習量を減らす」ことがセルフケアになる場合もあります。
逆流性胃食道炎(LPR)の管理
胃酸逆流は声帯粘膜を直接刺激し、慢性的な炎症を引き起こします。
– 就寝直前の飲食を避ける。
– カフェイン・アルコール・酸性飲料を控える。
– 枕を高めにして眠る。
休養とペース配分
激しい発声負荷の後には休養を入れることで機能が向上します。一般的には歌唱練習そのものが声にとって高強度の運動と考えられます。
– 連日の長時間練習は避ける。
– 声の疲労感が強ければ翌日は休声日とする。
– 短時間で集中する「インターバル型練習」を取り入れる。
Vocal Hygiene Education Program (2019) では、衛生教育によって発声過用行動が減少し、声の再発障害リスクが下がることが報告されています。

2. ウォーミングアップ ― 声の準備運動
スポーツと同じように、歌唱もウォーミングアップが重要です。声帯や呼吸筋は筋肉・粘膜組織であり、いきなり高音や大音量を要求すると損傷のリスクが高まります。
研究で示された効果
– 発声ウォーミングアップは声の準備性を高め、発声疲労を予防する。
– 発声直後には努力感が増すが、短時間で回復し、安定度が上がる。
– 高音発声や長時間の歌唱に対する耐性を高める。
※歌手にとっては超重要項目ばかりです。
方法例
– SOVT(半閉鎖発声):ストロー発声、リップトリルで摩擦を減らし、効率的な声門閉鎖を誘導。
– 軽いハミング:鼻腔共鳴を意識し、リラックスした音色で発声開始。
– 音階練習:低〜中音域からスタートし、段階的に音域を広げる。
このようにウォーミングアップは「声帯を温める」だけでなく、筋肉・呼吸・共鳴の統合を調整する機能を果たします。
3. クールダウン ― 発声後の整理運動
ウォーミングアップが「準備」なら、クールダウンは「リセット」です。歌唱や練習で負荷がかかった声を、元の会話域に戻す作業です。
研究からの知見
– Ragan (2016):68%の歌手がクールダウン後に声が楽になったと主観的改善を報告。
– Mezzedimi (2018):クールダウンによってF0(基本周波数/ピッチ)上昇やジッター・シマー(震え)が軽減し、音響的安定性が改善する傾向。
– Onofre (2017):歌唱後のF0上昇がクールダウンで緩和された。
※特に女性シンガーで、歌った後に声が上ずる感覚のある方にはとても重要なプロセスと考えられます。
またIngo Titze氏はワークショップ内で「例としてミュージカルで極端なベルト発声を行った後は、声をリセットするためにSOVTは有効だと考える」と述べていました。
具体的な手段
– SOVT(ストロー発声やリップトリル):摩擦を抑えて声帯の疲労を軽減。
– あくび発声(Yawn-Sigh):喉頭を下げ、声帯の緊張を解放。
– 頸部ストレッチ・マッサージ:外喉頭筋のこわばりを緩め、翌日の疲労を防ぐ。
歌唱後に数分〜10分程度取り入れることで、声帯疲労の蓄積を軽減できると考えられます。
実際に桜田のクライアントでもライブの直後にストロー発声とボーカルマッサージを組み合わせて行い歌唱クオリティの向上や、本人の知覚で努力性発声が軽減すると報告をうけてます。
4. 良性声帯病変とセルフケアの効果
特に注目すべきなのは、良性声帯病変(ポリープ・結節)に対するセルフケアの効果です。
Vocal Hygiene Education Program (PMC, 2019) では、強化された声の衛生教育を受けた患者のうち、手術を回避できた割合が有意に高かったと報告されています。
これはつまり、生活習慣や発声行動の改善だけで、器質的な病変が軽快する場合があることを示しています。手術は最後の手段であり、セルフケアの徹底が一次予防・二次予防の両面で重要であると理解できます。
5. まとめ ― 予防はキャリアを守る第一歩
– 声の衛生:水分補給、発声過用の回避、LPR管理、休養。
– ウォーミングアップ:SOVTや軽い音階練習で声を準備。
– クールダウン:SOVT、あくび発声、頸部ストレッチで負荷をリセット。
– 衛生教育の効果:病変の手術回避率を高める可能性。
歌手にとって声は最大の資産であり、障害はキャリアに直結します。セルフケアは地味に思えるかもしれませんが、研究でも効果が裏づけられ、現場でも実践可能な最前線の方法です。
予防に意識を向けることは、単に「声を守る」だけでなく、「声を育てる」ことでもあります。ボイストレーニングをセルフケアの延長線に置くことで、歌手自身が自分の声を一生使い続ける力を養うことができるでしょう。
機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括
👉 第1章:ミックスボイスとは何か? ― 定義と誤解
👉 第2章:ブレイクの正体 ― 地声/裏語と声道の相互作用
👉 第3章:ジャンル別のミックス ― クラシックとCCMの違い
👉 第4章:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても疲れる理由
👉 第5章:レジスター移行の科学 ― SourceとFilterの関係
👉 第6章:4つの共鳴ストラテジー
👉 第7章:ベルティングの実践と限界
👉 第8章:Airflowと声門下圧のバランス ― 効率的で安全なベルティング
👉 第9章:声の音量とエネルギー効率 ― SPLで見る発声の個性
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話