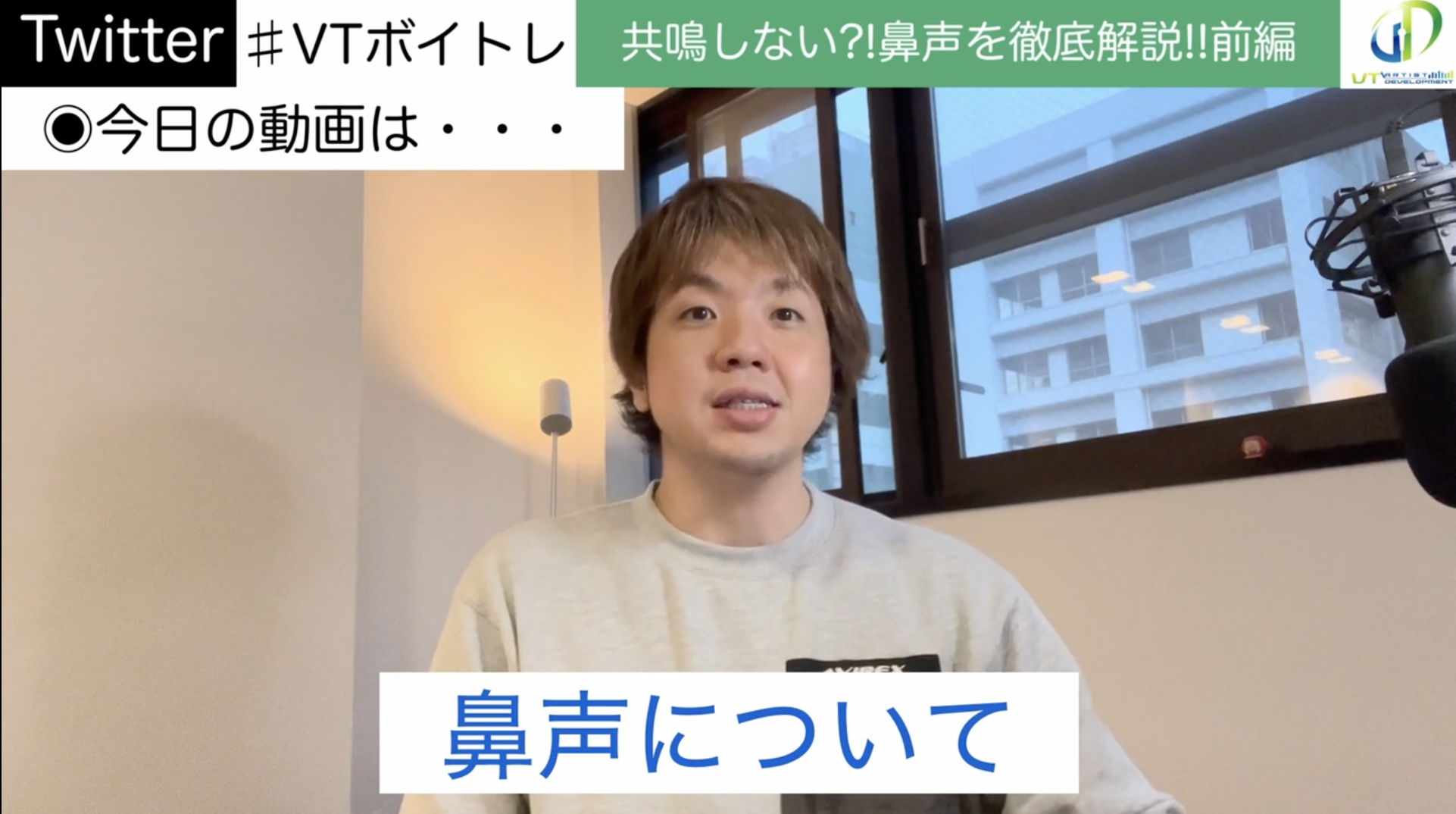第2話:ウォーミングアップとクールダウンの科学的メリット
声を「温める」ことと「冷ます」ことの両輪。
ウォーミングアップは歌うための準備。一方、クールダウンは歌った後の回復のための発声です。身体の筋肉と同様に、声の使用後にも「ゆるやかに収束させるプロセス」が必要であることが、近年の音声科学で明らかになってきました。
声は筋活動・血流・粘膜の協調によって成立する精密な運動です。それゆえ、過剰な使用の後に“何もせず止める”ことは、激しい運動後にストレッチを省くことと同じくらいリスクがある。声帯粘膜や外喉頭筋群が緊張したまま睡眠に入ると、翌朝の発声立ち上がりが重くなり、音域や響きに影響を及ぼします。
本章では、クールダウンで実際に起こる生理的変化、研究による効果、そして桜田が現場で観察してきた回復プロセスを紹介します。
さらに後半では、英国Voice Care Centreなどでも注目されるサーカムラリンジャル(ボーカルマッサージ)を、クールダウンと並ぶ回復手法として位置づけ、科学的根拠と実践的意義を考察します。

クールダウンとは何か? その目的と背景
クールダウンとは、歌唱後に行う軽い発声や呼吸運動を通して、声帯・喉頭・頸部周囲筋をリラックスさせる回復行為です。 目的は単純に「声を休める」ことではなく、発声で生じた微小な炎症や筋の過活動を整えることにあります。
スポーツ医学では、強い運動の直後に完全休息を取るよりも、軽い運動(active recovery)を行った方が乳酸除去や筋の再酸素化が促進されることが知られています。発声でも同様に、軽度の発声刺激が血流を正常化し、筋や粘膜の回復を助けることが示唆されています。
声を酷使した直後に完全沈黙を取るよりも、軽いハミングやリップトリルなどで「声を収束させる」方が翌日の発声が軽くなる。これは多くの歌手が体感的に知っていることですが、近年はその背景に科学的な説明が加わりつつあります。
クールダウンで起こる生理的プロセス
声を出し終えた直後、喉頭では小さな炎症反応と筋の緊張残存が生じます。長時間の発声では、声帯の接触によって生じる摩擦熱や微小な粘膜損傷、粘液層の不均一化なども起こります。
クールダウンは、それらを回復に向かわせる再調整の時間です。
まず、軽い発声によって喉頭と周辺筋への血流が穏やかに保たれることが重要です。急に発声を止めてしまうと、声帯周辺の血管収縮が起こり、局所の代謝が停滞します。一方、軽度発声を継続することで血流が維持され、酸素と栄養が再供給されます。
Abbottら(2012)は、急性音声負荷を与えた被験者を3群に分け、レゾナント発声・声安静・通常会話を比較しました。その結果、レゾナント発声群では炎症マーカー(IL-1β, MMP-8)の上昇が最も低く、軽い発声が声帯の炎症を抑制する可能性が示されました。この「軽い発声が回復を促す」という概念は、クールダウンを行う理論的根拠の一つです。
さらに、クールダウンでは筋の共同収縮を解消する効果もあります。歌唱中は喉頭挙上筋・喉頭下降筋・舌骨筋群などが微妙に拮抗しながら働いており、終演後もしばらくそのパターンが残ります。軽いグライド発声やハミングを行うことで、喉頭が中立位に戻り、過剰な筋緊張がリリースされていきます。

クールダウンの研究エビデンス
クールダウンに関する研究はまだ多くはありませんが、近年の報告をいくつか紹介します。
Ragan(2016)はプロ歌手を対象に、歌唱後にクールダウン(リップトリル・ハミング・スライドなど)を行う群と、休息のみの群を比較しました。結果、クールダウン群は「発声が楽」「喉の張りが取れる」と主観評価が有意に改善。聴取者による評価でも、音質がより安定して聴こえる傾向が確認されました。
Ribeiro(2016)のシステマティックレビューでは、クールダウンによってHNR上昇、jitter/shimmer低下、主観的疲労感の軽減が報告された研究が複数ありました。ただし、研究デザインやサンプル数のばらつきが大きく、今後の検証が必要とされています。
Whitling(2022)は、ウォームアップとクールダウンを同じ被験者に実施し、自己評価の変化を比較。
ウォームアップでは一部の被験者が「努力感が増す」と答えた一方、クールダウン後は「楽になった」「響きが戻った」という回答が優勢でした。この研究は、クールダウンが心理的にもリラクゼーション効果を持つことを示唆しています。
これらを総合すると、クールダウンは「炎症・筋緊張・主観疲労」を穏やかに戻す効果を持つと考えられます。桜田の現場でも、ライブ終演後に軽いレゾナント発声を行う歌手は翌日の発声立ち上がりが明らかに良く、声帯の“むくみ感”が残りにくいという傾向があります。
実践的なクールダウンの方法
クールダウンは難しい技術を要しません。
むしろポイントは強すぎないこと、短時間でも毎回行うことです。
– 時間の目安:3〜8分程度
– 強度:通常会話よりも弱い音量
– 目標:喉頭をリラックスさせ、呼吸・共鳴を穏やかに保つこと
おすすめの手順は以下の通りです。
1. ハミング(低音域)
2. ng発声
3. リップトリル/ストローフォネーション
4. スライド発声(グライド)
最後に深呼吸し、首や肩のストレッチを行いながら終了する。
これだけでも声帯・喉頭・呼吸筋のバランスが整い、翌朝の声が変わります。
サーカムラリンジャル(ボーカルマッサージ)とクールダウンの関係
クールダウンは内的な発声運動による回復ですが、もう一つ重要な外的アプローチがあります。それがサーカムラリンジャルマッサージ(Circumlaryngeal Massage)です。

これは、頸部・喉頭周囲の筋(舌骨上筋群、甲状舌骨筋、胸骨舌骨筋など)に対して手技を行い、筋緊張を緩和し、喉頭の可動性を回復させる方法です。
英国Voice Care Centreでは「Vocal Massage」として体系化され、音声障害からプロ歌手のコンディショニングまで広く用いられています。
科学的根拠と研究動向
複数の研究で、頸喉マッサージ(Manual Circumlaryngeal Therapy, MCT)は筋緊張性発声障害(MTD)に有効と報告されています。
2023年のメタ分析では、MCTによりHNRが有意に上昇し、jitter・shimmerが低下。
俳優を対象とした研究(2024)では、喉頭マッサージ直後に頸喉部筋緊張が有意に減少(p<0.001)し、発声時の喉の抵抗感が軽くなったと報告されています。
桜田の現場でも、連日のステージを行う歌手に対し、クールダウン後に舌骨サーフや咽頭リリースを加えることで、翌日の声帯疲労や共鳴位置の乱れが明らかに減少するケースが多く見られます。
クールダウンとの補完関係
クールダウンとマッサージは、どちらも「声をリセットする」行為ですが、アプローチの方向が異なります。
クールダウンは声を使って内側から整える内的回復、
マッサージは手技で外側から解きほぐす外的回復。
そのため、両者を組み合わせることで、筋骨格系・粘膜・神経系を同時にケアすることができます。
たとえば、発声後に以下のような流れを行うと効果的です。
1. 軽いハミング・リップトリルで発声を落ち着ける(3〜5分)
2. 舌骨周囲・胸鎖乳突筋・喉頭下筋を指先で軽くリリース(3〜5分)
3. 最後に深呼吸を行い、副交感神経優位の状態で終了する
この流れは、桜田がツアー現場で実際に行ってきたプロトコルに近いもので、疲労した喉を休めるだけでなく、翌日のリハに備えるコンディショニングとして非常に効果的です。
注意点と安全性
強い圧をかけることは避けるべきです。
炎症や痛みがある場合は実施せず、専門家に相談することが望ましい。正しく行えば、声の疲労回復・筋の弛緩・喉頭位置の再調整に有効です。
クールダウン+マッサージの臨床的意義
クールダウンとマッサージを組み合わせることで、回復のスピードと質が向上します。
発声による炎症や筋緊張は、内部と外部の両側面で生じるため、両方に働きかけるのが最も効果的です。
桜田が指導してきた舞台俳優のケースでは、リハーサル後に「軽いハミング+頸喉リリース」を5分取り入れただけで、翌日の声の立ち上がり時間が半分になり、喉頭位置の安定感も改善。客観的にも声域上限が1音分上昇した例があります。
このように、発声後の身体介入を「余分な儀式」ではなく、声の健康維持の一部と捉えることが重要です。
クールダウンとマッサージの併用は、声帯粘膜の負担を最小限に抑えながら、神経筋系の再調整を助ける声のアクティブリカバリーと言えます。
まとめ:声を「温め」、そして「冷ます」ことの科学
ウォーミングアップが声の立ち上がりを助けるように、クールダウンは声の再生を助けます。どちらも発声機構を“極端な状態から中立に戻す”という共通の目的を持っています。
さらに、サーカムラリンジャル(ボーカルマッサージ)は、その外的側面を補う有力な手段です。
発声によって疲労した筋や結合組織を直接リリースし、声帯周辺の環境を整えることで、声を「使うこと」と「守ること」の両立が可能になります。
声のトレーニングは「どれだけ出すか」だけでなく、「どう回復させるか」も同じくらい重要です。
ウォームアップ・クールダウン・マッサージ——これらをバランス良く取り入れることが、プロフェッショナルな声の長寿を支える科学的アプローチなのです。
このあと第3話では、「ウォーミングアップ・クールダウンは本当に必要か?」——個体差と最適化というテーマに発展します。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト
ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!
ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密