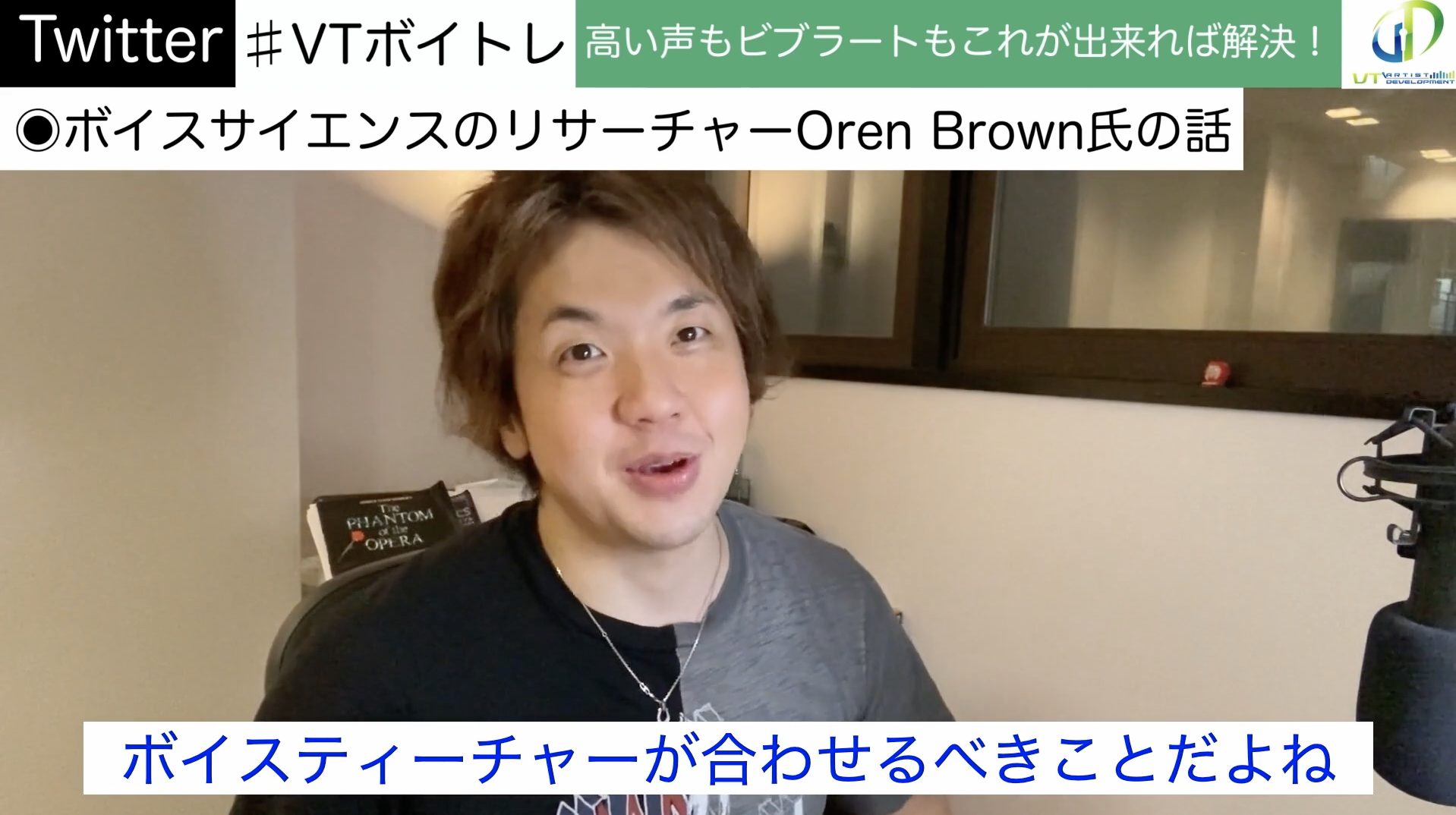クラシック発声を基盤として訓練を積んできた女性歌手が、ミュージカルやポップス(CCM)に挑戦する際に直面する大きな課題のひとつが「ベルト唱法」への適応です。
クラシックの声区操作や共鳴戦略をそのまま用いてベルトを試みると、過剰な声門閉鎖・喉頭挙上・喉周囲筋の緊張を伴い、機能性発声障害(筋緊張性発声障害)に発展する危険性があります。
これは臨床的にもよく見られる問題であり、ジャンル移行が単なる「スタイルの違い」ではなく、生理学的にまったく異なる発声パターンへの再学習を要する複雑な課題であることを示しています。

桜田ヒロキ考察
桜田ヒロキは、クラシックの声区制御をそのまま残してベルトを試みる女性歌手を多く見てきました。
多くの場合、喉頭を無理に押し上げてしまう「代償パターン」が身体に染みつき、喉頭全体の過緊張に繋がります。
特に女性のクラシック発声とベルト発声の違いは、甲状被裂筋(TA)の介入の度合いにあります。
ベルトでは TA の介入によって声門閉鎖率(CQ)が上昇し、声区チェンジの位置自体が高く設定されます。
しかし、TA の関与が弱いまま「地声的な音色」を作ろうとすると、外側輪状披裂筋(LCA)による「後方優勢の代償」が起こり、結果的に過緊張を招きやすくなるのです。
つまり「地声のような何か」で発声訓練を繰り返してしまい、誤った発声が癖化してしまうと言う例です。
研究データから見るクラシックと CCM の発声差異
1. 発声様式の分類(Thalén & Sundberg, 2001)
スウェーデンの研究では、6名のプロ女性歌手にクラシック・ポップ・ジャズ・ブルースの各スタイルで同一旋律を歌わせ、声門閉鎖率(CQ)や呼気流を測定しました。
クラシック歌唱:声門閉鎖率(CQ)平均 0.42(閉鎖時間が短い=流れるような発声)、呼気流量が安定
ポップ/ジャズ:声門閉鎖率(CQ)平均 0.48(中程度の閉鎖)、声の明瞭性は高い
ブルース:声門閉鎖率(CQ)平均 0.55(閉鎖時間が長い=圧搾的発声)、声門上圧が上昇
→ このデータは、クラシック女性歌唱が柔軟な閉鎖・共鳴を基盤にしている一方、CCM スタイルでは声帯振動や閉鎖のメカニズムが根本的に異なることを明確に示しています。
桜田ヒロキ考察
数字で見ても分かる通り、クラシックの声門閉鎖率(CQ)はかなり低く、流れるような発声を支えています。一方、ベルトは声門閉鎖率(CQ)が高くなる。つまり、「声帯の振動システム自体が別物」と理解する必要があります。桜田ヒロキは指導する際も、クラシックから移行する歌手には「声門閉鎖を強める」こと以上に、「どの筋がどのように働いて閉鎖を作っているのか」を意識させています。
ちなみにクラシックをトレーニングしてきた女性俳優の地声発声の声門閉鎖率を桜田ヒロキの手持ちの機材で計測した所、60%を超えていた事がありました。
明らかに声門閉鎖を作りすぎの発声で、クラシック発声はトレーニング出来ている。地声歌唱は素人の男性のがなり声とほぼ同じと言う状況でした。機能性発声障害(筋緊張性発声障害)
2. 発声調整と環境適応(Melton et al., 2022)
Melton らは、クラシック声楽家 15名を対象に、屋外 vs 屋内での歌唱を比較しました。
屋内:シンガーズ・フォルマント付近(2.5–3.5 kHz)の強調が顕著
屋外:同帯域のエネルギーが平均 2–3 dB 減少する傾向
調整戦略:屋外では声道の形状を変え(咽頭腔の拡大)、中音域(1.5–2.5 kHz)のエネルギーを増やすことで声の到達性を補償
結果:観察者は屋外でも「十分に届く声」と評価したが、音響的には声道操作の微調整が必須であることが分かった。
→ この点は、マイク使用を前提とした CCM とは根本的に異なる戦略であり、スタイル移行時には環境と声の使い方のギャップを埋める必要があることを意味します。
桜田ヒロキ考察
桜田ヒロキの経験でも、クラシックの発声は「ホールでマイクなしでの歌唱」を基準に組み立てられており、屋外やマイクを使う現場では全く別の戦略が必要です。
ベルトでは喉頭がある程度上がることを受け入れ、声道の調整を変えていく必要があります。
特にミュージカル歌手には「喉頭は必ずしも低く固定しなくても良い」という認識の転換を促しています。
まとめ:スタイル移行の難易度と再教育の必要性
桜田ヒロキは、女性クラシック歌唱からベルト発声(ミュージカルやCCM)へのスタイル移行は、声区制御の方法の違いが大きな障壁となると考えています。
クラシックの声区制御のままベルト発声を無理に行うと、喉を無理に押し上げてしまう「代償パターン」が身体に染みつき、喉頭全体の過緊張を生み出します。
これは特に甲状被裂筋(TA)の介入による声門閉鎖率(CQ)の上昇が不十分な場合に顕著です。
その結果、声区チェンジの高さを過度に引き上げてしまい、甲状被裂筋の関与が弱い状態で地声に近い発声を作ろうとした際に、外側輪状被裂筋(LCA)などによる「後方優勢」の代償が起こり、過緊張を招く可能性が高まります。
(通常、女性の地声歌唱時の声区チェンジはG♭4からB♭4くらい。クラシック発声の場合はE♭4からF程度になります)
長期的にこのような代償発声を繰り返すと、声の硬さ、喉の疲労感、声量低下といった機能性発声障害(筋緊張性発声障害)の典型的な症状が現れます。つまり、効率的な発声が行えなくなり、発声障害に進行するリスクが高まるのです。
ベルト発声を安全に身につけるためには、喉頭の調整・共鳴の再構築・呼吸サポートの再教育という3つの大きな柱が必要になります。
喉頭の調整:クラシックのように超高音以外の全音域で喉頭を低く保とうとするのではなく、音域によっては喉頭が自然に上がることを受け入れる調整。
共鳴の再構築:裏声に最適化された共鳴から、地声に適した共鳴へと再学習すること。
呼吸サポート(支え)の再教育:呼吸筋による操作だけでなく、声門閉鎖が適切に働くことで生まれる声門下圧の理解を深めること。
これらは論文的にも支持されており、Popeilによる軟骨位置の変化、Titzeによる声門閉鎖率(CQ)の上昇、Lepockによる臨床的語りの分析など、異なる角度からも同じ課題が繰り返し報告されています。
声楽からミュージカル、CCMスタイルへの発声の転換は容易ではありません。
しかし、それぞれの違いを正しく理解し、戦略的に発声トレーニングを行えば、悪い癖を積み上げることなく新しい歌唱スタイルに順応していけると考えます。
さらに、意外と見落とされやすいのが、各ジャンル特有のリズム感やグルーヴを理解し、それに応じた「声の運び方(声のデリバリー)」を習得することです。
これを欠いてしまうと、技術的には正しくても音楽的な説得力に欠ける歌唱になりかねません。
最終的には、声の科学的アプローチと音楽的理解を統合させることが、真のスタイル転換を可能にするカギとなります。
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話