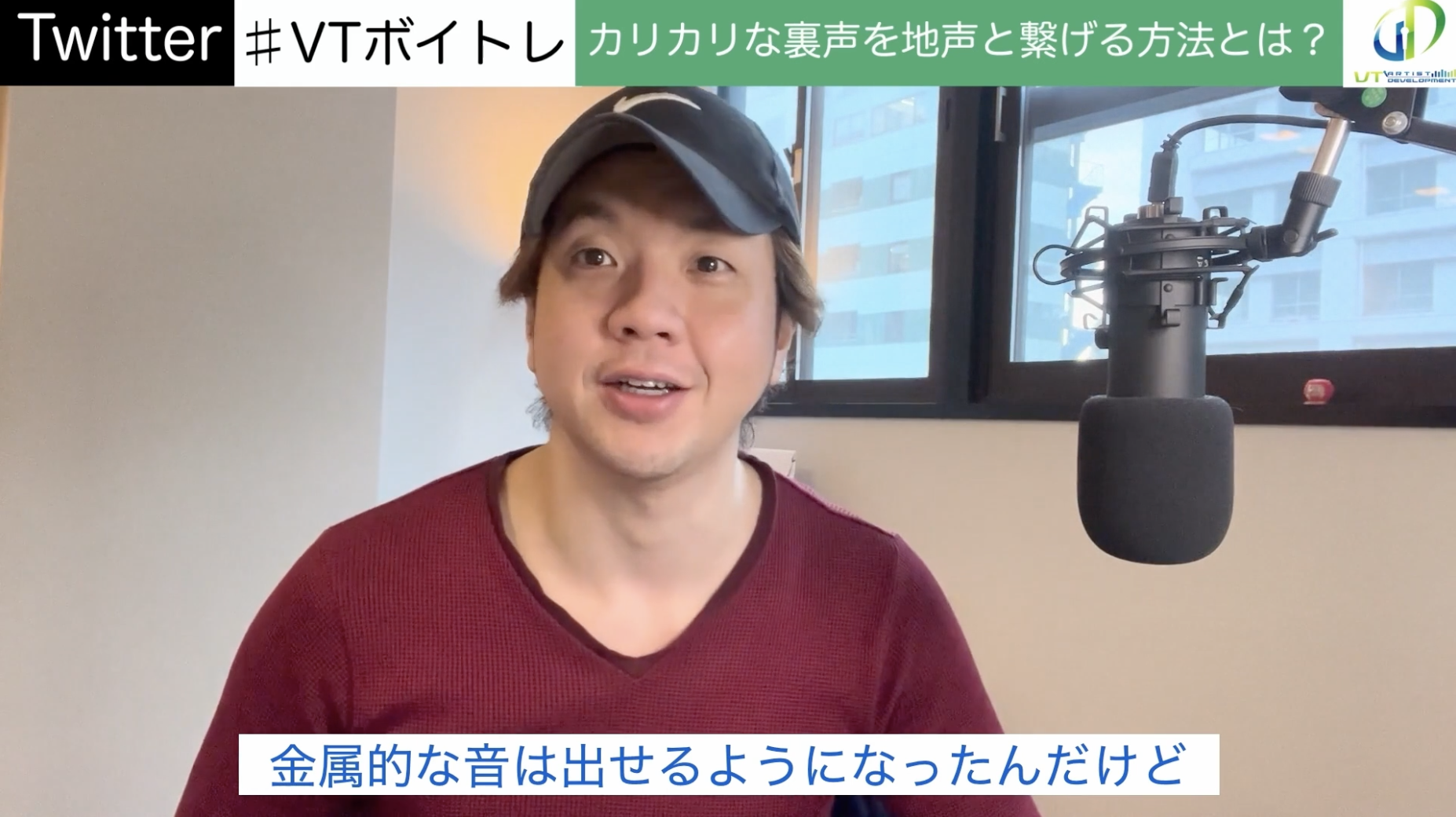第5話:ベルティングとジャンル差 ― 女性クラシック vs 女性CCM
「高音をどう出すか」は、ジャンルごとにまったく異なるゴールを持っています。
クラシックのソプラノと、ミュージカルやポップスのシンガー。
同じ「高音域の発声」でありながら、その音色・響きは大きく異なります。
ボイストレーニングの現場でも
「クラシックで学んだ発声をポップスに応用したら息っぽくなった」「ベルティングの練習したら単なる叫び声になった」という声は少なくありません。
ここには、ジャンル特有の声門閉鎖戦略と声道調整の違いが存在します。
そしてこの違いを理解することは、ボイストレーナーが生徒に適切な指導をする上で極めて重要です。
クラシック(女性ソプラノ)の戦略

女性クラシック発声の基本は輪状甲状筋(CT)主導です。
声帯を長く・薄くストレッチし、CTの働きによってF0(ピッチ/基本周波数)を上昇させます。
このときTAの関与は控えめで、声門閉鎖は比較的弱くなります。
その結果、息の少し混じった「軽やかで透き通った声」が得られます。
しかしそれだけでは声量や存在感が不足するため、クラシックの歌手は声門ではなく声道の操作を駆使します。
咽頭腔の拡大(いわゆる「喉を開く」)、母音ごとのフォルマントチューニング(第1・第2フォルマントを倍音に一致させる)、シンガーズフォルマントクラスタ(2.5–3.5 kHz)の形成によって、弱めの閉鎖でもホールを満たす音量が得られます。
Sundberg(1987, 2001)は、クラシック歌手が「声門閉鎖よりも共鳴の操作」に依存していることを音響分析で示しています。
言い換えれば、女性クラシックにおける高音は「息っぽさを響きでカバーする」戦略だと言えます。
CCM(女性ミュージカル・ポップス)の戦略

対照的に、CCM(Contemporary Commercial Music)の女性シンガーはCT+TA(甲状披裂筋)の協働によって高音を作ります。
CTが張力を作り、TAが剛性を補うことで「芯」のある声を実現します。
ここでは声門閉鎖が強く、息漏れは最小限に抑えられます。
CPP(Cepstral Peak Prominence)が高く、H1–H2の差が小さい、つまり「地声的で存在感のある高音」になるのが特徴です。
声道の調整(倍音と共鳴のチューニング)はクラシックほど極端ではなく、むしろスピーチ寄り。
母音変形も少なく、自然な発音を維持したまま強い声を作ります。
Bourne & Garnier(2010)はミュージカル・ベルティングとクラシック発声を筋電図で比較し、ベルティングではTAやLCAの活動が顕著に強いことを示しました。
つまり、CCMでは「声門閉鎖+声門下圧」が存在感の源泉になっているのです。
男性(補足)
男性テナーの場合、クラシックであっても高音では強い声門閉鎖と声門下圧が必要です。
つまり「芯を持った高音」という点ではCCMと近い戦略を取ります。
違いが出るのは声道調整です。
クラシックは暗めで深い母音を作り、CCMは明るくスピーチ的な母音を維持します。
そのため音色の印象は異なりますが、声門の使い方そのものは女性ほど大きくは変わりません。
音響的な違い
音響分析の観点からもジャンル差は明確です。
女性クラシックはH1–H2がやや大きく(高次倍音が少ない)、CPPは低めで、息っぽいがフォルマント強調で存在感を確保します。
女性CCMはH1–H2が小さくCPPは高く、芯が強く直接的でパワフルな声になります。
Henrich(2006)は声区とジャンルの関連を整理し、女性クラシックとCCMで「レジスター戦略」が異なることを明らかにしました。
またTitzeら(2016)は、ジャンル差を「声門閉鎖 vs 声道共鳴」の比重の違いとして説明しています。
ボイストレーニングへの応用
ボイストレーニングの現場では、このジャンル差を理解することが指導の成否を分けます。
女性クラシックはCT優位を維持しつつ声道調整を徹底し、TA過剰を避けて息の流れを妨げないことが重要です。
女性CCMはCTとTAのバランスを意識させ、強い声門閉鎖を引き出すエクササイズを導入しつつ、声道調整は自然でスピーチ寄りに保ちます。
ボイストレーナーは「ジャンルによって理想の音色が違う」ことを明確に伝え、クラシック的な美声とCCM的なパワフルさは必ずしも両立しないことを理解させる必要があります。
まとめ
女性クラシックと女性CCMの高音戦略は、同じCT/TAのバランスを基盤としながらも、その方向性は大きく異なります。
・クラシックはCT主導+弱めの閉鎖、響きで存在感を作る。
・CCMはCT+TA協働+強い閉鎖、声門下圧で芯を作る。
・男性の場合は声門戦略がCCM寄りですが、声道調整の違いによってジャンルの色が分かれます。
シンガーにとっては「自分のジャンルでは何が求められるのか」を理解することが、高音発声の方向性を決定づけます。
そしてボイストレーナーにとっては「ジャンル別の声の設計図」を提示できることが、指導の専門性を高める鍵となります。
高音はただ出すだけではなく、「どのように響かせるか」「どのような存在感を作るか」がジャンルごとに異なる。
この視点を持つことで、ボイストレーニングはさらに実践的で効果的なものになるでしょう。
輪状甲状筋と甲状披裂筋って「どちらが強い」?
地声の時、音程はどうやって作ってるの?
発声筋にも速筋と遅筋がある?
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト
ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!
ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!