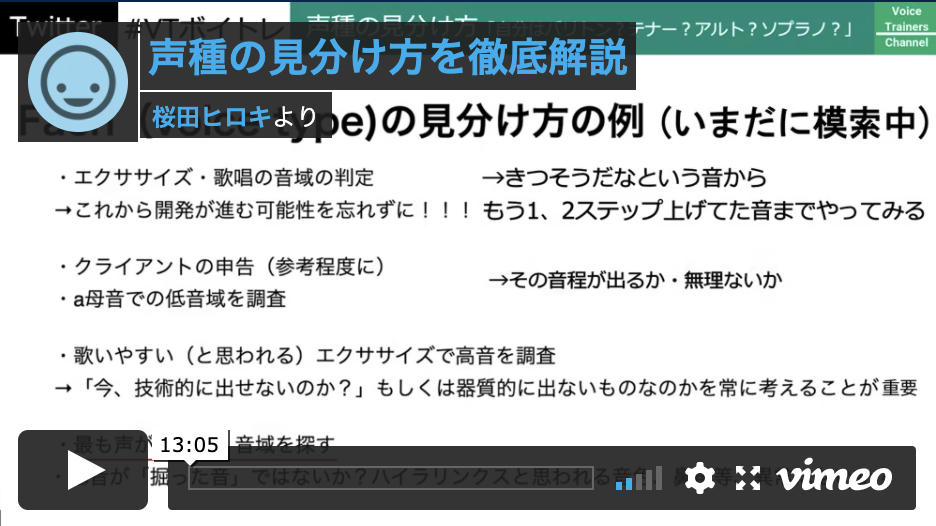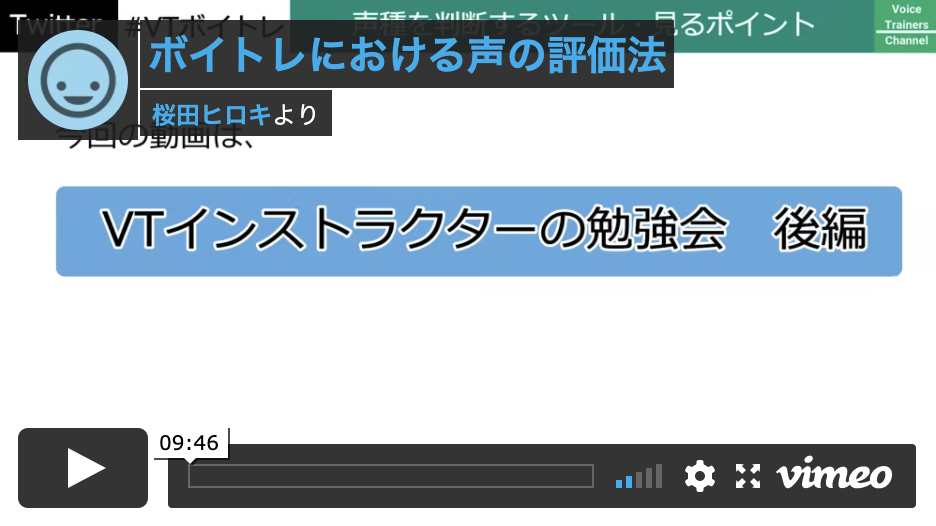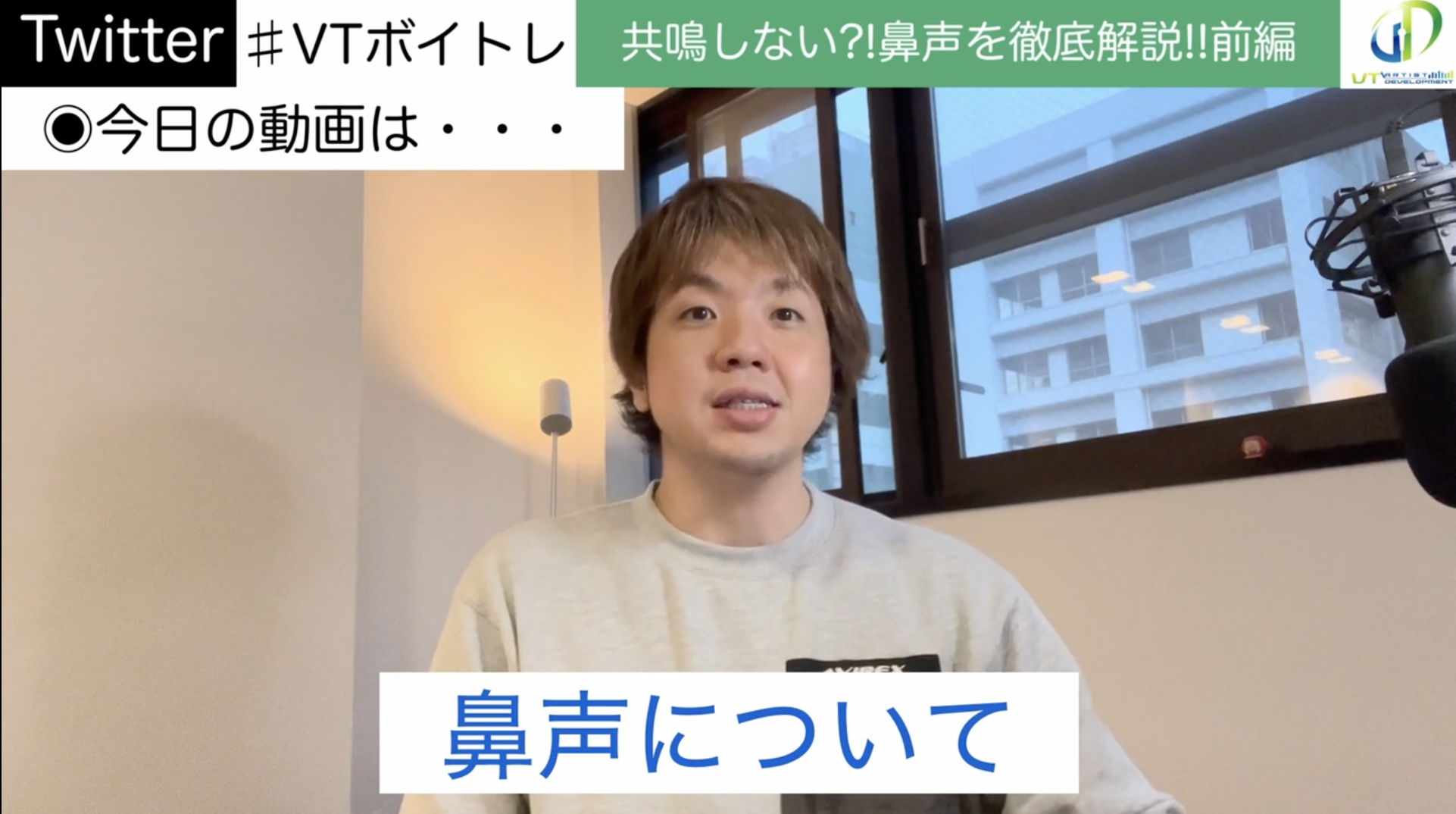- 2025.08.17
- ボイストレーナーのお仕事 加齢による声の変化 声の健康法 歌手の発声障害
前回まで、アメリカで実際に起きた発声障害と、そのリカバリーのプロセスを紹介してきました。最終回となる今回は、現場で役立つ具体的なアドバイスをまとめてみます。
インイヤーモニターの設計術
ステージでの歌唱に大きく影響するのが、イヤモニの音作りです。
多くのアーティストは「自分の声をしっかり返して欲しい」とリクエストしますが、逆に声が大きく聞こえすぎると、発声がぶれてしまうこともあります。
実際、桜田のクライアントの中には「声を少し引っ込める設定」に変えたことでリハから本番まで安定するようになった方がいます。
注意したいのは、モニターエンジニアが聴いている音と、歌手本人が聴いている音は同じではないという点です。
アーティスト歌っている時、常に「自分の生声」も聴いており、さらに生声はイヤモニの音に干渉します。
そのため、エンジニアの調整だけで完結せず、本人の感覚とのすり合わせが不可欠です。
「サンドイッチ練習」で声を軽く保つ
本番直前におすすめなのが「サンドイッチ練習」。
SOVT(ストロー発声など)→歌唱→SOVTという流れで行い、軽やかな発声感覚を思い出す方法です。
レッスンの現場でも「歌う前にこれをやると声が軽く出る、ツヤが出る」と言う生徒が多く、実際に本番でも緊張に左右されず声が安定した例が数多くあります。
特に重要なのは「自分にとって出しやすい発声練習パターン」を早めに見つけておくこと。
母音・子音の組み合わせや音階など、人によって違うので、それを持っておくとツアーや収録で役立ちます。
ツアー中の声の予算管理
「Vocal Budget(声の予算)」という考え方があります。
ハードなツアー中は、歌以外での声の使用をいかに減らすかが勝負です。
声の予算は、使用量だけでなく、睡眠・水分・加湿などによっても変動します。
つまり「声の衛生管理」全体が予算配分に直結するということです。
ツアー中の小さな油断が、翌日の大きな声のトラブルに繋がることは珍しくありません。
キーを下げる勇気
最後に、もっとも勇気がいる決断のひとつが「キーを下げる」ことです。
10年前に作られたキー設定が、今の声に最適とは限りません。
高音続きの曲では「被せ」(録音音源との併用)を活用しつつスタミナを温存するのも現実的な方法です。
私の経験では、キーを下げることを発表した際に「今の声で聴けることが嬉しい」というファンの声が多く届きました。
歌手本人が思う以上に、ファンは柔軟で、現在の声を大切にしてくれる存在なのです。
まとめ
発声の健康を守るためにできることは、トレーニングや治療に限りません。
イヤモニの調整、発声準備の工夫、声の予算管理、キーの見直し――いずれも「現場で即使える声の戦略」です。
これらを取り入れることで、アーティストは過酷な環境でも自分の声を守り、表現を続けることができると考えます。
ツアー中に発声障害に罹患したロック歌手のケース(第1話)
ツアー中に発声障害に罹患したロック歌手のケース(第2話)
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話