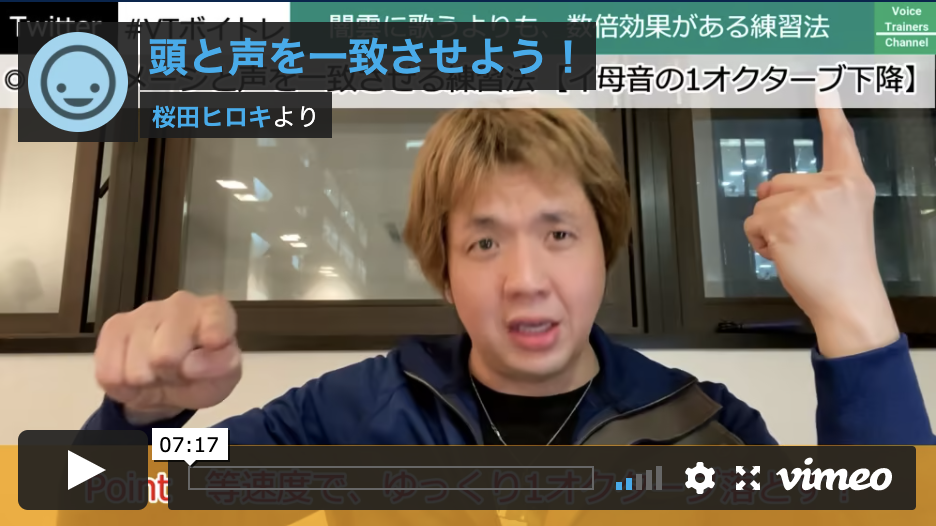第3章 スタイルと表現で使い分けるビブラートの技術
前章 ビブラートのトレーニング方法で述べたように、自然なビブラートは身体の協調によって「現れる」ものです。
しかし、音楽表現の中では、その揺れをどのように“使うか”“使わないか”という選択が求められます。
ビブラートは単なるテクニックではなく、スタイルや感情の一部としてコントロールされる表現要素です。
この章では、クラシックとCCM(Contemporary Commercial Music)におけるビブラートの使われ方の違い、フレーズ末尾での変化、ミックスボイスでの安定性などを中心に、ビブラートを意図的にデザインする方法を解説します。

自然な揺れを「制御」する段階へ
前章 ビブラートのトレーニング方法でのトレーニングを経て、ビブラートが自然に発生するようになった段階では、次に「その揺れをどのように使うか」を考える必要があります。
ここで大切なのは、“自然発生したビブラートを止めたり変化させたりする”ことは、無理に揺らすよりも難しいという点です。
僕の師匠の一人、セス・リッグスもエクササイズ中に「ナチュラルなビブラートを止めようとしないで」と良く言っていました。
身体が反射的に作り出す周期的な揺れを、音楽の流れに合わせて微妙に変化させるためには、より高次な筋協調と聴覚制御が必要です。
すなわち、ビブラートのトレーニングは「出す練習」から「止める・変える練習」へと発展していきます。
不規則性と心理的快・不快
前章 ビブラートのトレーニング方法でも触れましたが、私たちは周期の安定した揺れに安心感を覚えます。
逆に、不規則な揺れや過剰な深さは「緊張感」や「不安定さ」を感じさせます。
この心理的反応は、音楽スタイルごとのビブラート使用にも影響しています。
クラシック音楽では滑らかで安定した波形が求められますが、R&Bやジャズでは、クラシックのように常に一定の音幅・速度を保つのではなく、フレーズの流れによって速度や深さを変化させることで、表情を豊かにしています。
これは「リズムをずらす」というよりも、音楽的な流れの中で自然に“周期と振幅を変化させる”ことを意味します。
つまり、不規則性は常に悪いわけではなく、文脈によって“味”として成立することもあるということです。
このとき重要なのは、「聴き手がその揺れをどう知覚するか」です。
同じ深さや速さでも、楽曲のテンポや伴奏の密度によって、揺れの感じ方が変わります。
トレーナーとしては、単に技術的に正しいビブラートではなく、「音楽的に適切な揺れ」を指導できることが理想です。
「ビブラートをかけない技術」:クラシックとCCMのスタイル差
クラシック声楽では、ビブラートは音色の一部として常に存在しています。
一方、CCMでは、ノン・ビブラートやディレイド・ビブラート(音の後半で揺れを加える)が好まれる傾向があります。
これは、ジャンルによって“響きの基準”が異なるためです。

クラシックでは共鳴腔が大きく、音の持続性を重視するため、声帯の周期的な揺れが自然に含まれることが理想とされます。
一方、ポップスやミュージカルでは、リズムとの同期や明瞭なイントネーションが重要なため、音の立ち上がりを“真っ直ぐ”に保つ技術が必要になります。
この「ビブラートをかけない技術」は、意識的に筋活動を止めることではありません。
むしろ、声区や息のバランスを保ちながら、CT・TAの動きを最小限に抑えるという高度なコントロールです。
さらに、実際に音声解析ソフトで声のピッチ変化を観察すると、人間の声においてボイストレーナーが言う「真っ直ぐ出す」という状態は、厳密には存在しません。
どんなに安定しているように聴こえる声でも、微小な周期変動が常に含まれています。
つまり、「真っ直ぐ出す」というのは、実際に揺れをなくすことではなく、“真っ直ぐに聴こえるように変化を小さくする”ことなのです。
この点を誤解してしまうと、声を固定してしまい、むしろ自然な響きを損なう危険があります。
練習法としては、
・ノン・ビブラートでのロングトーン(息の支えを保ったまま)
・メトロノームに合わせて「揺れを遅らせる」ディレイド練習
・原曲を分析し、どの音にビブラートをかけるかを意図的に選ぶ
といったアプローチが有効です。
フレーズ末尾のビブラート制御:RateとDepthの変化
ビブラートの表情を最も効果的に変化させられるのは、フレーズの末尾です。
フレーズが終わる瞬間、聴き手の注意は自然と声の余韻に向かいます。
この「終わり方」をデザインすることで、音楽的印象は大きく変わります。
研究によると、ビブラートの速さ(Rate)が速いほど緊張感を、遅いほど安定感を感じる傾向があります。
また、振幅(Depth)が深いと情熱的、浅いと繊細に聴こえます。
つまり、RateとDepthの組み合わせによって、感情の表現が可能になるのです。
クラシックのビブラートでは、一般的に音の揺れが全音幅で描かれることが多く、これが声を壮大に聴かせる要因の一つになっています。
一方で、CCMでは半音幅を主体とし、ビブラートをリスナーに明確に知覚させたい箇所でRateを落とし、Depthを深めて揺れを強調する傾向があります。
つまり、CCMでは“すべての音で揺らす”のではなく、“伝えたい感情の瞬間だけを揺らす”という使い方がされています。
また、人間の聴覚には限界があり、1秒間に6回以上の揺れ(6Hzを超えるRate)は、音程変化としての認識が難しくなることが知られています。
この知見は、ビブラートの「速さを上げれば良い」という誤解を防ぐ上で重要です。
(この領域については音響心理の研究による裏付けがあり、参考研究を後述予定)
練習法としては、
・1音を持続しながらメトロノームに合わせて揺れを変化させる
・録音やアプリを使って、自分のRate(スピード)とDepth(深さ)の変化を可視化する
・プロ歌手のライブ音源を分析し、意図的変化のタイミングを学ぶ
といった方法が役立ちます。
この段階では「自然な揺れ」に加え、「音楽的に意味のある揺れ」を選択する力が問われます。
ミックスボイスにおけるビブラートの安定性
ミックスボイスの音域では、CTとTAがほぼ同等に働いており、声区の境界が曖昧になります。
この領域では、わずかな筋バランスの乱れがF0の周期に直結します。
そのため、ビブラートが「途切れる」「揺れが早すぎる」といった問題が起こりやすいのです。
安定させるには、まず「息の支え」を強化し、声門下圧を安定させることが大前提です。
その上で、CT・TAが無理なく拮抗できるように、軽いポルタメントや5度スライドを繰り返し行うと良いでしょう。
筋肉が硬直すると、揺れの周期が乱れやすくなります。
また、ミックス域の声では「聴覚の自己同調」が非常に重要です。
自分の声が響く空間をモニターしながら、音の輪郭が一定に感じられるようにすること。
これができると、身体はその安定感に反応し、揺れの周期も自然に整っていきます。
6. 過剰な操作を避ける:コントロールと自然の境界
ビブラートのコントロールに慣れてくると、多くの歌手が「意図的に形を作ろう」とし始めます。
しかし、ビブラートの魅力はあくまで自然さにあります。
過剰なRate操作やDepthの誇張は、声帯振動の連続性を損ない、人工的な印象を与えてしまいます。
Titze(2002)は、ビブラートを神経反射の周期的結果として説明しました。
このモデルに従えば、人為的な制御は生理的な反射ループを乱すリスクがあります。
つまり、コントロールは「抑える」方向ではなく、「選択する」方向で行うのが理想です。
目的は「どんなビブラートを出すか」ではなく、「どんな感情を伝えたいか」。
技術の正確さよりも、音楽的意図の一貫性が優先されるべきです。
7. 応用的練習プラン
1. ノン・ビブラート練習
息の支えを保ちながら、揺れを完全に抑制する練習。
「止める」ことで、反射的に生まれるビブラートを再認識する。
2. ディレイド・ビブラート練習
音を出してから1〜2秒後に揺れを加える。(ミュージカル歌唱では絶対に必要な技術です)
意図的なタイミング制御を学ぶ。
3. Rate変化練習
メトロノームを使い、テンポ60→80→100→120(3連符などを使用)で揺れを早める練習。
周期感覚を身体で学ぶ。
4. Depth変化練習
1音を保ちながら揺れ幅を徐々に深く、または浅くする。
筋緊張と呼吸圧の微調整を体感する。
5. スタイル分析練習
クラシック、R&B、ミュージカルの録音を比較し、揺れの形を視覚的に分析。
これらを交互に行うことで、ビブラートを“操る”のではなく、“選べる”状態へ導きます。
まとめ:ビブラートは「意図」と「生理」の共存
安定したビブラートを持つ歌手は、身体の反射と音楽的意図が矛盾していません。
自然な生理現象をそのまま表現に変換できているのです。
ビブラートの速さや深さを選ぶことは、単に音の問題ではなく、感情のデザインに関わります。
ボイストレーナーは、生徒に“操作”を教えるだけではなく、音楽との関係性を教え“意味づけ”を教える必要があります。
どのスタイルで、どの場面で、どんな心理的効果を狙うのか。
そこに明確な目的があれば、身体は自然と適切な周期に調整されます。
ビブラートは技術であり、同時に呼吸・筋肉・感情・文化が交わる総合的な表現でもあります。
その揺れが「意図のない癖」ではなく、「音楽的な選択」として響くように導くこと。
それが、ボイストレーナーと歌手の次なる目標です。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
ボーカルフライの効能とリスク
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ボーカルマッサージ2025.12.06なぜ発声障害の音声療法はマッサージとSOVTに偏るのか? 2話
ボーカルマッサージ2025.12.06なぜ発声障害の音声療法はマッサージとSOVTに偏るのか? 2話 ボーカルマッサージ2025.12.02なぜ発声障害の音声療法はマッサージとSOVTに偏るのか? 1話
ボーカルマッサージ2025.12.02なぜ発声障害の音声療法はマッサージとSOVTに偏るのか? 1話 ボーカルマッサージ2025.11.23加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第1話
ボーカルマッサージ2025.11.23加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第1話 ボーカルマッサージ2025.11.15音声障害(発声障害)の原因は?データを調べてみた
ボーカルマッサージ2025.11.15音声障害(発声障害)の原因は?データを調べてみた