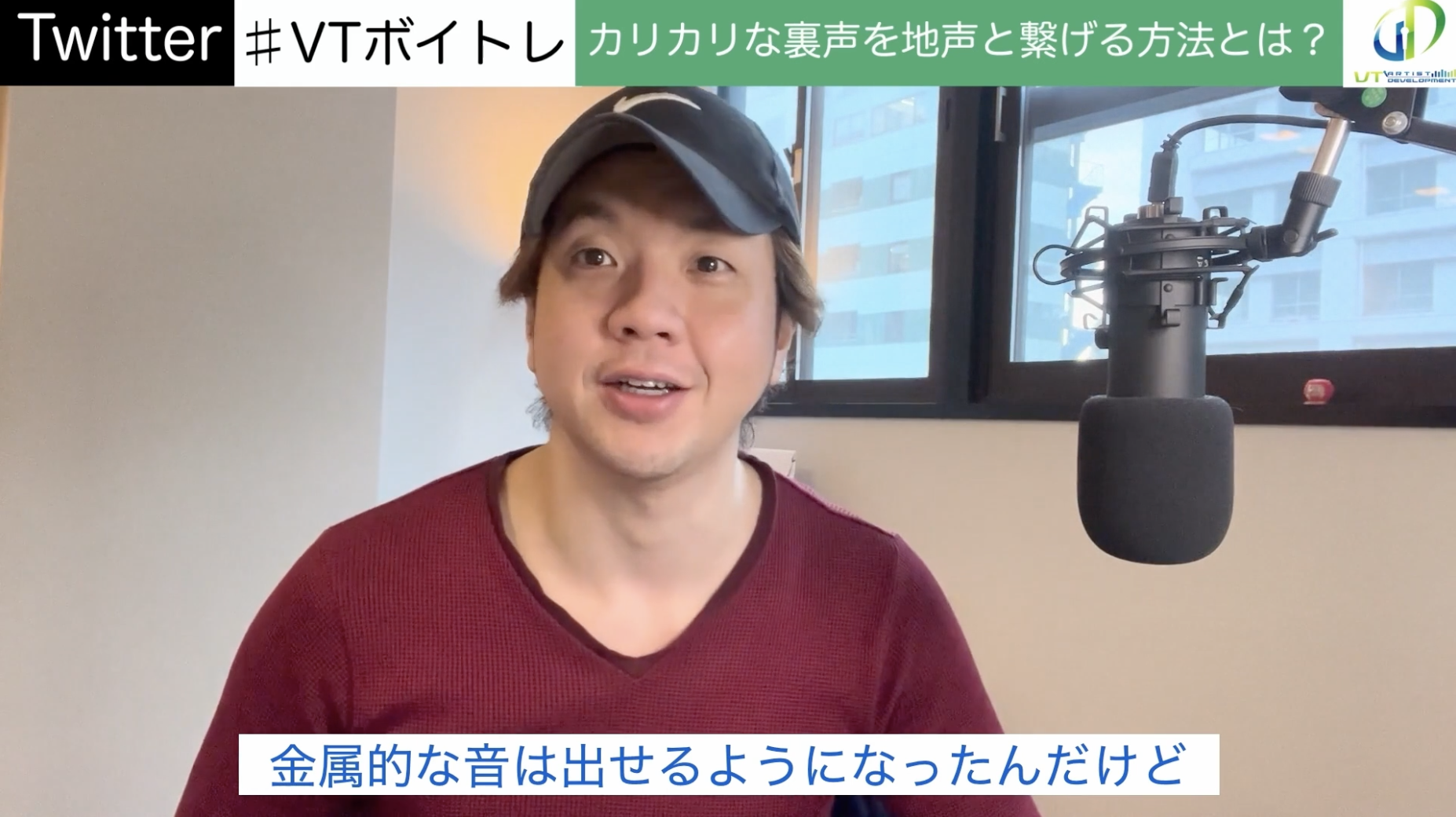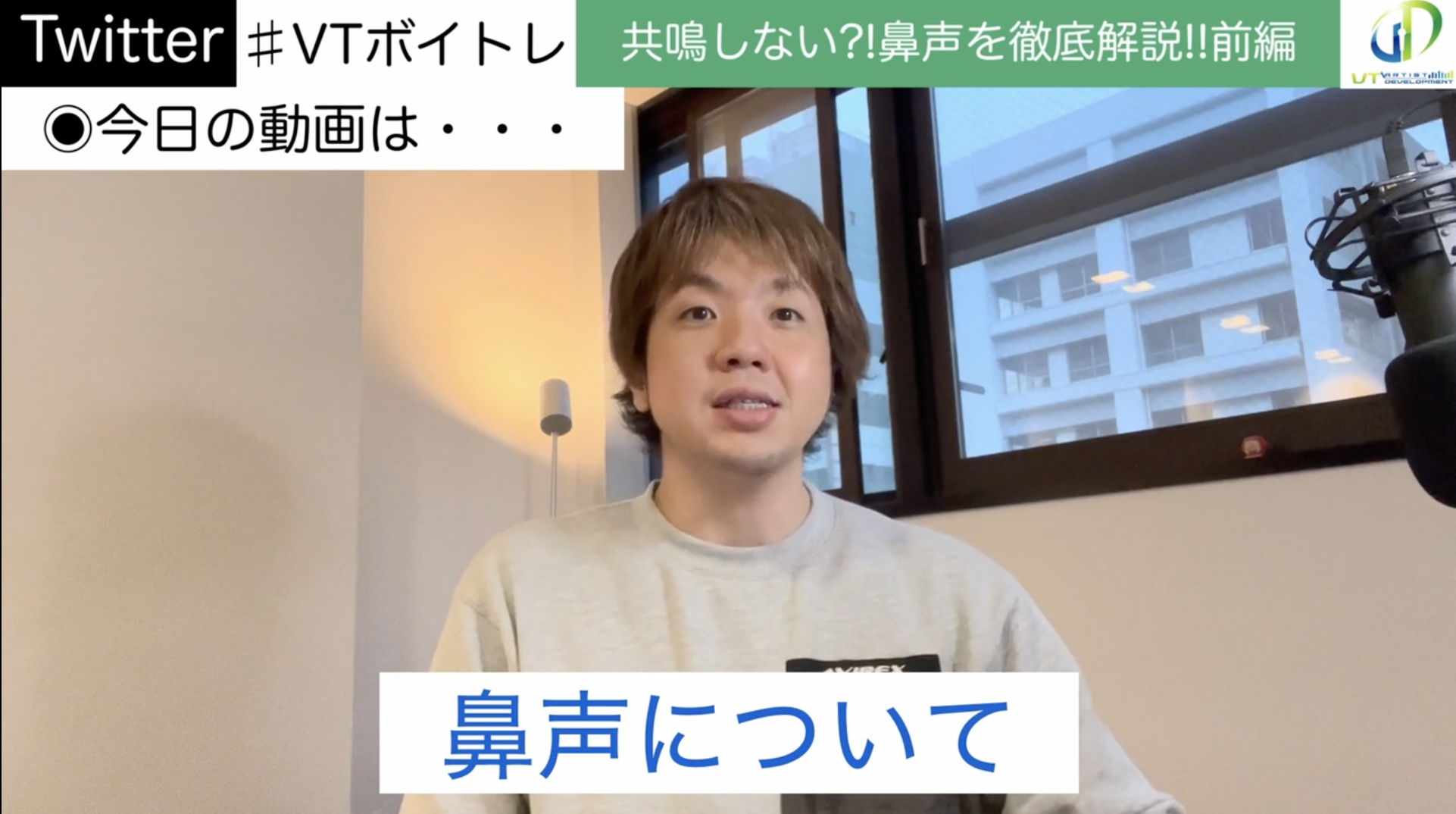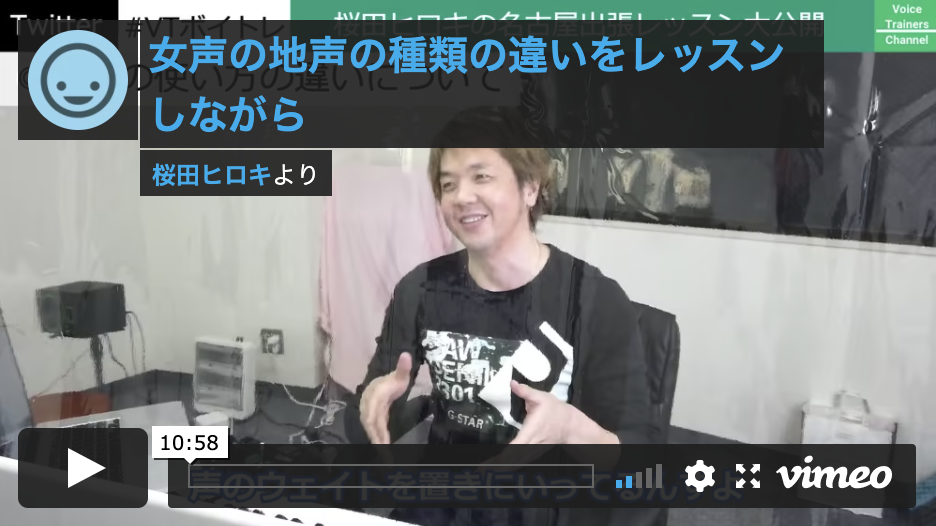第3話:声門閉鎖の計測と耳のつながり
声門閉鎖を理解するうえで欠かせないのが「数値化」です。
歌手やボイストレーナーの耳は確かに鋭いものですが、感覚や比喩だけでは客観性に欠けます。
研究分野では、声門閉鎖の状態をアコースティック指標や音響分析、さらに生理学的計測によって把握することが一般的になってきました。
ここでは代表的な方法であるH1–H2、CPP、HNR、そしてEGG(電気声門図)を取り上げ、耳で聴く声の印象とどのように対応しているのかを整理していきます。
H1–H2(第1・第2倍音差)
H1–H2は、声のスペクトルにおける第1倍音(基音)と第2倍音の強さの差を示す指標です。
H1が強く、H2との差が大きい → 息っぽい声、閉鎖が弱い声。裏声的な発声戦術ともいえます。ポップスやR&Bでは、この傾向をあえて利用して柔らかいニュアンスを作ることもあります。
H2が強く、差が小さい(またはマイナスになる) → 閉鎖が強く、芯のある声。
これは物理的に、声帯がしっかり閉じていると高次倍音が多く発生し、音の情報量が増すためです。
逆に閉鎖が甘いと、基音成分に偏り、高次倍音のエネルギーが不足するため「息が混じった声」「輪郭がぼやけた声」として耳に届きます。
歌手にとって、H1–H2を意識的に変化させることは声色のコントロールに直結します。クラシック声楽では低めのH1–H2を維持して声の芯を確保し、ポップスやジャズではあえて高めにしてエアリーさを演出することもあります。
CPP(Cepstral Peak Prominence)
CPPは、声の周期性の強さを測る指標です。
スペクトルの「規則性の高さ」を数値化したもので、値が高いほど声が明瞭で、低いほど声が不規則で曇った印象になります。
CPPが高い → 周期性が安定し、明瞭な声。
CPPが低い → 声門閉鎖が弱く、または振動が不規則で「疲れ声」や「濁った声」に聞こえる。
H1–H2が「閉鎖の強さと倍音バランス」に直結するのに対し、CPPは「周期性と安定性」を反映しているといえます。
両者を併用することで、声門閉鎖の質をより立体的に評価できます。
実際の臨床研究でもCPPは音声障害の有力な評価指標として広く使われており、声の健康度と密接に結びついています。
HNR(Harmonics-to-Noise Ratio)
HNRは倍音(harmonics)のエネルギーと雑音成分(noise)の比率を示す指標です。
簡単にいえば「どれだけ倍音が豊かに含まれているか」「どれだけ雑音的な成分が混じっているか」を数値化したものです。
Praatと言うソフトウェアで無料で計測が可能です。
HNRが高い → 倍音成分が多く、声が澄んでいる。明瞭で安定した声。
HNRが低い → 雑音成分が多く、声がざらついている。息漏れや疲れ声、声帯の不規則な振動に関連。
HNRはCPPと似た領域を扱いますが、視点が異なります。
CPPは「周期性そのもの」を測るのに対し、HNRは「倍音と雑音の比率」を強調します。
声は倍音と雑音(気流音)で構成されます。
つまり、CPPが「リズムの安定性」を見るなら、HNRは「音色の純度」を見る、と理解すると分かりやすいでしょう。
臨床研究では、HNRは声帯結節やポリープなどの病変を持つ声で低下する傾向が報告されています。
また歌手の現場でも、長時間のリハーサル後や過緊張で声帯が疲れた際にHNRが下がり、「声にざらつき」「透明感の低下」が耳に感じられることがあります。
EGG(Electroglottography:電気声門図)

アコースティック分析だけでなく、EGGも声門閉鎖を理解するうえで重要な計測法です。
喉頭の両側に電極を当て、声帯の接触による電気抵抗の変化を計測します。
非侵襲的で安全に長時間の計測が可能なため、研究と臨床の両方で広く用いられています。
EGG波形からは以下のような情報が得られます。
接触率(Contact Quotient, CQ):声帯が閉じている時間の割合。閉鎖が弱ければCQは低く、強ければ高くなる。
波形の立ち上がりや下降の鋭さ:声帯の閉鎖様式を反映し、Breathy(息っぽい)、Modal(自然な閉鎖)、Pressed(強すぎる閉鎖)といった発声タイプを推定できる。
EGGの強みは「声が空気として出る前の、生理的な声帯レベルの情報」を直接測定できることです。
一方で限界もあります。EGGは「声帯の接触」しか見ていないため、共鳴腔の影響や空気流のデータは得られません。
そのため、H1–H2やCPP、HNRと組み合わせて用いることで、初めて総合的な理解が可能になります。
H1–H2・CPP・HNR・EGGの比較と耳の印象
H1–H2 → 倍音バランス。息っぽさ、芯の強さ。
CPP → 周期性。声の明瞭さ、安定感。
HNR → 倍音と雑音の比率。声の純度やざらつき。
EGG → 声帯接触の直接計測。閉鎖率や閉鎖パターンを把握可能。
耳で聴くと、これらはしばしば同時に変化します。
たとえば息っぽく疲れた声は「H1–H2が大きく、CPPが低く、HNRも低く、CQも低い」というパターンを示します。
逆にプロの安定した発声では「H1–H2が小さく、CPPが高く、HNRも高く、CQも安定」という組み合わせが見られます。
H1–H2とCPPの聴覚印象との対応(補足)
耳で聞いた印象と数値は、以下のようにリンクします。
息っぽい声 → H1–H2が大きい、CPPが低い、HNRも低い、CQも低い。
芯がある声 → H1–H2が小さい、CPPが高い、HNRも高い、CQも安定。
締めすぎた声(Pressed voice) → H1–H2がマイナスに振れる。つまりH1よりもH2の方が大きくなる。
特にベルティング発声の場合、H1とH2がほぼ同等になることもありますが、H2が大幅にH1を超えるような声は「過度な押し声」として扱われるべきです。この状態では倍音バランスが崩れ、響きの豊かさが失われるだけでなく、長期的には声帯疲労や損傷につながる可能性もあります。
現場での応用 ― チェックリスト
桜田の現場経験でも、アコースティック分析やEGGは「耳の感覚を客観化する」ためのツールとして非常に有効です。例えば以下のような視点で、数値と耳の両方から声を評価します。
息っぽさを感じる → H1–H2を確認。
声がぼやけて聞こえる → CPPを確認。
声がざらついている、透明感が落ちた → HNRを確認。
閉鎖時間が短い/過度に長い → EGGのCQを確認。
締めつけ感が強い → H1–H2がマイナスになっていないか確認。
さらに最近では、スマホアプリや簡易ソフトでもH1–H2やCPP、HNRを近似的に測定できるようになってきています。
EGGは専用機器が必要ですが、大学や一部の音声クリニックでは導入が進んでおり、研究と実践をつなぐ重要な架け橋になっています。
まとめ
声門閉鎖の状態を理解するには、耳の感覚だけでなく客観的な数値の裏づけが欠かせません。
H1–H2は「倍音バランス」、CPPは「周期性と明瞭さ」、HNRは「倍音と雑音比」、EGGは「声帯接触」という異なる側面を示しており、それぞれが耳で感じる「息っぽさ」「芯の強さ」「疲れ声」「ざらつき」「閉鎖時間」といった印象に対応しています。
ボイストレーニングや臨床の現場でこれらの指標をうまく活用することで、指導の精度を高め、歌手自身も自分の声の変化を客観的に把握できるようになります。
輪状甲状筋と甲状披裂筋って「どちらが強い」?
地声の時、音程はどうやって作ってるの?
発声筋にも速筋と遅筋がある?
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト
ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!
ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!