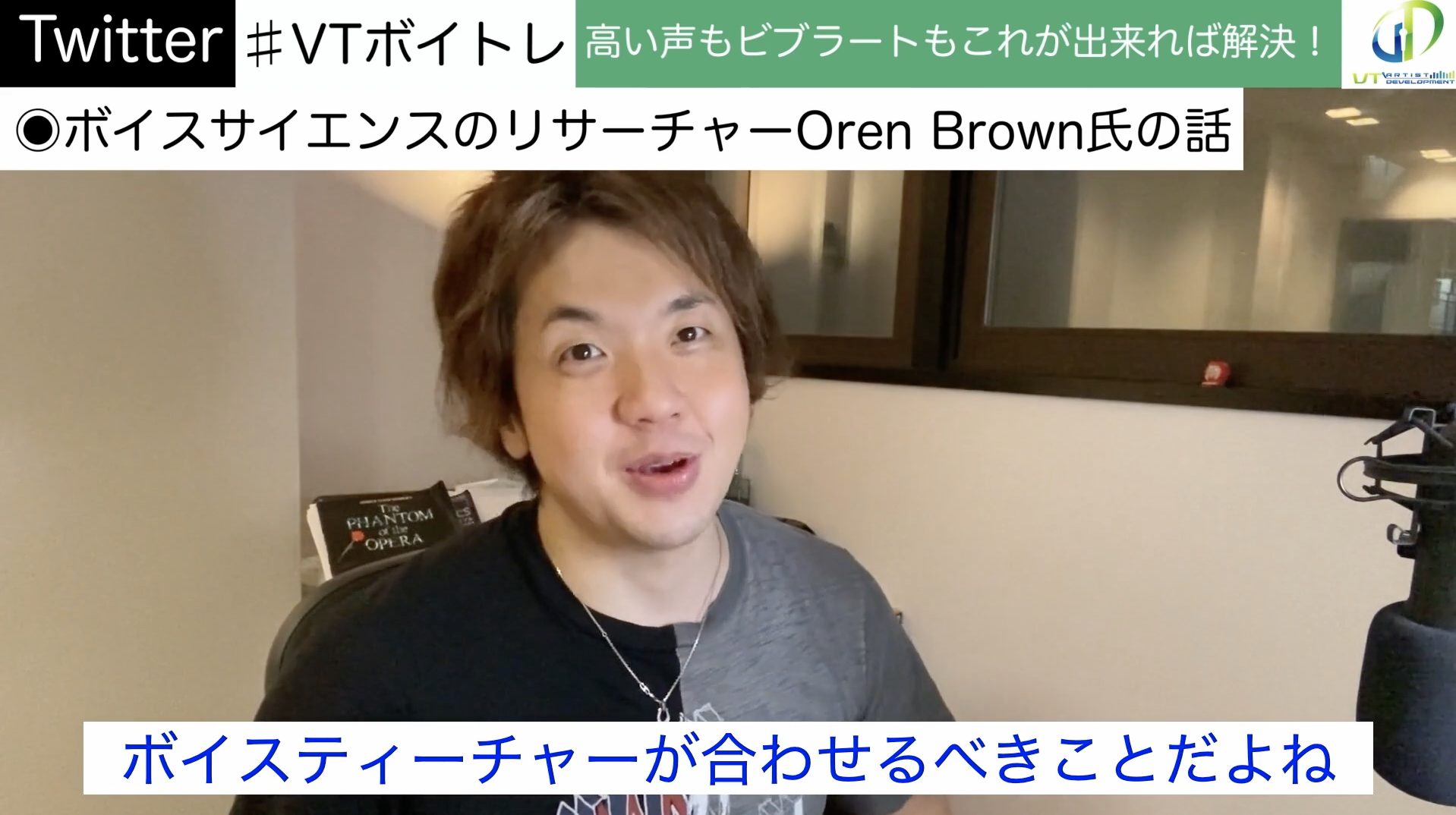歌手が声の不調を感じたとき、その原因を「筋肉の疲労」だと考える方は多いでしょう。確かに筋肉疲労は要因の一つですが、それだけではありません。
過酷な本番や稽古によって“代償的な発声”が習慣化し、機能性発声障害(筋緊張性発声障害)に発展するケースが少なくないのです。
代償発声が招く二次性MTD
MTDには大きく分けて**一次性(Primary)と二次性(Secondary)**があります。
一次性は明らかな器質的異常がないのに筋緊張が起こるタイプ。
二次性は、声帯や周辺機能の異常・負荷に対して、喉頭や首肩の筋肉を過剰に使って“代償”することで固定化してしまうタイプです。

例えば…
・高音を出すときに喉頭を強く引き上げる
・声量を出そうとして仮声帯を締める
・舌や首周りの筋肉を過剰に動員する
こうした代償動作は一時的には音を出せても、結果的に喉周辺の緊張を慢性化させ、声の質や持久力を低下させます。
本番・稽古が引き金になる理由
・長時間のリハーサルや連日の本番
・精神的プレッシャーによる無意識の力み
・怪我や一時的な声帯不調をかばうための無理な発声
これらが積み重なり、「代償パターン」が“通常モード”として体に刻まれてしまうのです。
回復の難しさと専門評価の重要性
代償発声が固定化したMTDは、単純に休養を取っただけでは改善しにくい傾向があります。
さらに、歌唱の特殊性や芸術的要求を理解していない医療現場では、診断が難しく誤診も多いのが現状です。
そのため、声の専門医や歌唱経験を持つ医療スタッフによる評価が欠かせません。
桜田ヒロキも、必要に応じて信頼できる医師の紹介や、発声データの共有を行い、歌手が回復への道筋をつかめるようサポートしています。
改善へのヒント
・練習や本番後の喉・首・舌の感覚を記録する
・特定の音域・音量で力みが出る場合は早期に専門家へ相談
・身体(喉頭筋・舌・姿勢)へのアプローチと発声トレーニングを並行する
・「妥協した方法で出す」より「極端に力まずに出せる方法」を優先する
まとめ
機能性発声障害(筋緊張性発声障害)は筋疲労だけでなく、過酷な負荷によって生じる代償発声の習慣化が大きな要因となることがあります。
歌手として長く歌い続けるためには、声帯の健康と芸術的表現を両立させる発声法を身につけ、早期に専門的な評価とケアを受けることが重要です。
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
声が出しにくくなった!原因を探る
声が出しにくい!?機能性発声障害に陥るプロセスの例を解説
何が原因で声が出しにくくなりますか?
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話