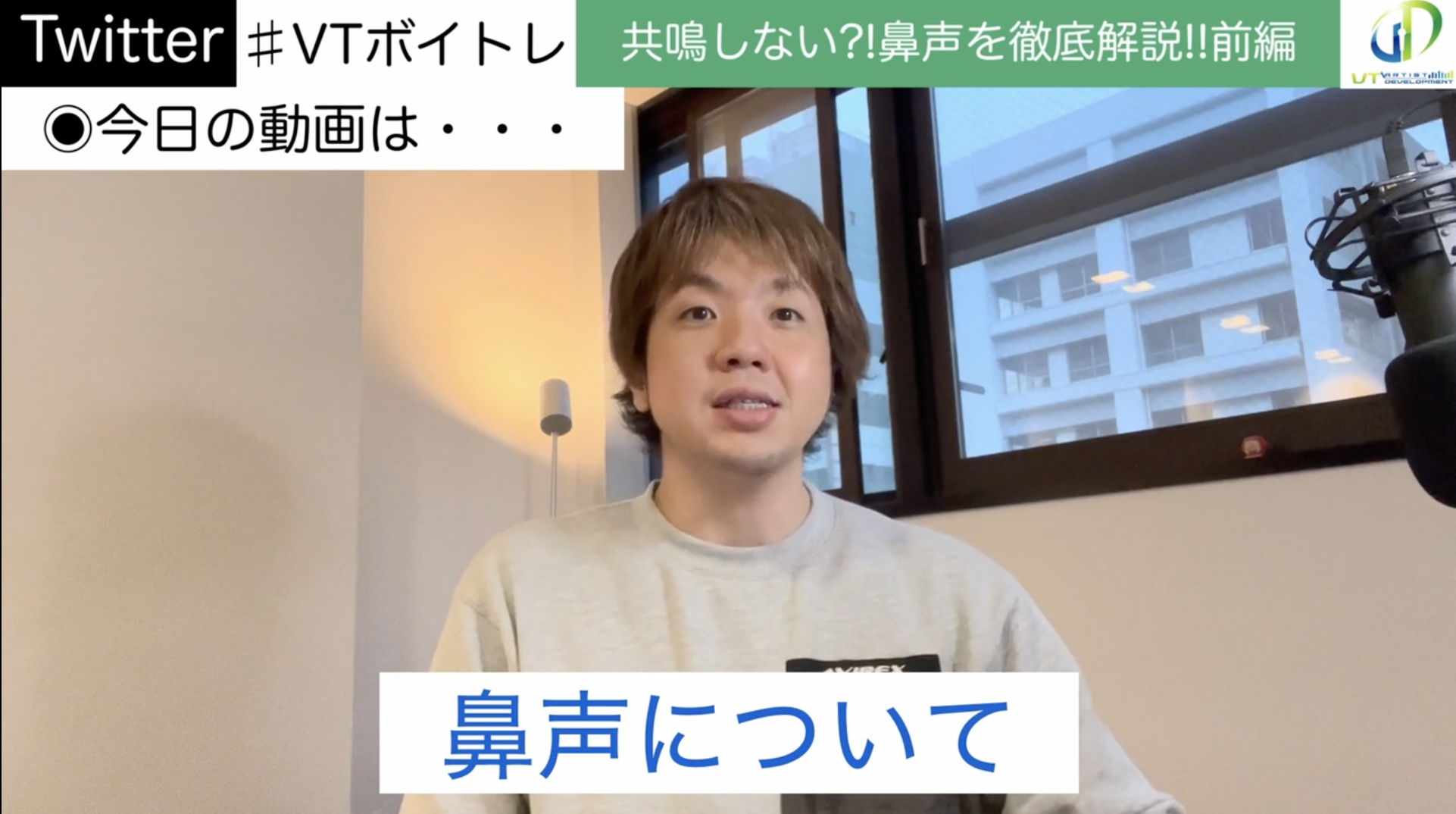- 2025.09.03
- ボイストレーナー育成 ミックスボイス 加齢による声の変化 声の健康法 歌手の発声障害
ボーカルフライとは何か
声帯を極端に低い振動数で鳴らし、声門閉鎖時間が長い発声をボーカルフライと呼びます。
特徴としては、低い呼気流、長い閉鎖期、粘膜波の振幅が抑制されることが挙げられます。
言語聴覚士(SLP)の領域では「声門閉鎖促通」の一手法として古くから用いられてきました。
効能:一時的に声門閉鎖を改善する
- Bolzanら(2008):ボーカルフライ後に粘膜波振幅が改善し、声門閉鎖も向上。
- 臨床報告(小規模):声帯結節や声帯溝症のリハビリに短時間使用すると、声門閉鎖が一時的に改善。
- ケースシリーズ(成人5例):フライ直後に喉頭・鼻咽腔の閉鎖機能が改善。
→ 一時的に「閉じ感」を思い出させるトレーニングとして有効とされています。
リスクとデメリット
- 長時間使用のリスク
30分間連続使用で発声しきい圧(PTP)が0.4 cmH₂O上昇(Svec, 2008)。努力感が増大し、発声負荷が高まる可能性があると報告されています。ただし、このような「30分間連続での実施」は実際のトレーニング現場ではまず行われず、研究的に負荷を観察するための条件と理解するのが妥当です。 - パフォーマンスへの影響
フライ直後に強度レンジが狭まり、声のダイナミクスが制限される報告があります。歌唱前のウォームアップとして多用すると、かえって表現力を阻害する恐れがあります。 - 社会的影響
女性の会話で常用すると「だらしない声」と評価される実験結果があり、声の印象や信頼度が低下する可能性があります。こちらは桜田が知る限り英語圏で言われることであり、日本人女性が日常的にボーカルフライを話し声に取り入れることは少ないようです。
文化比較:ボーカルフライとスウィート・ボイス(おまけ)
ボーカルフライは英語圏において、女性が会話で常用すると「だらしない」「信頼感が低い」と評価される実験結果が報告されています。特にアメリカの若年女性の話し声で頻繁に観察され、社会的イメージや職業的評価にマイナスの影響を与える場合があるとされています。
一方で、日本の女性の話し声には別の文化的特徴が存在します。それが「スウィート・ボイス(sweet voice)」と呼ばれるスタイルです。これは英語圏の研究者が日本人女性の声を国際的に説明する際に用いた用語であり、日常会話で日本人が自ら使っている言葉ではありません。
スウィート・ボイスは、比較的高めのピッチ、息を含んだ柔らかな音質、そして「可愛らしさ」や「無邪気さ」を感じさせる声質を指します。日本文化では「kawaii(可愛い)」という価値観と結びついており、ポジティブに評価されることが多いです。しかし、英語圏の研究者はこの声質について「幼さ」「権威性の弱さ」を印象づける側面があると分析しています。
このように、英語圏でのボーカルフライと、日本におけるスウィート・ボイスは、それぞれ異なる文化的背景と社会的評価を受けていることが分かります。声質そのものに善悪があるわけではなく、その文化や社会でどう受け止められているかが重要なのです。
他手法との比較
- あくび・ため息法(yawn-sigh)
声道の開大を促し、声の強度レンジ拡大に効果が報告されています(フライより有効とする研究もあり)。 - SOVT(ストロー発声、リップトリルなど)
声門下圧を調整し、自然な閉鎖を促す点でフライより安全性が高いとされています。 - レゾナント・ボイスセラピー
軽く響く声を反復させ、効率的な閉鎖を無理なく獲得する手法です。
→ フライは「第一選択」ではなく、「補助的な促通ツール」として位置づけるのが妥当です。
実務への提案
- ・使用は短時間(数セット、各20〜30秒程度)に限定する。
- ・単独で終わらず、必ずSOVTやレゾナント発声で「リセット」する。(ボーカルフライが無理な声門閉鎖を作らないように副作用防止)
- ・声門の後方ギャップを無理矢理「埋める」目的ではなく、「軽い閉鎖を思い出させる補助」として活用する。
- ・クライアントの声の状態に応じて使い分ける。(リアルタイムで声の変化に注目が重要)
まとめ
ボーカルフライは、声門閉鎖を一時的に高める効果が研究で示されていますが、万能ではありません。長時間の使用は発声負荷を高め、表現力を制限するリスクもあります。
したがって、フライは「補助的なアプローチ」として短時間使い、必ず他の方法(SOVTやレゾナント発声)と組み合わせることが望ましいです。
SLPやボイストレーナーにとって重要なのは、「声門閉鎖を強制的に作る」のではなく、「自然な閉鎖と声の流れを取り戻す」ための一手段としてフライを適切に位置づけることです。
本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク
ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜
歌手に多い「機能性発声障害(筋緊張性発声障害)(MTD)」とは?
歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話
加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話