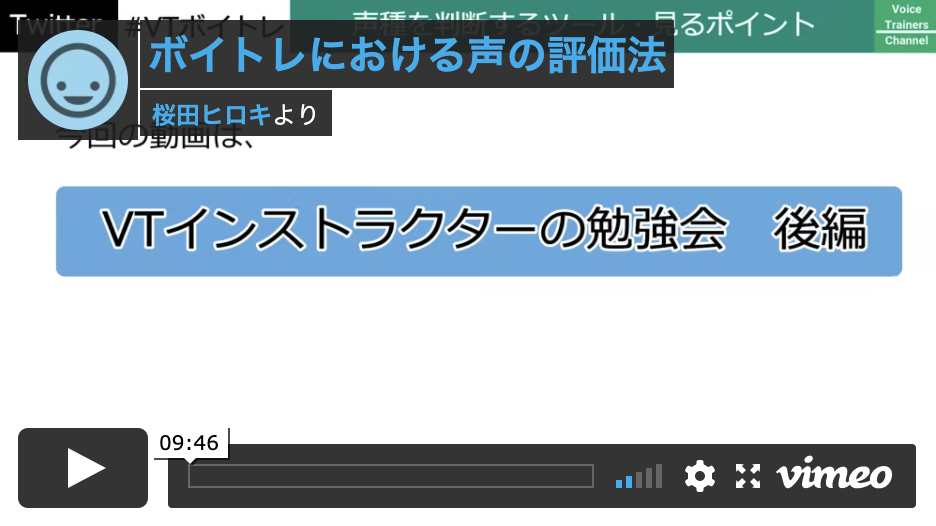”力強いベルティング”発声は本当に、大きな声なの?
プロ歌手の歌唱をYouTube等で観てコメントに「すごい声量だ!」と書き込みを良く見かけます。
プロフェッショナルを多く担当しているボイストレーナーとしては、「それは歌手本人のパワフルな”声色”にだまされているかもしれません」と思います。
桜田自身でも、その声が実際に声量があるかどうかは、マイクの無い状態で、目の前で歌声を聞かないと実際の音量(音圧/SPL)は分からないのです。

実際、プロフェッショナル歌手の中でも発声音量(SPL)には大きなばらつきがあります。
ライブやレコーディングでは“爆音”に聞こえる歌手でも、実際に生の声を数メートルの距離で聴くと「意外と小さい」と感じるケースは少なくありません。この「知覚される声の強さ」と「実際の音量」は、必ずしも一致しないのです。
声門下圧(Ps)が 1.0〜1.2 kPa(約10〜12 cmH₂O) を超えると、声帯粘膜の柔軟な振動モードが制限されることが報告されています(Titze, 2000; McHenry et al., 2009)。
声門下圧が高すぎると、声帯の閉鎖時間が延び(OQが0.3以下に低下)、気流の制御よりも筋的な押し付けによって声が生成されるようになります。この状態では、声帯の振動が粘弾性から弾性優位に変わり、「柔軟に歌う」ことよりも力任せに「押し出す」ことが支配的になります。
結果、音響的にはH1–H2差が減少し(高次倍音が過剰強調)、聴感上は“張り上げたような叫び声”となります。音圧は高くても、音色の一貫性やピッチ安定性は著しく低下します。一般的にピッチは下がりやすい傾向になります。
声の音量を決める3つの生理的要素
音圧(SPL, Sound Pressure Level)を上げるためには、単に“息を強く出す”だけでは不十分です。
声の強さは以下の3つの生理的要素のバランスで決まります(Titze, 2000, Principles of Voice Production)。
声の音量を決める3つの生理的要素
| 要素 | 内容 | 関与する筋群 |
|---|---|---|
| 声門下圧(Ps) | 声帯下の圧力。肺から押し出す力。 | 呼吸支持筋群(横隔膜、外肋間筋など) |
| 呼気流量(Airflow) | 声帯を通過する空気の量。 | 呼吸調整筋群 |
| 声門閉鎖率(CQ) | 声帯が接触している時間の割合。 | LCA・IA・TA筋 |
———-
音圧(Ps)を高めても閉鎖が弱ければ息漏れとなり、
逆に閉鎖が強すぎれば声が詰まり、音量は上がりません。
理想的な「強い声」は、中程度の圧+効率的な閉鎖+安定した気流によって作られます(Titze, 2000)。
発声音量(SPL)の実測値 ― 研究が示すリアル
プロ歌手・俳優・クラシック声楽家などを対象にした研究では、ジャンルごとの実際の音量(SPL)は次のように報告されています。
発声音量(SPL)の実測値 ― 研究が示すリアル
| 研究 | 条件 | 平均SPL (dB @30cm) | 主な所見 |
|---|---|---|---|
| Sundberg et al., 1993, JASA | クラシック vs ミュージカル(女性B4) | クラシック:93 dB ミュージカル:97–98 dB |
ベルトの方がやや高いが、知覚差はスペクトル構造による |
| Garnier et al., 2010, JASA | 演劇俳優(projected vs shout) | 90 vs 108 | 叫びはSPLが高いが持続できない |
| Laukkanen et al., 2012, J Voice | クラシック vs CCM(女性) | 90 vs 98 | CCMは声門下圧が高く、呼気流量が少ない |
| Echternach et al., 2017, J Voice | ベルト vs クラシック | 96 vs 94 | SPL差より倍音構造の違いが支配的 |
————
これらの結果から、「クラシック=静か」「ミュージカル=大音量」という単純な構図は誤りです。
むしろ音響構造の最適化こそが、聴覚的な“強さ”を決定づける要因だと示されています(Sundberg, 2015, The Science of the Singing Voice)。
聴感上の「強さ」は音量ではなく音響効率
Echternach (2017) は次のように報告しています:
「SPLが3dBしか違わなくても、2〜4kHz帯域のエネルギー差が10dBあれば、聴感上の“パワー感”は倍に感じられる。」
つまり、「大きな声」に聞こえる理由は音量ではなく、倍音構造のチューニング(formant clustering)にあります。
これは桜田自身の現場経験でも一致にします。
「すごい声!」と感じる声は決して応援団のような声ではなく、声の密度が高く聞こえます。
実際に音響解析をすると、3kHz以上の高い周波数帯が笛のようになっている事が確認出来ています。
クラシック発声:F₁ ≈ F₀ または F₂ clustering により共鳴効率を最大化。
→ 声帯負荷を最小限にして豊かな響きを作る(Sundberg, 1993, JASA)。
ベルティング:F₀ > F₁を維持しつつ、2〜4kHz帯域でエネルギー集中。
→ 「叫んでいないのに強い声」に聞こえる(Echternach, 2017)。
叫び声:非周期的波形と仮声帯の共鳴でSPLが最大化。
→ 音圧は高いが、音楽的な倍音構造は破綻する(Garnier et al., 2010, JASA)。
実際のSPLレンジ(30cm距離)
以下に様々な研究で上げられた発声法ごとの音圧レベルをまとめておきます。
| 発声タイプ | SPL (dB) | 特徴 |
|---|---|---|
| 話声 | 65–75 | 通常の会話レベル(McAllister et al., 2011, Logoped Phoniatr Vocol) |
| 強い話声(舞台) | 80–90 | 投射声。長時間維持可能(Garnier, 2010) |
| クラシック | 90–95 | 共鳴効率型。喉頭低位・声道拡張(Sundberg, 1993) |
| CCMミックス | 90–98 | バランス型。声門閉鎖と喉頭位置の調和(Laukkanen, 2012) |
| ベルト | 95–100 | 高Ps・低流量・2〜4kHz帯域強調(Echternach, 2017) |
| 男性ベルト | 95–105 | 喉頭高位・TA+LCA協調(Titze, 2000) |
| シャウト | 105–115 | 短時間持続。非線形ノイズ強い(Garnier, 2010) |
| スクリーム | 110–120 | 仮声帯共鳴・ノイズ主導(McAllister, 2011) |
———-
これらの研究を総合すると、必ずしも“プロの歌声=大音量”ではないことが明確になると同時に、ごくごく一部の恵まれた声を除いては、結局声が最も大きく出るのは歌声とはほど遠い素人の叫び声と言う事になります。
クラシック歌手もミュージカル俳優も、共鳴効率を最大化することで、Psを抑えながら十分なSPLを生み出しているのです。
各種発声スタイルと平均呼気流量(Airflow)
| 発声スタイル | 呼気流量(L/s) | 声門下圧(Ps, kPa) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 話声(ナチュラル) | 0.10〜0.20 | 0.4〜0.7 | 話し言葉レベルのSPL(70〜75dB) |
| 地声(モーダル/ミックス含む) | 0.15〜0.25 | 0.5〜0.8 | 最も効率的な範囲。閉鎖と流量のバランス |
| ベルティング(Belting) | 0.10〜0.18 | 1.0〜1.5 | 流量は抑えめ、圧優勢。高SPLだが摩擦増 |
| 裏声(ファルセット/ヘッド) | 0.25〜0.40 | 0.3〜0.5 | 閉鎖が不完全で流量増。SPLは低め |
| クラシック高音(例:リリコ系) | 0.20〜0.30 | 0.6〜1.0 | 声道主導で効率良。安定した支えが重要 |
| 叫び声(Shout/Scream) | 0.35〜0.60 | 1.2〜2.0 | 流量も圧も高い。瞬間負荷が大きい |
| ウィスパー(ささやき) | 0.40〜0.60 | ≈ 0 | 声門開放。摩擦音としての息流主導 |
———-
ここで興味深いのが、
・ベルト発声が100dB程度。叫び声は110dB程度
→音楽的な声でないと認識されやすい、継続性が低い、怪我のリスクが高い、を除けば結局音量が最も多いのは叫び声。
しかしながら前の章で書きましたが「「SPLが3dBしか違わなくても、2〜4kHz帯域のエネルギー差が10dBあれば、聴感上の“パワー感”は倍に感じられる。」を忘れずに。音楽的な声色とパワー感を両立させてこそ一流です!
・呼気流量(リットル/秒)はベルト発声が0.10〜0.18リットル程度。叫び声は0.35〜0.60
→呼気の効率性は圧倒的にベルトの方が良い。練習の仕方のヒントとして「むやみに息を吐いてはいけない」も勉強になりそうです。
・声門下圧(キロ・パスカル)はベルト発声が1.0〜1.5キロ・パスカル程度。叫び声は1.2〜2.0程度
→叫び声は声帯の下圧が非常に高く、怪我のリスクが高い、疲労しやすい。ベルト発声は呼気流量を下げる事で声門閉鎖を誘発しているので、叫び声より遙かに省エネで怪我のリスクは低い。
これらが考察出来そうです。
呼気流量平均値の目安(男女差を考慮した中央値)
注記:数値は代表的研究(Rothenberg 1981/Sundberg 1987/Titze 2000/Verdolini 1998/McHenry 2009/Tan 2017 など)のレンジを統合した目安です。個体差・キー・SPL・母音・発声条件で変動します。
声の“存在感”は倍音構造で決まる
音圧レベル(SPL)は音量そのものの指標ですが、聴き手に届く“声の存在感”を決めているのは、 むしろスペクトルの整理(高次倍音のバランス)です。
桜田ヒロキ氏の現場経験でも
「音量が小さくても、倍音構造が整理された声は“遠くまで通る”し、マイク乗りが良い!。」
これは声門閉鎖のタイミング(CQ)と、LCA・IA筋による後部閉鎖の安定性によって支えられています。
強い声とは肺圧で押し上げた声ではなく、音響的に効率の良い声なのです(Titze, 2000)。
ケーススタディ ― 「音量を下げて音域を広げる」
あるバリトンのミュージカル俳優(『オペラ座の怪人』の怪人役を務める)が、
地声域の強化トレーニングの中で「音量を少し抑えた裏声と地声の関係づくり」や、
アジリティ(機敏性)を取り入れた練習を行ったところ、
結果的に地声の最高音域が大きく伸びたという例があります。
このケースでは、「爆音を出さないこと」が逆に声門閉鎖の効率化とCT・TAの協調を促し、より高音でも“響く声”を維持できるようになったと考えられます(桜田, 現場観察, 2024)。
まとめ ― 「声の強さ」と「声の健康」
“強い声”は必ずしも“音量が大きい声”ではない。
叫び声のような高SPLは長時間維持できず、損傷リスクが高い(Garnier, 2010)。
実際のプロ歌手の多くは 90〜98dB前後 の範囲で発声している(Sundberg, 1993; Laukkanen, 2012)。
声の存在感は「倍音構造」「閉鎖タイミング」「共鳴バランス」で決まる(Echternach, 2017)。
機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括
声門閉鎖と高音発声を理解する ― シリーズ総まとめ
輪状甲状筋と甲状披裂筋って「どちらが強い」?
地声の時、音程はどうやって作ってるの?
発声筋にも速筋と遅筋がある?
この記事を書いた人

-
米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。
科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。
日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。
倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。
歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。
最新の投稿
 ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!
ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!
ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密
ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?
ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?